|
本書より抜粋引用
 カトリック信者にとって、ミサや、聖体、告解などの秘蹟の授け手である司祭の有無は、信仰生活の維持にかかわる カトリック信者にとって、ミサや、聖体、告解などの秘蹟の授け手である司祭の有無は、信仰生活の維持にかかわる
問題である。だからこそ、かのキリシタン迫害時代、あるいはメキシコ革命下にあって、司祭は生命を賭けて信者を
訪ね、秘蹟を執行したのであった。
弾圧者の脅しと、ある意味では甘言に乗せられて、島から司祭を一人残らず失ってしまった奄美大島の信者たちの
宗教的苦悩は、弾圧に耐える苦しさ以上のものであったはずである。
本土の教会上層部がこの引き揚げを決定したのは、要塞地帯のこの離島で問題をこれ以上悪化させないことが、
島はもちろんだが、それ以上に日本の教会ぜんたいの利益のためであると判断したからであろう。そして、さらに
外国人宣教師に代わる日本人司祭の派遣も、結局は断念した底流には、ぎりぎちの判断としてやはり同じ配慮が
働いていたに違いない。いや、このときはもう、念頭にあったのは「日本の教会ぜんたい」だけだった。
個々人の日本人司祭の中には、進んで奄美大島への挺身を名乗り出た人は、松下や梅木以外にもいたらしい。
しかし、教会当局としては、梅木の場合を特別の例外としたほかは、最終的にはそれをとらなかった。繰り返し
言うが、奄美大島の事態をこれ以上こじらせることは、日本の教会ぜんたいのためにならなかったのである。
それにしても、これがもし本土の一部の地域、たとえば長崎の五島ででも起きたことだったら、はたして同じような
処置で終わったものかどうか、多分に疑問が残る。もっと日本の全教会あげての、ねばり強い、断固とした交渉
ないし抵抗がつづけられたのではないか、という気がしてならない。
奄美大島のカトリック信者は、二重に裏切られたわけである。まず、外国人宣教師を追放することが弾圧の目的
であるとうそぶいた軍部から、そして、外国人宣教師を引き揚げさせることは島の状況から適切だったとしても、
意図はともあれ、現実にはその「穴」を埋めえなかった教会上層部からも・・・。
当時、信者数、10万の日本ぜんたいの教会のために、3500人の奄美大島の信者が犠牲にされたということに
なる。昭和10年から敗戦までの10年間、奄美大島3500人・・・弾圧下での棄教者もふくめて・・・のカトリック信者
は、司祭も秘蹟もなしに、つまりは実際問題として教会なしに放置された。放置したのはいったいだれだったのか?
戦争激化とともに、本土でもキリスト教にたいする風圧は強くなっていったが、それでも、すくなくとも表面上は、
「大政翼賛」とやらの波に巧みに乗ることによって、大勢としてはことなく切り抜けてきた。だが、それはヤマト
(本土)の教会だけであって、そこにはもうシマの教会はふくまれていなかった。シマはいつもヤマトのつごうしだい
で、簡単にヤマトから切り捨てられる。
思えば、この島はこれまでどれほどヤマトの犠牲になってきたことだろう。薩摩の財政をうるおし、明治維新の
大事業を完遂させたのは、この島の資源と労働力であったし、そのあくなき搾取が、形こそ変えても、明治に
なっても改められなかったことは、すでに見てきた通りである。近くは敗戦にさいして、本土は沖縄とともにこの
島を切り捨てたのであった。

私はそのとき、ああ自分はヤマトの人間、島の人々がいう「ヤマトンチュ」なのだと、つくづく痛感した。しかし、すでに
島へ数度足を運んでいた私の頭からは、以前には持っていなかったかもしれない「ヤマト即日本」いいかえれば
「ヤマト以外は日本ではない」という考えは払拭されていたようである。私がつぎに抱いたのは「日本って広いんだなあ」
という感慨だったから・・・。「ヤマトだけではない日本」という広がりをもって自分の国を見直すことができたのは、
島尾敏雄氏(大戦末期、加計呂麻島の震洋特攻隊の一隊長であったことが氏と奄美とのかかわりのはじめであった)
の奄美にかんする数冊の著書に負うところが大きかった。いずれにせよ、私の奄美体験は、むしろ日本というものを
私にとって痛快、爽快なまでに拡大してくれたのだった。
私のわずかな体験と印象からだが、私は妙に南の古仁屋という町に心ひかれる。かつて軍人相手の花街として栄え、
昭和のはかない「栄光」とともにそれに終止符を打って、戦後はひっそりと、しかし、貧しいながらもおのれを持して
生きているといった風情が、とりわけ旅人の感傷をそそるのかもしれない。
また、この町は大正年間に過激な反軍運動を生んだように、奄美における進歩思想の濫觴の地でもあった。当時、
長髪のいわゆるアナーキストの志士たちがふところ手で闊歩する姿が、見られたものだそうである。
小1時間もあれば隅から隅まで歩き回れる小さな町である。そのどの町角、どの路地で出会う人々にも、やさしさ、
なつかしさが感じられた。これも旅情のなせるわざか。
しかし、私はジェローム神父の「古仁屋は世界でいちばん住みよいところ」という言葉に、彼の実感としてすこしも誇張
はないと思った。
そのジェロームも、主任司祭時代をふくめて、古仁屋に住んでもう10年近くになる。老境に手の届いた年齢だが、
元気に大股で町を歩く長身の姿に、幼稚園帰りの子どもたちが、「神父様、神父様」と、甘えるように大きな声を
かけていた。

二人はそれぞれの家から、薄暗いあぜ道を、懐中電灯で照らして教会にやってくる。晴れた日は、満天に星がちり
ばめられている。どの家々も、深い眠りの中である。波の音が教会の祈りの席まで伝わってくる。
平和な集落である。巡査も隣村まで行かなければいけないが、犯罪など起こったことはない。隠居老人の集落の観が
あると書いたが、最近、すこしずつ若者のUターン現象も見られるという。それにしても、僻地の小さな小さな集落・・・。
「みんなが協力しなければ、とても成り立たない。宗教のことで喧嘩なんかしていたら、やっていけませんよ」と人々は
実感こめて語っていた。それぞれの宗教の自由を確認し合ったあの集落の常会も、その共通の認識の所産なので
ある。
しかし、じつはこのことは何も「小さな集落」にかぎったことではあるまい。人間の共同体というものをどんなに大きく、
地球大にまで拡大しても、原則は同じではないだろうか。
宗教の違いとそれに伴う誤解や偏見が生んだ「交際絶交」や「排撃」がどのような不幸な結果をもたらすか、奄美大島
の人々は高価な代償を支払って学んだのである。しかも、ことは単純に「加害者」を責めるだけですむ問題ではなかっ
たと思う。もちろん、意図的な宗教弾圧を進めた軍部の場合は論外だが・・・その無法と恐ろしさについては、もうここ
で繰り返す必要はないだろう・・・彼らにそそのかされて直接の「加害者」となった素朴な島民たちにたいしては、
「被害者」もまた負うべき一端の責任を有していた。まして、彼らが信仰者、宗教者であればなおさらである。宗教は
人間の平和と一致と幸福のために存するのであって、断じてその逆ではないのだから・・・。
|



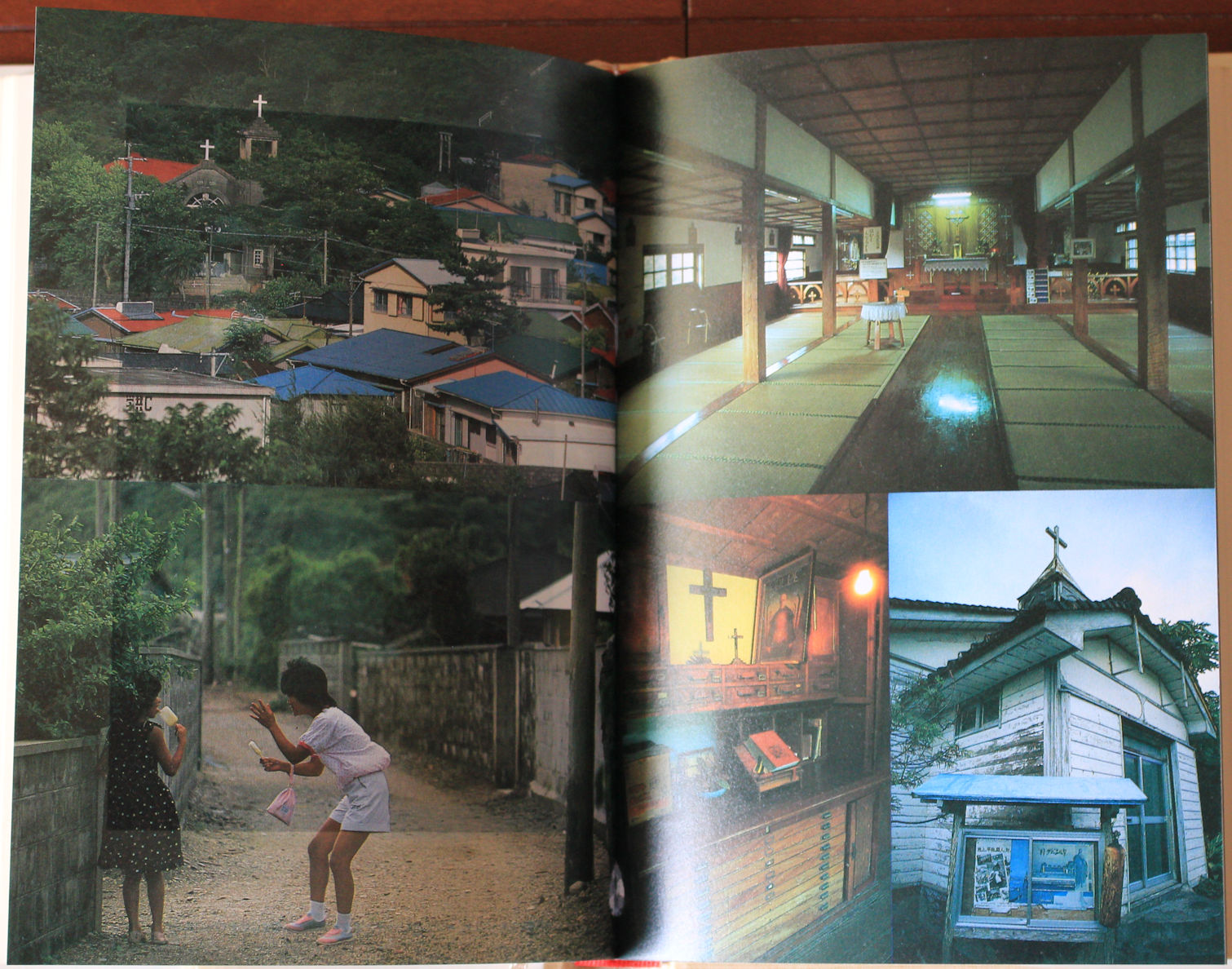
![]()
