 AllPosters |
 AllPosters |
![]()
|
�������i�ȂǂȂ��̂��낤�B���Ƃ��S�̕Ћ��ɃL���X�g���̎O�ʈ�݂̂̌���^���s�����p�Ɉ،h �������Ă��Ă��A�C���f�B�A���ɑ�\������Z�����̐��Ȃ�ւɖ������Ă��鎩����F�߂��� �����Ȃ�����ł���B�ނ�̂˂Ɏ������̎q��������z���A����@���ɍl�������čs������ �������_�ɁA��F����n��ꂽ�n����̎����ɖ������p���v�������ׂĂ��܂��̂��B���̗y�� ���Â���p����Ă���������́A����͑n���傩��̑�����̂ł���A�ނ��Z���͓��X�� �c�݂̒��ɑn����̑����������Ă����B����Ȕނ�ɂƂ��ăL���X�g���̌����u�߁v�Ƃ����T�O�� �����邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�n����A���тɂ��̑z������葱���Ă����c��̑z���������Ă��� ���̎�������n�ɗ��Ă�̂ł���B���̊��ӂƊ�сA�����Ď��̐���֎p���ӔC�B���̐��Ȃ� �ւ̒��ɂ̓L���X�g���̌����u�߁v�̈ӎ��͂Ȃ��A���ӂƊ�тƋF��̌����ނ���ݍ���ł����B �����炭�ނ��Z�������������g���u��������Ă���v���Ƃ��A�m���ł͂Ȃ��̂̈��̍זE ��ʂ��č��ɍ���ł����l�X�ł��낤�B�l�ԈȊO�̐�������́u�^�������v�ɂ���ď��߂Đl�� �͐����邱�Ƃ��o����B������^���Ă��ꂽ�S�Ă̂��̂ɑ��Ă̊��ӂƋF�肪���邩�炱���A �����Ă��邱�Ƃւ̐[����т�����B�������A�L���X�g���k�������炵�����̂̑����́A�j��ƕ��� �Ɩ\�͂ł����Ȃ��B���̂悤�ȃL���X�g���Ɏ��͉��̂��䂩��Ă���̂��낤���B����͂����� �\���ˏ�̃C�G�X�́u�^�������v�̒��ɁA�n����̐[�������������Ă��邩��Ȃ̂��낤�B�S�� ���C�Ƃ��������悤�̂Ȃ������̌��`�������Ɍ��Ă���̂����m��Ȃ��B�߂������Ƃɗ��j�́A ���̌��`�Ƃ͑S���������ߌ���n��o���Ă������Ƃ��L���Ă���B�L���X�g���k�͓O��I�ɂ��� ���Z���̑n����̎����ɖ������ڂ�D���łڂ��Ă����B�L���X�g���k���ނ��Z�����ɗ��� �n����̎p�A�^���s�����n����ݖłڂ����Ƃ������Ƃ͉��Ɣ���Ȃ��Ƃ��낤�B���������� �̌��ł��Ȃ����������̌����A��ؐl�ƌ�����l�̒��Ɍ��o�������̍��f�Ǝ���̗]��ɂ� �����܂����p�ɐ�ɂ������A�ނ�L���X�g���k�͂��̂��ׂĂ��f���o������łڂ��s�����B����� �܂�ŃC�G�X�ݏ\���˂ɂ��������̂��̂̎p�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ʂ����Đ�Z�����̍��ɗ���� ����錹���ƃL���X�g���̌�������������葱���Ă��鐹�Ȃ����̂��낤���B����Ƃ����� ��͍�������邱�Ƃ̂Ȃ��S���َ��Ȃ��̂Ȃ̂��낤���B���ɂ͂킩��Ȃ��B�����u�^�������v �n����̎p���A�ǂ���̐�ɂ��f���o����Ă���̂��������ĂȂ�Ȃ��̂��B���������Ď��� ���́u�^�������v�����������Ă���Ƃ͌����Ȃ��B����Ȏ��ɂƂ��āA���̖₢�������m�ł���A �܂��Ă��̐��Ȃ��ɂ��Č�鎑�i�������Ȃ��B���x�ƂȂ�����̗~�]�Ɉ��������A�r�ꋶ�� ��͂Ɋ��x���ۂݍ��܂�Ă��܂��B���̂悤�ȑ����̒��ɂ����āA�����o����Ƃ����̂��낤�B �������͂��̒��ق̒��ɂ����Ă��A�n���傪���̎���~�낵�Ă���邱�Ƃ�҂��̂��݂����B 1999.7.9
���B�����̍��͂���ׂ��l�Ԃ̎p�A���n�̃L���X�g���̎p���_�Ԍ������A������i�������Ă� ��Ɗ����Ă��܂��B�܂���Z���̍��ɂ��Ă��u�A�����J�E�C���f�B�A���v���Q�Ƃ��Ă������������ �v���܂��B�F���܂̒��ɑ����̓��Ȃ�o����Y�܂�܂��悤�ɁB
|
![]()
 AllPosters |
�Ö{�ɂ����ẮAAmazon����ԏ[�����Ă��邩���m��܂���B �܂��u���E�U�uFirefox�v�ł̓����N�悪����ɕ\������Ȃ��ꍇ������܂��B |
������ǂ̂悤�ɑ����Ă����̂������g�킩��Ȃ��ł��܂��B |
|
![]() �e������
�e������![]() �������ƕ\�����тɕ����̌��t���o�܂��B
�������ƕ\�����тɕ����̌��t���o�܂��B
![]()
 |
����E���a�����E���a�F�O���@1998�N1��6���B�e
�i�傫�ȉ摜�j
|
�@����E�ܓ��̓V�哰�@�@ |
|
�w�ǎc���Ă��Ȃ��B���������܂ꂽ�̋��E����͂ǂ�ȏ����낤�Ƃ����z���Ƌ��ɁA �A�b�V�W�̐��t�����V�X�R�ւ�ʂ��ăJ�g���b�N�ɂЂ���Ă����������̎��͓Ɛg�� ��A���T�Ԃ����Ē���̓V�哰�����ĉ�������Ƃ�����B�w�Ǎs����������� ��̗��ŁA���ɂ͐Q��ꏊ���Ȃ��V�哰�̑O�ň�Ӗ����������Ƃ����������A���� ���͎��ɂƂ��ċM�d�Ȏv���o�ɖ������Ă���B���̐S�Ɉ�ԋ����c�������́A �����ۂɂ��������Ƃ������ŁA���Q�ꑽ���̃L���X�g���k���ܓ��Ȃǂɓ� ��Ă������A���������̒��̈���B�h�𑁒��o�ēV�哰�Ɍ����������A���x�w�Z �̓o�Z���Ԃŏ��E���w������������Ă����B�����͉����̂ł���̂��A�Ƃ����₢ �������Ƌ��ɔ������̂͂��̎��������B�����������E���w���̑S�Ă������m�炸 �̗��l�ł��鎄�Ɂu���͂悤�������܂��v�ƏΊ�ň��A�������̂��B���Q�ɑς����l �����̎q���ɂ��p����Ă����L���X�g���̔����B���̎��A�����v�����̂����� �����������U�̔��������o�������A��Γ�l�ł��̓��ɗ��悤�ƌł����������̂��� ���B�����ĉ������猩�铰�X����V�哰�A�~�T�̎�����ɓ��肫��Ȃ��قǑ����̐M �ҁB���̎����炱�̍����̋���͎��ɂƂ��ē��ʂȑ��݂ɂȂ����B���N��A���͍D ���Ȑl�Ƃ��̍����ɍ~�藧���Ă����B���̎��̎v���͎U�����u���ʂĂʖ��v�ɏ��� �Ă��܂��B�ޏ��ƌ�������ꃖ���O�A���͉��l�E�R�苳��Ő�������B�얼�� �u�A�b�V�W�̐��t�����V�X�R�v�B�V�����s�ōs�������̓C�^���A�ŁA�����o�`�J���� �@�����n�l�E�p�E���Q���ɓ��{��������Ă������R�_������̈ē��Ńo�`�J���� �����ē����Ă�������B�@���l�̋F��̕����̋߂��ɃK���X�P�[�X������A�甼�� �Ђǂ�����̐Ղ����܂ꂽ����A����͍ŏ��̏}���Ґ��X�e�t�@�m�̂��̂� �����B�Q�O�O�O�N�߂��O�̈�̂����s���邱�ƂȂ��ڂ̑O�ɒu����Ă���B��ʂ� �ό��q������Ȃ��Ƃ���܂ŁA���R�_������͈ē����Ă��ꂽ�B�X�C�X�q���Ɏ�� �ꂽ������ŁA�w��Ɋ����������̊ό��q�̎����ɁA���߂����\����Ȃ��C�� ���ƁA���̂悤�Ȍ��h�Ɍb�܂ꂽ�Ƃ������G�ȐS���Ŏ������͕������B�O�q�����@�� �l�̋F��̕�����}���Ґ��X�e�t�@�m�̈�̂����J����Ă͂��Ȃ��ꏊ�ɂ���B�� �̒��ň�ԐS���h�蓮�����ꂽ���̂́A�S�O�������傫�ȕ����̓V��ɕ`���ꂽ �lj悾�����B����͖Ӑl�̕����`�������̂ŁA�Ȃ̏�������Ċ����������Ƃ����� �Ƃ����ꂽ���A�����Đ��쒆�̕v�w�̎p��lj�̒��Ɍ��o�������A�M�ƈ���� �����������ɐS��D���Ă����B�A�b�V�W�ł��C���@�ɂ������{�l�_���̈ē��Ő� �t�����V�X�R�̂䂩��̒n���ē����Ă�������B���X�e�t�@�m�Ɠ������V�O�O�N���������� �������ϐF���~�C�������Ă�����̂̕��s���Ă��Ȃ����N�����̈���B���t�����V�X�R�� ���܂ꂽ�ƁA�ނ�����������Ɏg��������ՁA�����Đ��t�����V�X�R�̌�肩���� �\���˔G�A�C������̓؏����A�V���[�k�E���F�C�������܂�ď��߂ĂЂ��܂��� �ċF�����������|���`�E���N�������B�S�Ă̎v���o���܂�ō���̂悤�Ɋ������� ���܂��B�����E�o�`�J���E�A�b�V�W�A�����ɓ����ꂽ���̂悤�ȗ������Ă������A���̍s �������悪�����Ȃ̂����̎��ɂ͂킩��Ȃ��B���x���������A�L���X�g���Ɛ�Z���� ��������T���Ă���̂����m��Ȃ��B���̗��͂܂��I�����}�����Ȃ��ł� �邪�A���̏o���_�ƂȂ����̂͒���E�����ۂƂ������Ƃ����͊m���Ȃ̂��Ǝv���B |
![]()
|
�@�~���ҁE���@ �V���� |
2012�N6��9���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B 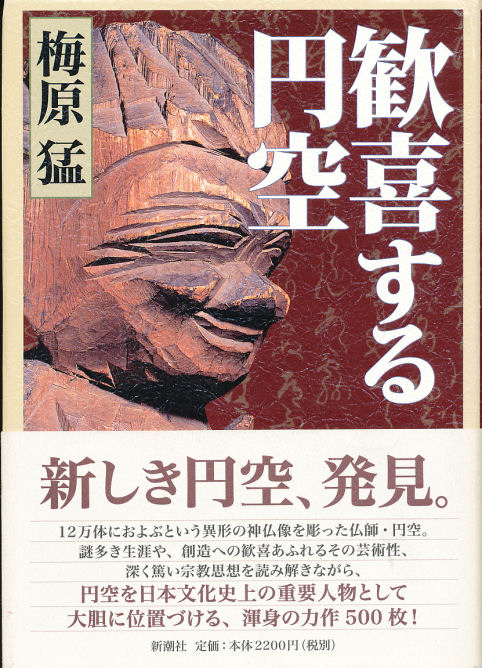 4��16���ɓ��e�����~��̑��A�����ƒm�肽���Ǝv���u���삷��~��v�~���Ғ���ǂ݂܂����B �]�ˏ���1632�N�A���ɐ��܂ꂽ�~��́A���ɂ���k�C���܂ő���L���āA��n�ٕ̈ς���߁A �l�Ԃ��肩���ׂĂ̏O�����~�����߂�12���̂̕�����܂��B �~����ꕶ��������̐_�ƕ������K���������C���҂ł������A���̐��U�͏�ɏO���~�ς�ړI�Ƃ��A 64�̂Ƃ��ɒ��ǐ�Ȃɂē��肵�܂����B ����Ƃ͓y���̐Ύ��Ȃǂɓ���A�@��o���ꂸ�ɖ��܂����܂܂̑��g���̂��Ƃ������܂��B ���ǐ�Ȃ����̒n�Ƃ��đI�̂́A�^���̊Q��h�����Ƃ���~��̋����ӎu�������Ă���A���� �͔ނ̐��ꂪ�^���Ŏ��Ƃ����~�����̉����𗠂Â�����̂������ł��B �܂��y�n�̐l�X�͒��ǐ�ɑ吅���o��Ɖ~��̗삪�ւƂȂ��Č����A�������߂�Ƃ��������` ��������܂��B ����̑O�q�|�p�𗽉킷��~���Ɍ����銴���A�����Ęa�̂Ɍ�����_�X�ƗV�Ԏq�ǂ��� �悤�ȉ~��̍��A���͉~��ɖ������Ă��܂��܂����B ���̕����ŐS�Ɏc�����ӏ������ɏЉ�悤�Ǝv���܂��B �������� ���~��͎��ɂƂ��Ă��͂��l�̌|�p�Ƃɂ����Ȃ����݂ł͂Ȃ��B�ނ���ނ͎��ɐ_���K���v�z�� �[���閧��������N�w�҂Ȃ̂ł���B ���w�~��̏W�x�̘a�̂ɂ́u�y�v�u��v�u���v�Ƃ������t�������Γo�ꂷ��B���͉~��̎v�z�̒��S�� �����Ă����сA�y���݂��^���邱�Ƃł���Ǝv���B����͂܂��ɐ_�X�̐��炩�ȗV�тł���B �����͂����Č��������B����A�~��̉̏W�𐼍s�́w�R�ƏW�x�ƂƂ��ɓǂ��A���s�̉̂��~�� �̉̂̕��ɂ�苭���������o�����B�~��̉̂𐼍s�̉̂Ɣ�r����ȂǁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł���� �����̐l�͌�����������Ȃ��B�������ɉ̂Ƃ��Ă͐��s�̉̂̕����͂邩�ɍI�݂ł���B�܂��A�~�� �̉̂ɂ͌뎚��E��������A�u�Ăɂ��v������Ă���B�ɂ�������炸�A�~��̉̂ɂ͍��܂łǂ� �悤�ȓ��{�l�̉̂ɂ������Ȃ��Y��Ȑ��E�ς����ł��Ă���B�܂�����Ñ�l�̐����������Ă� ��悤�ł���B ���u�Ղ���@�Y�̌�_���@�N�z�ւā@���������ց@�����q�i�����̂ˁj�m�t�v�i��ꎵ�O�j �t�ɂȂ�N���������B���������Y�y�i���Ԃ��ȁj�̐_���J���āA�傢�ɏ����A�q�ǂ�������B �NJ��̂悤�Ɏq�ǂ������Ɩ��S�ɗV��ł���~��̎p���ڂɕ����Ԃ悤�ł���B���̏��̐��_�� ��C�̐��_�Ɍ��т��B���͎Ⴂ���A�l����s���E��]�̑��Ɍ�������N�w���玩�Ȃ�������� ���߂Ɂu���̓N�w�v�Ȃ���̂��\�z���A�������l�ቺ�Ƃ����T�O�ōl�������A���͂��̂悤�� �T�O�ʼn��߂����ׂ����̂ł͂Ȃ��B���̎��͂܂����͋�C�̌����u��v�Ƃ������̂��悭������ �Ă��Ȃ������B���悤�₭�~���ʂ��ċ�C�́u��v�̈Ӗ��������͗����ł���悤�ɂȂ����̂� �͂Ȃ����Ǝv���B ���u�V�ʂ�́@�c���t�́@�ԂȂ邩�@���ɑ����i���������j���@�V�ӕ��́i���܂Â��j�v�i��l���j ����͍��̎��̐S�����҂���ƕ\�������̂ł���B�~���̉̂�������̂͘Z�\���ł���Ǝv ���邪�A���͂����肳��ɓ�\�N�̍��Ƃ�A���\�����B���̂悤�ȘV�l�ɂ��t������� �ł���B���͂܂��Ԃ��炩�������B�w��̉ԁA�|�p�̉Ԃ��炩�������B�w���|�p�͂��傹��V�� �Ȃ̂ł���B�V�т̂Ȃ��w���|�p�͂܂�Ȃ��B��҂����S�ɂȂ��ėV��ł���悤�Ȋw���| �p�Ȃ����āA�ǂ����Đl������邱�Ƃ��ł��悤���B�~��̕�������͒n���ٕ̈ς���߁A�l�Ԃ� ���肩���ׂĂ̏O�����~�����߂ł������B��F�͐l���~�����Ƃ�V�тƂ��Ă���B�������̍ɂȂ��� �悤�₭��F�̗V�сA�~��̗V�т������Ă����B���̗V�т͑����Ȃ�V�тł�����B�V�тƑ����A�� ��͂ӂ��͌��т��Ȃ��T�O�ł��邪�A���ꂪ���т����Ƃ���ɉ~��̌|�p�̔閧�����낤�B �������� (K.K) |
![]()
|
�@����̐_��ƃ��[���X�E�Y���f���̐l�Ɨ쐫�@ �����J��������@�Җ�@���q�p�E���� |
|
�J�g���b�N�n�̗c�t��������A���W���[�X�_�������V�X�^�[�B���^�c���Ă����B������ �̑̌��͂��܂�v�������ׂ邱�Ƃ͏o���Ȃ����A�������̓��ɂ�������������}���A �̑��̉��Ƃ������Ȃ����M�ȁA�����Ă��ׂĂ��ݍ���ł����悤�Ȃ��̋F��̎p�ɁA ���̐S�͂Ђ�����ꖣ�����Ă������Ƃ����͑N���Ɏv���o�����Ƃ��o����B�C�� �ۈ����ɋ߂Ă������̎d���̓s���Ŋe�n��]�X�Ƃ��邪�A���Z������߂������{�� �̓���ŁA�J�g���b�N���NJ��l�ƌ���ꂽ���їL���_������́u������ɒl���閽�v�Ƃ� ���Ռ��I�Ȗ{�ɏo��B���̗��e�̓L���X�g���ł͂Ȃ��̂ɉ��̂��̖{���Ƃɒu���� �������̂����ł��s�v�c�ł��邪�A�����D�F�̐t����𑗂��Ă������ɂƂ��āA�� �̖{�͐l�Ԃ́A�����Đ����邱�Ƃ̑f���炵�����_�Ԍ������Ă��ꂽ���̂������B���̂� ���ȏo����������ɂ��ւ�炸�A���͋���ɍs�����Ƃ͂Ȃ������B�ڂ������Ƃ͎U���� �ɏ����Ă��邪�A���̌�V���[�k�E���F�C���ɖ������A����_������̕����ŃA�b�V�W �̐��t�����V�X�R��`�����f��u�u���U�[�E�T���@�V�X�^�[�E���[���v�ɐG��A�J�g���b�N�� �M�ɋ����Ђ���Ă������B�����ĒP���f�p�ȃJ�g���b�N�̐M�����ȂƂ̌�����O �ɉ��l�̋���Ő������B���̃��[���X�E�Y���f���_���Ƃ̏o��́A���ꂩ��b ���o���Ă���̂��̂ł���B�L���X�g���̉��`�A�O�ʈ�݂̂̌���^���s�����p�A���Ǝq �Ɛ��삪���ꂼ��Ɏ����^���s�����A�����Ď������푢���ɑ��Ă��A�Ђ��܂����ꂵ ��ł�����_�̎p��S�ɉf���o���Ă��ꂽ�B���̃��[���X�E�Y���f���_���͌���̐� �t�����V�X�R�ƌĂ�A�n�����̒��ɐ����ꂵ�ސl�Ƌ��ɕ��l�ł��������A�ނ̎v �z�͓����ْ[�����ɂ���l�X�ȋ����]�X�Ƃ�������B�ނ̐����Ȃ������҂ŁA�� �ɔނ����������c�p�E���U���ɂ���ă��@�`�J���ّ̖z�w���ɏ����ꂽ�͔̂ނ����� �R�N�O�̂��Ƃł���A���U�̑唼�͋^���̖ڂŌ����a���Ă����B�ނ������� �Ɉ₵�����̂͂Q�T�N�o�������ł��A�l�X�̐S�ɎO�ʈ�̂̐_�̎p��N�₩�ȐF�ʂ� �F���������ĉf���o���A���ق�ʂ��Č��ꂽ�_�̌����́A��������l��l���Ǒ̌� ���邱�ƂȂ��ɂ́A���ɂ��̍����~�낷���Ƃ͂Ȃ����낤�B�܂��ɔނ͂��ׂĂ̑��݂� �w��ɂ���n����̑����ɐG��邱�Ƃ��ł������x�̍��������̂��̂ł���A���� ���ɔ��˂��ꂽ��]�Ɗ�т͎������̍��̉��[���܂Ŋт��Ă���̂����m��Ȃ��B
�u���Ȃ镟���v������A���ꂼ�����q�p�E��������o�ł���Ă��邪�A�ǂ������ �ł����ɂ͂����Ȃ����̂ł���B
|
|
2011�N12��21���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B
|
![]()
|
�@ ���}�i�E�}�n���V�� �R���O�Ȗ�@�߂邭�܁[��� |
|
��ꂽ�[���Ȏ�����^�ɗ������邱�Ƃ��o���Ȃ����낤�B�u���فv��ʂ��ď��߂Đ^�� �u�m�v�͎Y�܂�A����͌����Ďv�ٓI�Ȓm�����܂Ƃ����Ƃ͂Ȃ��B�C���h�Ɍ��炸�C���f�B �A���i��Z���j�A�L���X�g���̈̑�Ȑl�X�͂��́u���فv���玩��̑��݂̑b��z���� �����B���}�i�E�}�n���V�ɂƂ��Ă���́u�g���͍݂�h�Ƃ������o����������A�z���͂Ȃ��B �g���͍݂�h�Ƃ����o���́A�Â��ł��邱�Ɓv�Ȃ̂ł���B���̗]��ɂ����X�������㕶�� �Ɋ���Ă��܂������������y���ޕ��ɖY��Ă��܂������́B����͈�̂Ȃ낤�B
|
|
�C���h�I�Ȏt�i�O���j�ł������B�P�V�ɂ��Ď��Ƃ̊������A���_�̎����̍��ɍĐ��� ���ނ́A��C���h�̃e�B�����@���i�}���C�ɂ����āA���N�Ԃ̒��ق̂̂��A���ՂȌ��t�� �[���^�������n�߂��B�v��R�O�]�N�A�ނ��ҍ������A���i�`�����̐Ԃ��R����́A�� �Ȃ���̔��������������˂�@---�@�u���͒N���v�B�@�i�{���ѕ����j
|
|
��Ȃ�ʂ��̂������Ă���B�C���h�ɂ����Ĕނ́A������Ԃ̓��Ȃ�ł�������_�ł���B ����ꂪ�V�����E���}�i�̐��U�Ƌ����̓��ɔ���������̂́A�ł������ȃC���h�ł���B �C���h�̉��������ꂽ���E����ѐl�ԊJ���̌ċz�́A�ЂƂ̐�N�����̐��̂ł���B ���̃����f�B�́A�����ЂƂ̑傢�Ȃ郂�e�B�[�t�ɓY���đt�ł��Ă���A����̍ʂ�� ���˂��āA�C���h���_�̓��ɂ˂ɂ��ꎩ�����Ԃ点�Ă����̂����A���̍Ō�� ���g���A�V�����E���}�i�E�}�n���V���̐l�ł���B���ȂƐ_�ꎋ���邱�Ƃ́A���[���b�p �l�ɂƂ��ẮA�ЂƂ̃V���b�N�Ƃ��ċ����ł��낤�B���̂��Ƃ́A�V�����E���}�i�̌��t�̓� �Ɏ�����Ă���悤�ɁA���ʂɃI���G���^���ȁu���Ȏ����v�ł���ƌ�����B�S���w�́A���� �悤�Ȏ��Ȏ����̖�����镪�삩��͗y���u�����Ă���Ƃ������n�̑��ɂ́A�� �ЂƂ��̖��ɍv�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���C���h�l�ɂƂ��ẮA���_�̌��� ���Ă̎��Ȃ́A�_�ƈقȂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��Ăł���A�l���ނ̎��Ȃ̓��� �݂邩����́A�ނ͒P�ɐ_�̓��Ɋ܂܂�č݂邾���łȂ��A�_�䎩�g�ł�����Ƃ������� �����Ăł���B�V�����E���}�i�͊��S�ɁA���炩�ɂ��̌��n�ɂ���B�i�����j�@����䂦�� ���m�̒q�d�Ɛ_���`�́A�ނ炪���g�̌ŗL�̌��t�Ō��Ȃ�A����ꐼ�m�� �l�Ԃɓ`����ׂ����ɑ����̂��Ƃ������Ă���B�����͂����ɁA���������� �Ă͎��g�̕����ɂ����ē��l�̂��̂������Ă������A���łɖY�ꋎ���Ă��܂��Ă��邱�� ���v���o�����Ă���邵�A����ꂪ�d�v�ł͂Ȃ����̂Ƃ��ĕ����̂��Ă��܂������́A ���Ȃ킿�A�����̓��Ȃ�l�Ԃ̉^���Ƃ��ĕ����̂��Ă��܂������̂ւƁA����� �̒��ӂ������߂��Ă����B�V�����E���}�i�̐��U�Ƌ����́A�C���h�l�ɂƂ��đ�Ȃ��� �ł���Ɠ����ɁA���m�l�ɂƂ��Ă���Ȃ��̂ł���B����́A�l�Ԃ̍ő�̊S���� ���Ă̋L�^�ł������łȂ��A���ӎ��̍��ׂƎ��Ȑ���̌��@�̒��Ŏ������g�� �r�����鋰��̂���l�Ԑ��ɂƂ��āA�ЂƂ̌x���̃��b�Z�[�W�ł�����B�i�����O�j
|
![]()
|
�@ �e�I�h�[���E�C���I���� �їz��@���ԏ��X |
|
�ł���A���̍����p�I�Ȗ��@�̓A�h���t�E�q�b�g���[�ɂ�����ȉe����^�����B���� �Í��̒n�ꉤ���ɌN�Ղ���u���̌N�v�͒��҂ɂ����V�g�i�_�̂悤�ɂȂ�� �Ɨ~���A���̂��߂Ɏ���̉h�����������V�g�����j���̂��̂������B�C���I���Ƃ� ���ނ���ȒT���ƁA�_��v�z�̎�����ł����ׂ����Ȃ����������ׂ��̌��L�^�B �������{���̐^�̉��l�́A���̈Í��̐��E�ƑΛ�����`�x�b�g���l�̎����ɖ� �������ɗ����Ă���B�C���I���������悤�ɁA���́u�ڂ�����ނ���̒��Ƃ����� �����ޗ��̒�v��I�Ԃ͎̂�������l��l�̎��R�ӎu�ł���B���̌��ƈł̐� �E�̕����ꓹ�ɁA�����`�x�b�g�̌��l�̋F��͎�����������ׂ����ւƓ����A ����ׂ������w���������W�Ƃ��ė��������Ă���̂��낤�B
|
|
�s�s�ɏ�����A�ł̔閧���ЂŎO���Ԑ��������ɂ����̂���ՓI���҂��ʂ����܂ł́A ��ɂ��Ăԋ��|�̑̌���L�B���̒����A�W�A�̒n�ꐢ�E�Ɏ��ۂɎQ�����A�����ł̑̌� ���ڍׂɕł����T���Ƃ̓e�I�h�[���E�C���I���B��l�ł��낤�B�u�`�x�b�g���҂̏��v�� ���сA�ꕔ�̃`�x�b�g�����Ƃ̊ԂŔ鑠���Ƃ���Ă����C���I�����̒�����킪���̓ǎ� �ɍL���ł��邱�Ƃ́A�傫�Ȋ�тł���B�u���҂̏��v���g�\�h�̃`�x�b�g�������Ƃ���A �{���͂܂��Ɂg���h�̃`�x�b�g�������Ƃ����悤�B�@�i�{���E�������j
|
|
�̈�l����������t�ł���B���̌��t�͂����l�ɂ��肩�A�l�ޑS�̂̉^���ɂ������� �������B�Ƃ��̂��邵�͐V���Ȃ鎞����Ă���B����͂������ɂ܂ł��Ă���̂��B�V ���Ȃ鎞��A����͂��悫���̂ƂȂ邾�낤���B����Ƃ����ȏ�Ɉ���������ƂȂ�̂��� �����H�@�����琔�Z���`�̂Ƃ���ɐ�ǂ͂���B�����ꏭ�Ȃ���A�����̒N�������E�� �����ɉ��S���Ă���B����̐ӔC�����o���悤�ł͂Ȃ����B�`�x�b�g�̌��l�����͐��̏o�� �������߂͂��邪�A�ނ�������悤�ɁA���W�Ƃ��Ă̖�ڂ��ʂ����Ă���ɂ����Ȃ��B�ނ� �͑��l�̎��R�ӎu�Ɍ����Ċ����Ȃ��B���̓����Ƃ邩�ł̓����Ƃ邩�́A�l�Ԃ̎��R�� �̂ł���B�����ɂ����l�Ԃ̉h��������B�����͗�I�Ɋw�ׂΊw�ԂقǂɐӔC���傫 �������Ă���B�����̐S�̉���ɂ́A�ȓI�Ȉ��̉ΉԂ��B����Ă���B������ ����A�^���̎��Ȃƒ��a�����Ă�����̂����ꂾ�B���̑��삪�������Ƃ��A��I�� ���v�����������ڂ݂Ȃ��u���v�������̐����̎w�������ɂȂ�A�����Ă���m���Ɨ͂� ���́A�������đ����Ă���ӔC�ƌ������̋C�����ɂ���āA�����I�Ƀo�����X���͂� ���悤�ɂȂ�B���̂��Ƃ��A�킽�����`�x�b�g�̐��_��������������ߒ��Ŋw�тƂ����ő� �̋����������B�i�@�e�I�h�[���E�C���I���@�{�����@�j
|

![]()
���{���j�Z�t����i�q�������ɏΊ���j