|
本書 訳者後書き 大島由起子 より抜粋引用
 白人と先住民。この両者には相対立する面があったものの、まだ論じ尽くされていない相互浸透も 白人と先住民。この両者には相対立する面があったものの、まだ論じ尽くされていない相互浸透も
あれば相互転化もあった。ヴィゼナーは、真の先住民(彼の表現では「ネイティヴ」と、偽の、つまり白
人に都合のよういように構築された先住民(彼の表現では「インディアン」)とを峻別する。彼に従えば、
インディアンは文化人類学、民俗学などにさんざん利用されてきた。インディアンはネイティヴの不在
を模倣する。白人は、自分たちが合衆国で主役を演じ続けるためにネイティヴを抹殺し、替わりにイ
ンディアンという自分たちに都合のよい先住民像を捏造した。
真の先住の民であるネイティヴは、逃亡者のふりをして潜伏するしかなかったというのだ。初めは意図
的な潜伏であっても、幾世代を経て、都会で単独で生きる混血がすでに1980年には全先住民人口の
半分を超えるうちに、白人の価値観を内面化していきインディアン化してしまう先住民も出ている。もう
自分な何を失い、何を取り戻すべきか分からなくなった者も増えた。自身が都市部の混血であるヴィ
ゼナーはそうした切迫感を持って書いている。
例えば、ヴィゼナーの父は、例のドーズ法によって、居留地の仲間同様に都会に移り住む羽目になる。
大恐慌後の1930年代に職を探すわけだが、先住民は家屋に住まないのだからペンキの塗り方など知
らないだろうと言われ、ペンキ塗りの職に就けない。そこでイタリア系だと偽って職にありつく。ヴィゼナ
ーは彼らが「ふり」でもしなければ生計も立てられなかった現状を踏まえ、なりふり構わず「ふり」をして
ネイテヴらしく生き抜いた先祖を愛しむ。
ヴィゼナーの祖母にしてもそうだ。福祉に頼って生きている彼女が、人種や境遇を問わず、自分を必
要とする人には愛情を注ぐ。行商先の郊外で、裕福だが孤独な白人主婦が、自分の売ろうとしている、
おそらくはつまらない商品になど見向きもしないで、一方的に身の上話などをするのに耳を傾け、トリッ
クスターのお話をしたりして相手を癒す。報酬を期待しての事ではなく、ささやかな悦びを感じつつ。
ヴィゼナーは、彼女が都会で彼女なりに、先住民のポトラッチ(与え尽くし)を行なっているのだという。
つまり、儀式の日に行う伝統に従ったポトラッチではない。混血が日々の都市生活のなかで変容した
型で執り行なえるポトラッチである。こういった、ヴィゼナーの提言する儀式や伝統の自在な応用は、
どのような時代、状況になろうとも、先住民が(ひいては困難を抱えて生きている誰もが普遍的に)、
生きる指針としてゆけるものを備えていると思われる。父や祖母のような社会の底辺をうごめく先住民
を描く時、ヴィゼナーの視線は地を這うように低い。一方、白人受けを狙って立ち回るインディアンに
対してはヴィゼナーの舌鋒は鋭い。
ネイティヴの先祖が「ふり」をして、先住民の民でありながら逃亡者のように潜伏してきた以上は、当然
のことながら、先祖探しは困難を極める。そうしてヴィゼナーはネイティブが書いた「自伝」に、トリック
スターのお話に、あるいは写真の中のレンズを見据え挑みかかるような被写体の目に、ネイティヴが
いた痕跡を見い出す。ネイティヴが白人に口述して英訳された「自伝」にしても、民族衣装を着せられて
撮られた写真の姿も、白人との接触なしにはそもそも存在しなかったのであって、純粋にはネイティヴ
の痕ではない。が、それでもネイティヴの片鱗をまさぐるには貴重なのだ。
私事になるが、初めは本書の語り口の潔さと、先祖として誇れるような先祖を探そうとする切迫感、呪
詛のように寄せてくる言葉の波に引き込まれた。(拙訳は日本人読者を想定して説明的になってしまっ
たが。)北米の大地に詰まっている先住民の死骸と怨念、文学、絵画、写真、野外歴史劇、博物館で、
徹底して不在者として扱われてきた先住民を、墓なき大地から立ち上げようとするヴィゼナー。インデ
ィアンしかいないと言い募られてきたが、自分たちはこのように立派な先祖がいたではないか、彼らが
いたことまで葬り去るなと迫るヴィゼナーの姿勢に、息がつけない思いがした。合衆国の裏面史だけ
でなく、動物と人間の境がなくおどろおどろしくもあるシャーマニズムやトーテミズムも、私の理解を阻
み、ともすれば暗い魅力を湛えた書だという第一印象だった。
が、読み返していくうちに、気負って本書に向かっていると、逆に漏れ落ちる部分が多そうだと、また
別の不安に駆られるようになった。本人が述べているように、ヴィゼナーは白人の批評理論をネイティ
ブに引き付けて茶化して使い、ネイティヴの世界の猥雑で騒々しいまでの大らかさも盛っている。むし
ろそれこそが、この本の著しい特徴であって、そういった明るさも聴こうとしなくては、ヴィゼナーの魅
力の半分も掴めないだろう。
白人の先住民観を批判することは夥しい数の批評家がやってきた。ただ、先住民ならではの、こちら
に不意打ちを食らわせるような生き生きとした世界へと、これまでどれほどの先住民が読者を導いた
だろうか。ヴィゼナーにとっては、快活でおしゃべりで、馬鹿な見栄を張りたがり、気前がよく、均整な
どとれていない状態を居心地良く感じる人々が、ネイティヴである。こういった明暗。あるいは固さ柔ら
かさのスペクトルの幅もまたヴィゼナーの身上である。それが、生きているうちから不在者とされてき
た恐怖と悲しみを塗りこめているようでもあり、かと思うとふざけているようにも響く。本書の表題『逃亡
者のふり・・・・ネイティブ・アメリカンの存在と不在の光景』にも表れている。
ヴィゼナーはどこに向かおうとしているのだろうか。彼は時代は変わったのだから、逃亡者のふりなど
終わらせなくてはならないと提言している。先住民は辛酸を嘗めさせられてきて、今だに全体としては
アメリカ社会の最下層を占めている。しかし中には社会的、経済的に力をつけた者も増えてきた。居
留地のカジノで大儲けをした昨今、物議をかもしている成金もいる。また、混血がほとんどだとはいえ、
現在活躍中の先住民作家の大半が、大学で教えているか教えた経験がある。ヴィゼナーは、社会的
地位を得た先住民が白人に対して復讐に出ることを強く戒める。このような、報復の連鎖を断ち切る
ようにと提言する箇所では、指導者めいた響きすらする。(キリスト教でいえば山上の垂訓のように)
ネイティブらしい大らかさを忘れたところに、ネイティヴらしい生き残りも、ネイティヴの文学もありえな
いとヴィゼナーは繰り返す。
|


![]() 「逃亡者のふり ネイティブ・アメリカンの存在と不在の光景」
「逃亡者のふり ネイティブ・アメリカンの存在と不在の光景」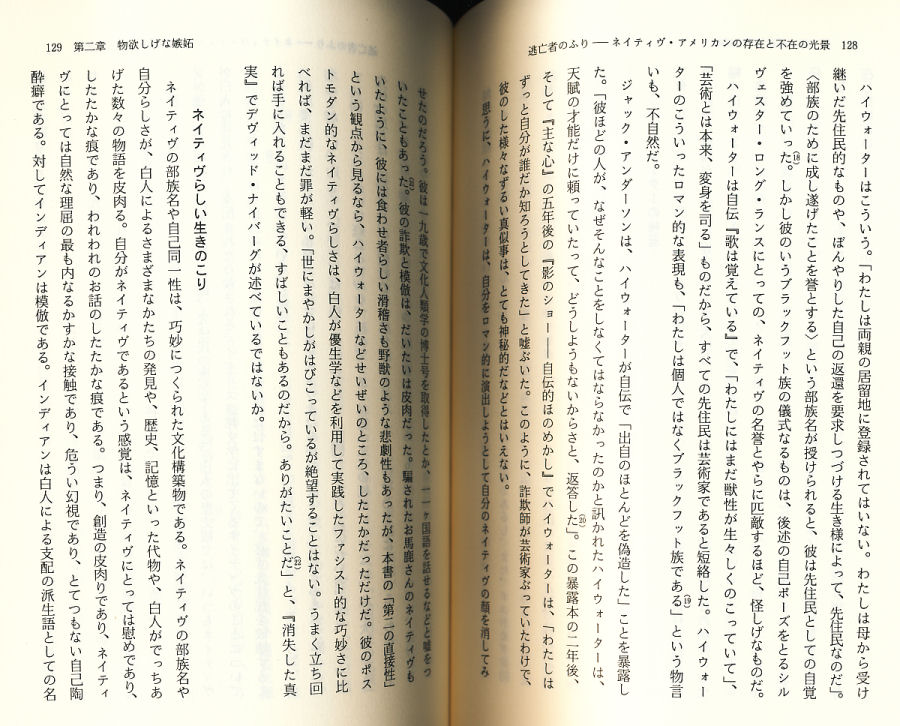
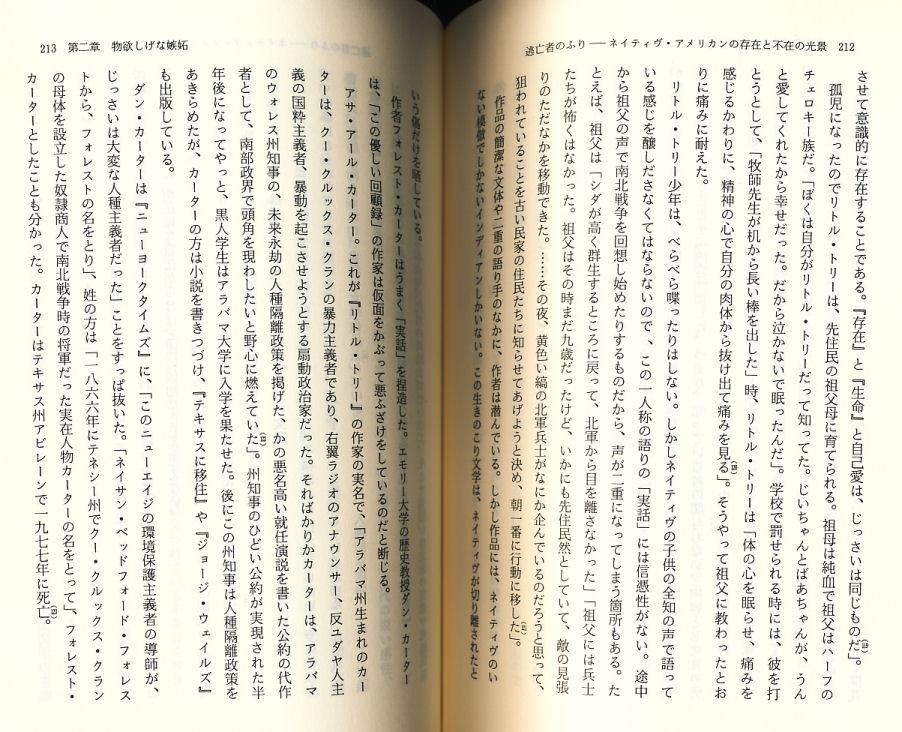
![]()
