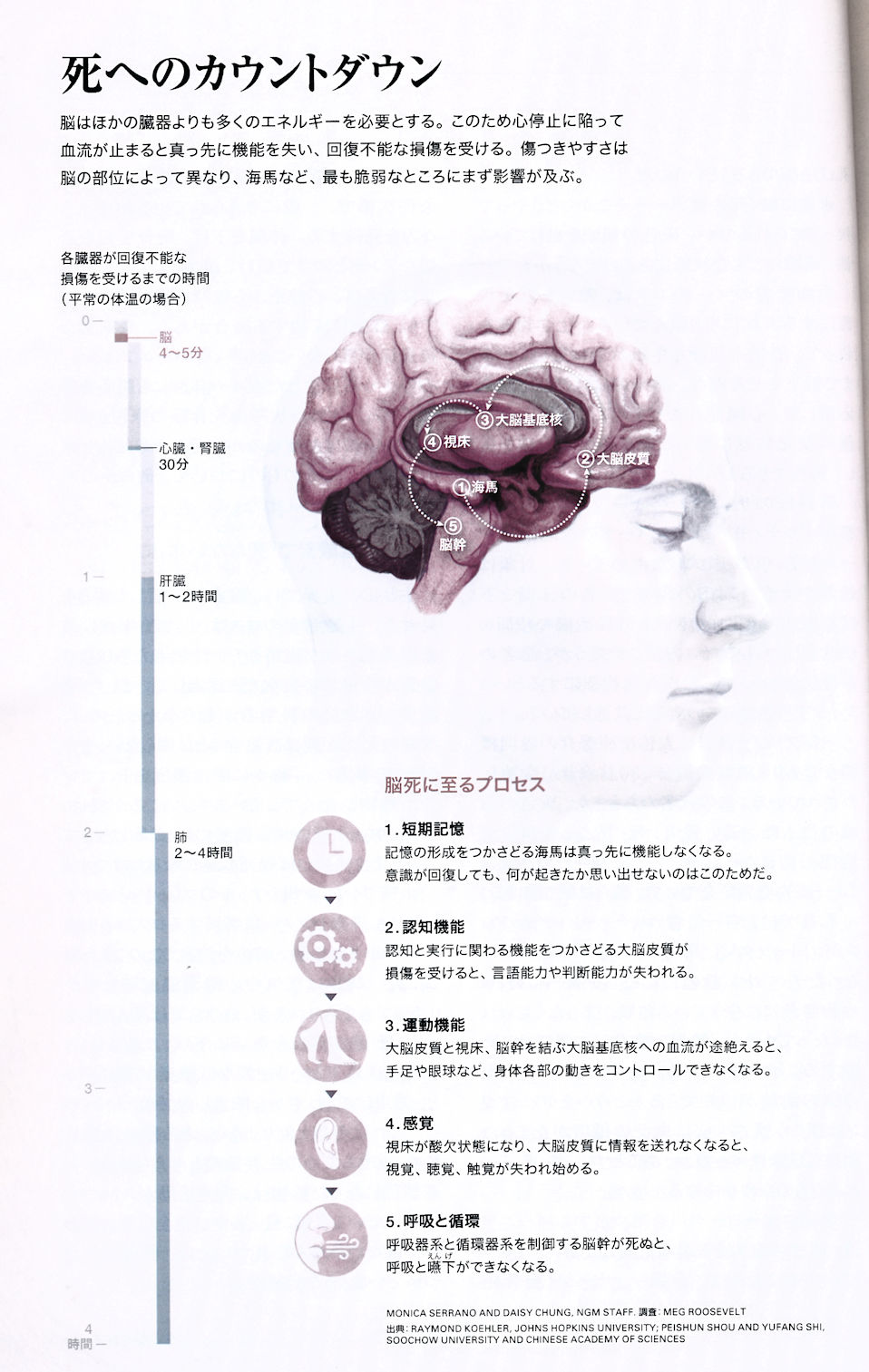
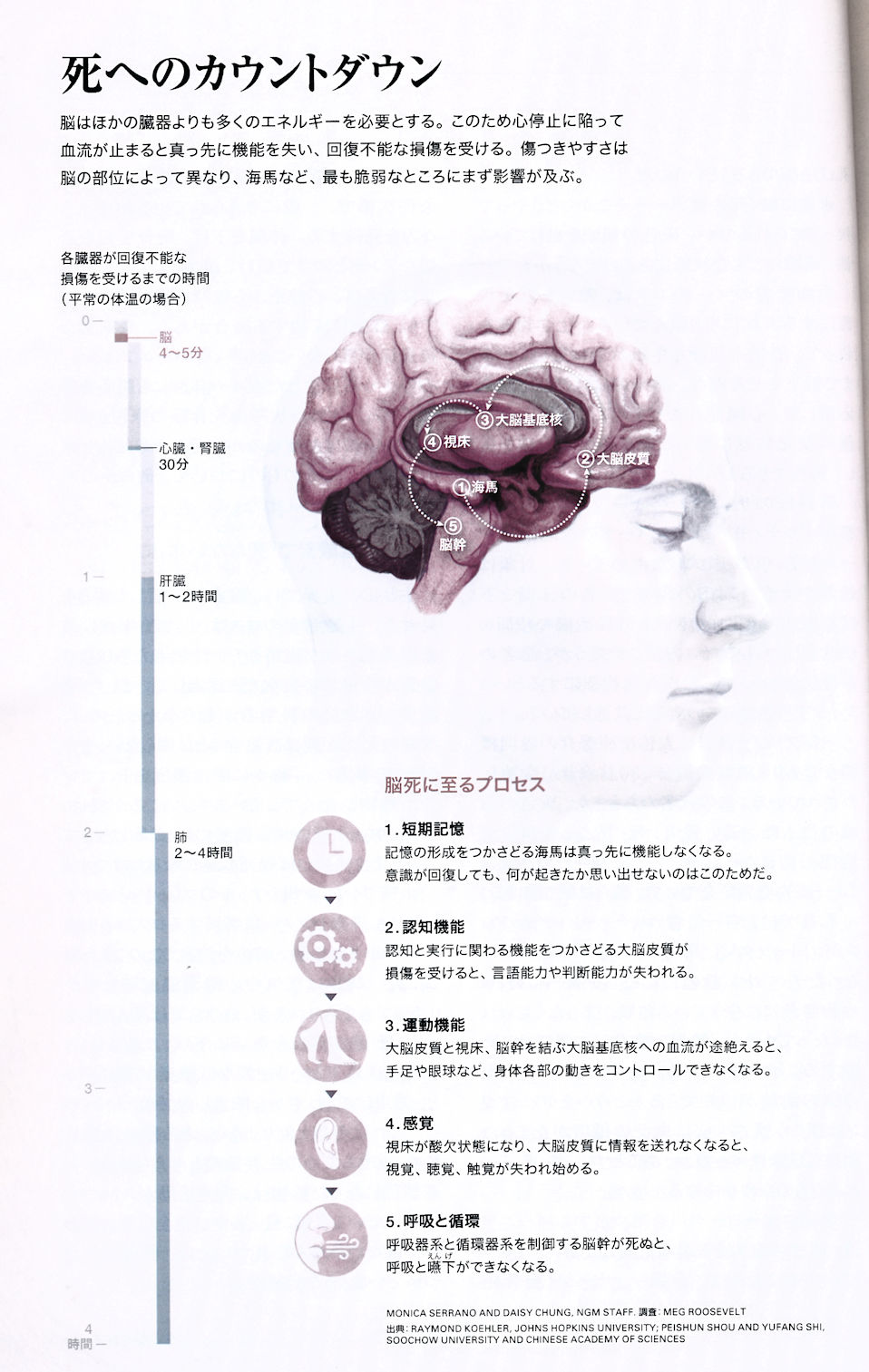
![]() 生と死 境界を科学する
生と死 境界を科学する
ナショナル ジオグラフィック 2016年4月号


本書 より抜粋引用 文=ロビン・マランツ・ヘニグ(サイエンスライター) 写真=リン・ジョンソン 認めつつも、その解釈を疑問視した。「これらを死の世界から帰還した人の体験談とみるのは誤りです」とネルソンは 述べた。「体験の間、脳は生きて活発に活動しています」。ニールの体験は「レム侵入」と呼ばれる現象かも知れない と、ネルソンは指摘する。急激な低酸素状態などが引き金となって、眠っていないときでも、レム睡眠中に夢を見る ときと同じような脳の活動が起きる現象だ。ネルソンによれば、臨死体験も体外離脱の感覚も低酸素状態になった ために生じるもので、命を失ったわけではなく、正常な意識を失ったために起きた幻覚として説明できるという。 臨死体験については、生理学的な研究も行われている。米ミシガン大学の神経科学者ジモ・ボージギン率いる研究 チームは、ラットを使って心停止後の脳波を計測する実験を9例行った。いずれも心停止後には、高周波のガンマ波 (瞑想に関連があるとされる脳波)が通常の覚醒時よりも強まり、秩序立った現れ方をした。 ボージギンらは、これが臨死体験の正体ではないかと推測している。死が完全に逆転不能となる前の移行期に、 「意識をつかさどる脳の活動が高まった状態」ではないかというのだ。 チベット仏教でトゥクタム(即身仏)と呼ばれる状態になった僧侶の肉体は、1週間余り腐敗しないように見える。この 希少な現象にも、生と死の境界を探る手がかりがありそうだ。神経科学の立場から瞑想を長年研究してきた米ウィス コンシン大学のリチャード・デビッドソンは、ある時、ウィスコンシン州のディア・パーク僧院でトゥクタムの状態になった 僧侶を目にした。 「何も知らずに部屋に入ったら、深い瞑想状態にあると思ったでしょう。肌にも生気が感じられ、腐敗の兆しはありま せんでした」。科学の力でこの謎に迫ろうと、デビットソンはインドの2ヵ所に研究拠点を設けて脳波計や聴診器などの 機材をそろえた。チベット人の医師12人を訓練し、僧侶の死後も脳の活動が続くかどうかを調べる体制が整った。 願わくば、生前から測定を始められれば申し分ない。 「こうした僧侶の多くは死ぬ前に瞑想状態に入り、その状態が何らかの形で維持されると考えられます。どうやって それが起きるか、その説明は、従来の科学の範疇を超えているかもしれません」。デビッドソンは現代科学の手法を 用いながらも、科学だけでは説明しきれない、もっと複雑な何かがそこにはありうると考えて研究を進め、トゥクタム の状態にある僧侶だけでなく、生と死の境界を旅するすべての人に何が起きるかを探ろうとしている。 |
|
「熱きアラスカ魂」最後のフロンティア・インディアンは語る シドニー・ハンチントン著
れていた。その彼が祖父から聞いたという次のような話を私に聞かせてくれた。彼はこの話を 事実にもとづいたものと信じていた。
1820−30年代は、コユコック川一帯にけものも魚もおらず、そこの住人にとってまことに過酷 な時期だった。ヘラ鹿(ムース)もいなかった。それまでにコユーコンの人たちは川や湖から魚を 獲りすぎてしまった。何年も続けて筌をしかけ、いくつかの川をふさぎ、川に産卵に戻ってくる鮭 を獲りつくしてしまった。ダルビ川とその傍流だけが、辛うじて鮭の遡上する川として残った。(ち なみにコユーコンの人たちが鮭の生活史を知るようになったのは近年のことである。川底の砂 礫の中に産みつけられた卵から孵った稚魚は、川を下って海に到り、そこでじゅぶん成長した のち、生まれた川へと戻ってくる)。インディアンの多くが、もっと獲物の豊かな土地を探してコユ コック川を去った。ユーコン川へと移動した者が多かった。そこでは夏の間、鮭がたくさん獲れ、 干し魚にすれば冬いっぱいそれで持ちこたえることができる。コユコック川流域にとどまった人 たちの中には、魚が戻ってくるのを待ち望みながら餓死していく者もあった。一縷(いちる)の 望みにすがって身を滅ぼしてしまったのである。四度の春が過ぎていった。移動していった人 たちは、故郷へ帰りたくてたまらない。カリブーも戻ってきているに違いない。とっくに姿を消し た兎も。いったんいなくなった魚やけものがそんなに早く戻るはずはないと長老たちは懸念し た。だが、一部の人たちは警告を振りきって、恵み豊かなユーコン川を去り、コユコック川の 支流ホグ川へと戻った。秋になった。ホグ川に注ぐいくつもの流れに筌がしかけられたが、ほ とんどは魚はかからない。冬を乗りきるにはとても足りない。飢餓の脅威にさらされた人々は、 生存ぎりぎり支えるわずかな食料をそりに乗せて、徒歩で狩りや漁に出た。与えるべき餌がな いので、そり犬を飼うことはできなかった。刻々と餓死の運命が迫っている。男たちは山へ狩 りに行ったきり、何週間も戻ってこない。日脚が延びはじめる一月になってようやく、何人かが 帰ってきた。帰らなかった者は飢えて野垂れ死んだに違いない。戻ってきた男たちは、はるか 東のメロジトナ川の源流あたりでカリブーの姿を発見したと伝えた。肉を持ち帰ってもきたが、 その量ではみなの飢えを満たすにはほど遠い。彼らは家族ごとメロジトナ源流へ移るつもりで いたので、そのときのために道中数カ所に隠してきた。源流域に戻りさえすれば、もっと多くの 肉が隠してある。前の年に女と暮らす資格を得た一人の若者も、長い狩りの旅から戻ってい た。彼が旅に出てすぐに、新妻は赤ん坊を生んでいた。若い父親は、家族の食べ物が底を 突いているのを目の当たりにした。病身の母親は、自分の食べ物を息子の嫁に与えつづけて いた。たった一人の孫を生き延びさせるためなら、彼女は自らの命の糧を差し出しても惜しく なかった。こうして、ゆっくりと着実に彼女は餓死へ向かっていた。野営地の人たちはみな、 メロジトナへの長い旅への準備を急いだが、赤ん坊の老いた祖母だけは別だった。「わたしは 行けないわ、息子よ」彼女は言った。「もうそんな力はないの」 「そりで引っぱっていくさ。母さ んのお陰でぼくは頑丈に育ったからね。置き去りにして死なせるわけにはいかないよ」息子は きっぱり言った。母親はしばらく黙りこんでいたが、やがて息子と嫁を呼び寄せた。話している 間、彼女は孫を腕の中でやさしく揺すった。「息子よ、わたしはもう年寄りだ。このところ何年も 何年も苦しい時が続いている。おまえの父さんが飢え死にしてからも、わたしはおまえをりっぱ に育てようと、ただただ頑張ってきた。もうそれもお終いだよ。でも、死ぬときだって、おまえを 助けるつもりさ。わたしがいなければ、おまえもお嫁さんも赤ん坊も生き延びられるに違いな い。行き先は遠すぎて、とても歩けやしない。わたしをそりに乗っけて引っぱりしたら、おまえ はへたばってしまうよ。よくお聞き、頭を使いなさい。目は泣くために使うんじゃないよ。勇気の ある男になるんだ。でっかいけものを殺す勇気とは違う勇気だよ。わたしを安心させ、女房と 子どもを生き延びさせるためには、もっと大きな勇気が必要なんだ。わたしの言うとおりにしな かったら、おまえは家族を失う。わたしはおまえの面倒をしっかり見てきた。今度はおまえの 番だ。どれほど勇気のある男か見せてほしい。わたしはいっしょに行かない。だが、どうかこ のままじわじわ飢えて凍え死んでいくままにはしないでおくれ」 母が言うことはよくわかった。 若者は打ちひしがれてイグルーから外に出た。自分たち小さな部族の祈祷師で指導者でも ある男のところへ行った。話を聞いた祈祷師は、こういうことは以前にも起こったと言い、若 者に説いて聞かせた。「おまえの母親は正しい。この世に送り出してくれた母親の命を奪うこ とに比べたら、でかい動物を殺すことなんか造作ないこった。強く、勇気のある息子になれ。 もし彼女の言うとおりにしなければ、おまえの若い奥さんとたった一人の赤ん坊を死なせる 羽目になる。おまえは強い男だ。こそこそ隠れたり、恥じたりしなきゃならんことをしでかす男 ではない。精いっぱいおまえを育て上げ、最後の最後まで守ってやろうと心をくだいている母 親を安心させてやりたいだろう? どうだ、勇気をもってそれができるか?」 若者と妻は眠れ ない一夜を過ごした。生き延びようと思うなら、明日みんなと肉を隠している場所へと出発する しかない。早朝、二人が荷をそりに積み終えると、母親が生皮の紐を輪にしたものを手にイグ ルーから出てきた。道の脇の樺の木に向かってしっかりした足取りで歩いた。紐の一方の端 を枝越しに投げて引っかけ、地面に腰を降ろすともう一方の輪を頭から通して首にかけた。 それから母親は道とは反対の方角に向きなおり、叫んだ。「いいよ、わが息子よ」 息子は生 皮の紐を引いた。
コユーコンの年寄りはみなこの話しを知っている。だが、ある老婆が私に言ったことがある。 「こんな話は他人に聞かせちゃいけないんだ。わしらの信条に反することだからね」。まさに その理由で人々は口をつぐみ、口承により伝えられてきた話のうち多くのものが失われつつ ある。幸いにも私はコユーコンの長老からいろいろな話を聞き出すことができたが、それら の話しは、人々のすべての思いとエネルギーは、「生き延びるべし」という一点に向けられて いたことを示している。
|
