

![]() 「今日は、死ぬにはいい日だ。」
「今日は、死ぬにはいい日だ。」
元気になれる、7つのメール。
作 木戸寛行 画 華丸 小学館
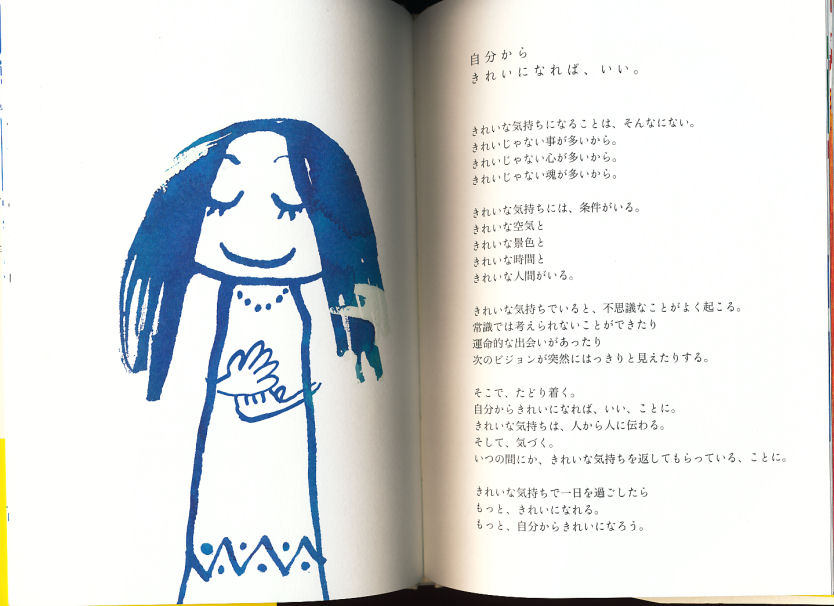


|
覚悟でアメリカに旅する。その目的は前代未聞のインディアンから名前をもらう ことだった。何の準備や用意もなくアメリカの立った著者は、200人の人たちの 縁を通してナバホの地に立つことになる。そして自分がここへきた意味を数時 間かけて政府重鎮の前で必死に訴え、日本人としては初めて彼らから「たくさん の言葉を操る少年」という意味のインディアン・ネームを与えられる。本書はその ような経緯を辿った著者が、疲れた現代人に送る優しい癒しのメッセージであり、 画はイラストレーターで有名な華丸氏が描いている。 (K.K)
|
![]()
|
1969年東京生まれ。外資系広告会社で活躍するコピーライター。TCC(東京コピーライター ズクラブ)新人賞、読売広告賞、クリオ賞、ロンドン国際広告賞、ニューヨーク・フェスティバル (金賞)など、国内外で数々の受賞歴を持つ。過労死寸前にネイティブ・アメリカンの言葉に 出会ったことをきっかけに、彼らの聖地へと旅に出て、ナバホ族から日本人としては初めて の公式なインディアン・ネームAshkii Bizaad tani(「たくさんの言葉を操る少年」の意)を与え られた。
1969年福岡生まれ。坂本龍一、ゴスペラーズなどミュージシャンのアルバムワークや雑誌、 書籍でイラストレーターとして活躍する一方、携帯電話のキャラクターデザイン、テレビの アニメーション製作、北欧のデザイン会社に参画するなど、幅広くアートとデザインの世界で 活躍している。自作キャラクターから生まれたアイテムは300点以上。モノマガジン別冊 「インディアンの声を聞け」では、自らの絵と文で巻頭を飾っている。
|
|
(本書 帯文より引用)
単純で、いい。 自分からきれいになれば、いい。 空を見上げれば、いい。 内なる声に耳を傾ければ、いい。 もっと遠くへ行けば、いい。 手をさしのべてもらえば、いい。 あなたの物語を編めば、いい。
インディアンになりたかった。 大空を飛ぶイーグルのように 人生を自由に生きていく。 自然と共に 自分の魂にただ忠実に あせらず 屈せず 裏切らず 希望を持って生きたかった。 そして僕は 旅に出た。 本当の自分を 見つけるために、インディアンに なるために。
2001年、僕はインディアンになった。 アリゾナのWindow Rockで、ナバホ族の政府に直接かけあってナバホ族として認められ、 インディアン・ネームをもらったのだ。思い立ったのは、インディアン・ジュエリーの仕事をし ている友人と再会した時だ。彼のアトリエで数冊の本をめくっていたら、ナンシー・ウッドと いう詩人が集めたインディアンの言葉である“Today is a good day to die”にめぐり会った。 東京で仕事をしていて、実際に、過労で死にかけた直後に目にしたこの言葉は、僕の運命 を大きく変えようとしていた。
「これからは、いつ死んでも後悔することのないように、一日一日を過ごそう」 その時に、感じた強い気持ちが、僕にネイティブ・アメリカンかr名前をもらうといった途方も ない馬鹿げたことをしでかす原動力になったのだ。 「いつ死んでもいいじゃないか。命を賭けて自分のやりたいことをやろう」 大袈裟なようだが、僕は、死ぬ覚悟を決めていた。
3日後に、成田空港を飛び立ちアメリカに向かっていた。何の計画も、準備も用意もなかっ た。まさに、無謀と形容される旅だ。すべては、到着してからはじめた。地図を購入し、どの ルートで行くかを、出会った人たちのアドバイスと自分の直感で決めていった。ダイナーで 話かけた助教授風の2人組の白人たちから、ナバホ族の名前を僕にくれるように手紙を書 いてくれたTerryまで、約200人の人たちと僕は話をした。あの日、あの時に出会った人の 一人でも欠けていたら、夢を実現することはできなかっただろう。
数週間後、僕は、ネイティブ・アメリカンのナバホ族の聖地に立っていた。そして、彼らの前で 想いのすべてを言葉にしていた。歓迎してくれる雰囲気など微塵もなかった。 「お前は日本人だから、絶対にダメだ」 「今まで、そんな前例はない」 「不可能だ。帰れ」 一様に、そんな拒否を示す態度であった。何の不思議もない。海の向こうの日本から、ヘンな 奴がやってきて、名前をくれと勝手なこと言ってやがる。向こうの立場から言えば、一体ナンノ コッチャだったはずだ。しかし、僕だって必死だったのだ。それが、旅の目的だったのだから。 そして、命を賭けてやろうとしたことであったのだから。だから、無下に却下されても「はい、す いませんでした」と帰ることなどできなかった。
いつの間にか、数時間が経過していた。最後の切り札は、アメリカ到着から交換してきていた 200人のアドレスとTerryの手紙だった。僕は、目の前でアドレスを広げはじめた。それから、 ナバホ族の重鎮の一人に宛てられた手紙を、静かに差しだした。そして言葉を放った。「200人 の人間が僕をここに導いた。それは、神が僕をここに導いたのと同じことだ」 僕はどうしても インディアンになりたかった。新しい名前をもらうことで僕は自分が新しく生まれ変われると感じ たし、その行為は自分の人生においてとても大切な気がしたのだ。たくさんのフレーズが、僕 の口からまるで生きているように次々とあふれてきた。すると、半ばあきれかえられた空気の 中で、一人が重い口を開いたのだ。「我々の歴史の中で、こんなヘンな奴が、訪ねてきたこと はなかった。おそらく、こんな奴は、これからも現れないだろう。いや、二度と、現れないことを 祈る」
その場にいた、みんなが、笑いだした。そして、僕を見る表情がとてもやさしいものに変わっ ていくのを感じた。ナバホ政府の建物から出た時、僕の手にはナバホ政府が正式に発行し たクオリフィケーションが握られていた。まるで、夢の中にでもいるようだった。最高の奇跡 が起こったのだ。
“Today is a good day to die” 日本人である僕が、ネイティブ・アメリカンとして名前を手に入れることができたのは、この 言葉に出会えたからだと思う。出会う人たちとの強い運命を感じた旅だった。何かをやり 遂げることの意味を感じた旅だった。あれは、僕の心が必要としていた旅だった。日本で の忙殺された生活の中で、何か大切なモノを失っていた僕は、それをとり戻しに行ったの かもしれない。そして、自分自身が何者かを、再認識しに行ったのかもしれない。死ぬ覚 悟で行ったのに、僕は、生きる歓びを再び手に入れて帰ってきた。Ashkii Bizaad taniという インディアン・ネームとともに。
あの旅の途中で出会ったすべての人に感謝をこめて。 2005年初夏 木戸寛行
|
