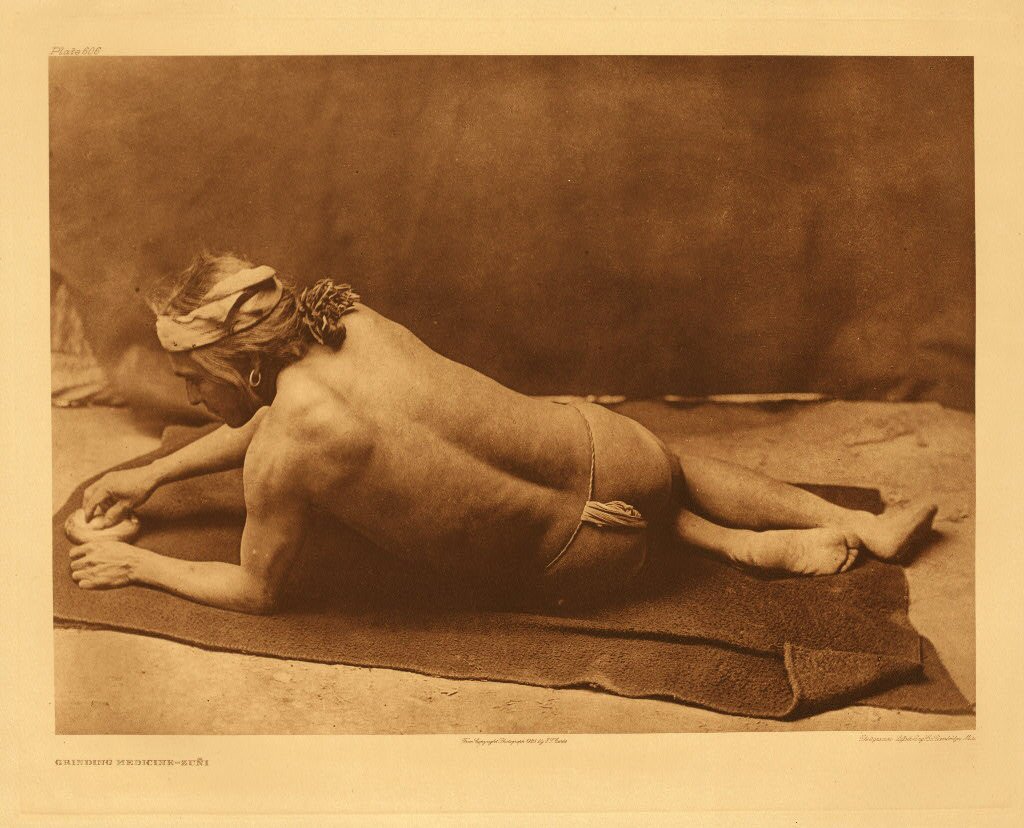
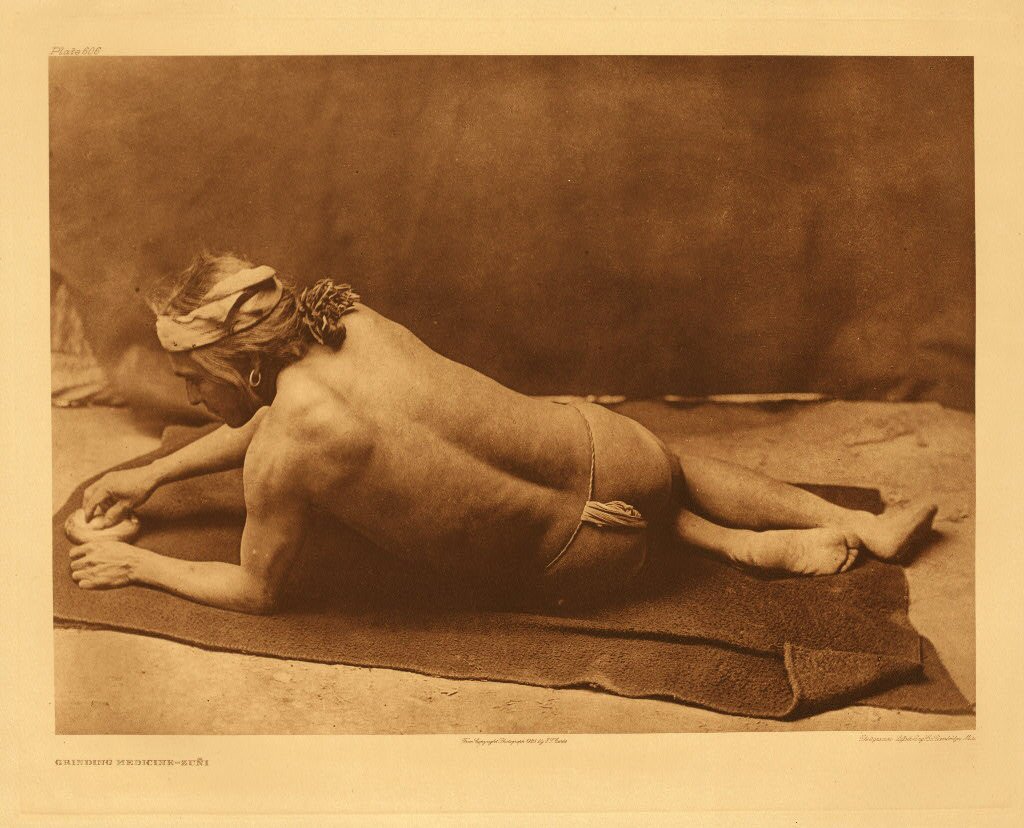
Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)
![]()

|
(ホピ族の著名な画家)
ついては語ることはできるんです。じっさい、それを僕は絵の中で表現する。たとえばギャラ リーにあったカチーナの絵。窓は、“通路”を象徴しています。肉体の世界と霊の世界を結ぶ 通路。それは、現在と過去、ひいては未来を結ぶ通路でもあります。ホピという土地は、儀式 に参加しなくても、僕を過去に連れ戻してくれる。そして儀式は、それよりずっとはるかな過去 にまで連れていってくれる。ある意味で、儀式は、遠くからの眺めを与えてくれる、と言うことが できる。自分が今日いったい何をしているのか、この生において何が最も大事なのか、人間 と自然がどんなふうに織り合わされているのかがはっきり見えるんですよ。
どこへ行っても人々は無益なことばかり喋り続けている。お金、評判・・・実在しないものの話 です。サンタフェでも同じ。モノがひしめいている世界。携帯電話、コンピュータ、飛行機、そし て人を殺すためのガンもある。産業廃棄物といった汚染。人間がつくり、地球という惑星に災 厄をもたらすたくさんのモノ。しかし、儀式においては、自分と自然、二つのものしか存在しな い。自然に対して全霊をかけてたのむと、自然が霊感を与えてくれるんですよ。最後には、 人間と自然のあいだに共感が生まれるんです。それは自分の生をまるで違ったやり方で見 る手助けをしてくれる。精神、思考、ビジョンの清掃をしてくれる。
歌を通じて過去を旅するだけでなく、自分を導くことができる。現代に、都市に暮らすというこ と、生きていくことはラクじゃない。こうした歌を聴いているとき、人はある意味で自分を見つ め直している。立ち止まる。歩く速度をゆるめて、自分のなかを覗きこんでいる。それは儀式 と同じく、過去の話でありながら、現在につながり、未来に問いを投げかけてくる。過去は未来 であり、未来は過去だ、と僕が感じる所以です
描き続けて、いわば自分を生贄に捧げることを要求される。終わったとき、もう何もできないという くらい精力を使い果たしている。その意味で、創作は儀式と同じです。儀式では、準備に長大な時 間を費やすだけでなく、最後の段階では、食べることも眠ることもやめて歌い、踊り続けるわけで す。もう疲れ果てて、どんな感覚も失われている。僕がまだ若かったころ、あれは儀式の二日目 だった。もう立つこともできなくて、キバの床に横たえていた。もううっすらとしか目を開けることが できなかった。ひとりの長老が来て、<ダン、疲れたのか?>と尋ねる。<・・・・ええ、疲れました> とやっとのことで答えた。長老は言いました。<よし、そうでなくちゃいかん。もし疲れていなければ、 何にも与えられんぞ>(笑い)」 創作に行き詰まったとき、疲れきってもう描けないと思うとき、ダン はこのときの長老の言葉を自分に向かって言う。「疲れているのか? よし、そうでなくっちゃいかん」 「何であれ、自分にとって非常に大切なものとつながるためには、自分を犠牲にしなければならない のだと思います。何かに自分を投入していって精魂尽き果てたとき、ある種の心の状態ができあ がっている。もうほとんど夢を見ているような、からっぽの・・・・・・・・。そのとき、到達している。つな がっている。言い換えれば、与えられているんです」
|

