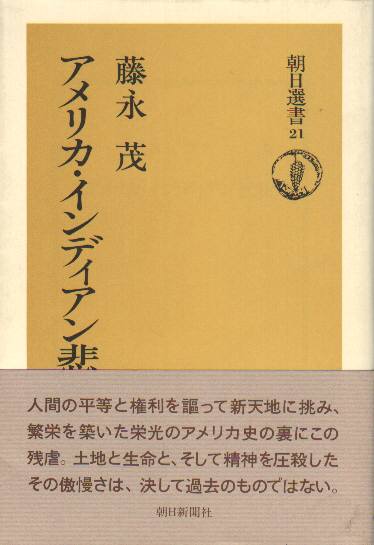
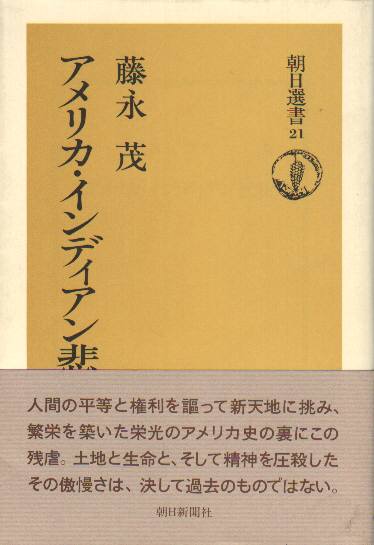
![]() 「アメリカ・インディアン悲史」
「アメリカ・インディアン悲史」
藤永茂著 朝日新聞社より
藤永茂氏のブログ「私の闇の奥」
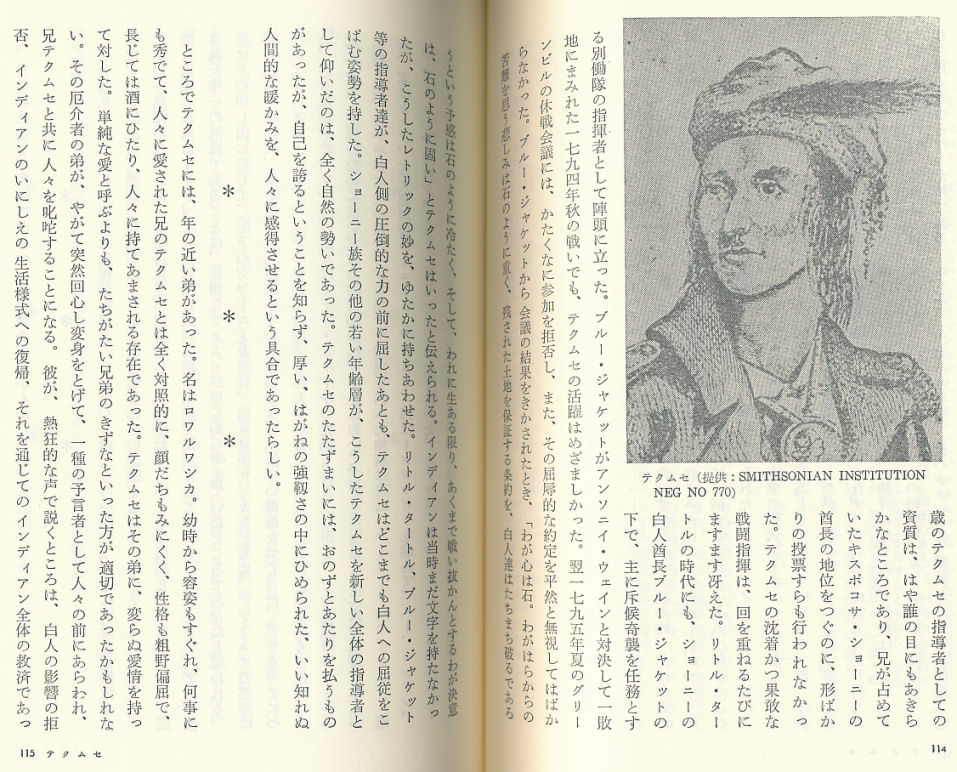
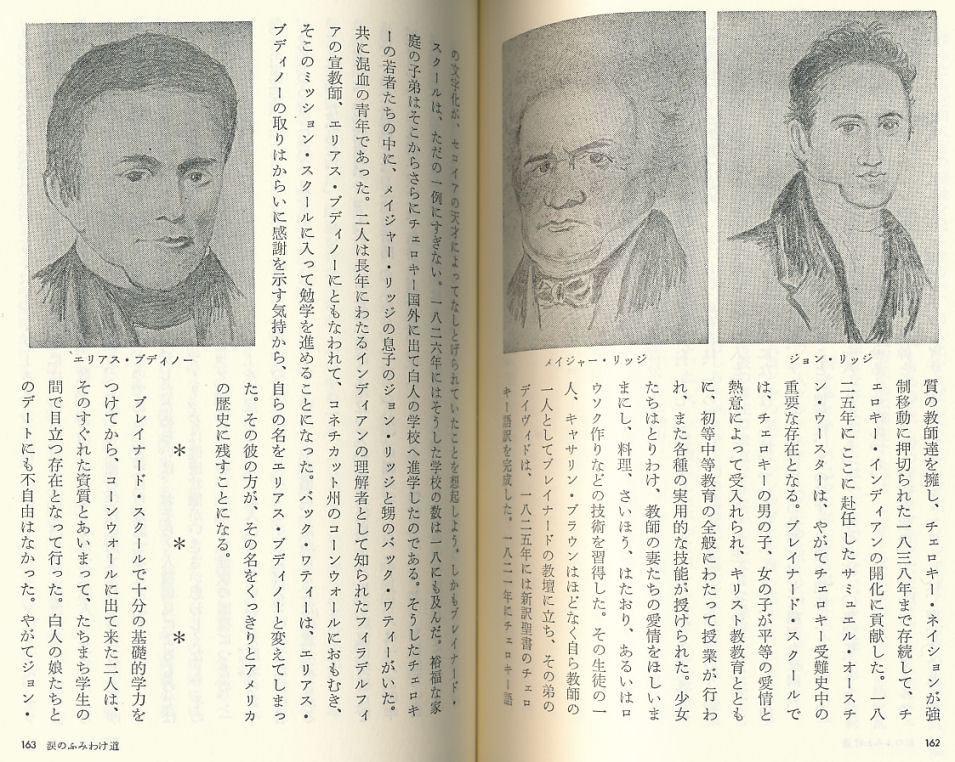

|
この残虐。土地と生命と、そして精神を圧殺したその傲慢さは、決して過去のもの ではない。」と著者は断罪しているが、このインディアンに加えられた残虐さと、 それを基盤にして発展してきたアメリカという国に対して言い知れぬ憤りを覚えて ならなかった。白人だけでなく、我々文明人と言われる人々が世界中の多くの高貴 な精神文化を踏みにじり、それによって豊かな、そして快適な生活を獲得してきた ことへの反省は現在においても殆ど見られていない。文明人という輝かしい表の顔 の下に潜む残虐・傲慢さの正体が、この書を通して明らかにされ、今後のあるべき 社会とはどのようなものかを痛烈な自己批判の中に自らを置いて、考えなければな らないし、決して彼ら先住民族の払った大きな犠牲を葬り去ることは許されない。 (K.K)
|
|
2012年1月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。
|
![]()
|
「インディアン」はいたる所にいる。素朴な親愛と畏敬をこめてクマを殺すことを 知っていたアイヌたちだけが我々にとってのインディアンではない。「かかよい、 飯炊け、おるが刺身とる。ちゅうなわけで、かかは米とぐ海の水で。沖のうつくし い潮で炊いた米の飯の、どげんうまかもんか、あねさんあんた食うたことのある かな。そりゃ、うもうござすばい。ほんのり色のついて、かすかな潮の風味のし て。かかは飯たく、わしゃ魚ばこしらえる。わが釣った魚のうちからいちばん気に 入ったやつの鱗ばはいで舷の潮でちゃぷちゃぷ洗うて。鯛じゃろとおこぜじゃろ と、肥えとるかやせとるか姿のよしあしのあっとでござす。あぶらののっとるか やせとるかそんときの食いごおのある。鯛もあんまり太かとよりゃ目の下七、八 寸しとるのがわしどんが口にゃある。鱗はいで腹とってまな板も包丁もふなばた の水で洗えばそれから先は洗うちゃならん。骨から離して三枚にした先は沖の 潮ででも、洗えば味は無かごとなってしまうとでござす。そこで鯛の刺身を山盛り に盛り上げて、飯の蒸るるあいだに、かかさま、いっちょ、やろうかいちゅうて、 まずかかにさす。あねさん、魚は天のくれらすものでござす。天のくれらすものを ただで、わが要ると思うしことってその日を暮す。これより上の栄華のどこにゆ けばあろうかい。」(苦界浄土) こう、石牟礼道子さんに語った水俣の漁師の爺 さまを、我々が殺したとき、我々はまぎれもなく「インディアン」を殺したのである。 インディアン問題はインディアンをどう救うかという問題ではない。インディアン問題 はわれわれの問題である。われわれをどう救うかという問題である。
|
|
を持ち続けて今日に至っている。それは、自分達の幸福論と本質的に対峙する幸 福論によって生き、しかも自分達よりもあるいは幸せであったかもしれない人達を、 まず力によってみじめな状態に追込み、そして殺してしまったらしいという不安で あった。ここで幸福論を神といいかえてもよいかもしれぬ。白人たちが物の所有に よって幸福を求めるとき、彼等はわかち合うことをよろこびとし、白人たちが隣人と 競い、それに優越することによって幸福を求めるとき、彼等は自己にうちかつこと によって自らと他の自由を確保し、白人たちが大地を凌辱してその富を強奪すると き、彼等はそれを大いなる母と慕った。インディアン達のあらゆる愚昧さは、白人た ちの競って利用するところであった。その愚昧さによって白人たちは莫大な利益を 手に入れた。しかし、同時に、そのインディアンの愚昧さのかげに、初々しい精神 の高貴としかいいようのないものを、白人たちはたしかに垣間見たのである。
|
|
ついては、それなりの理由がある。1968年3月、私が九州大学教養部を去ってカナダ に渡ったのは「エンプラ事件」の直後であった。私の心に容赦のない荒々しさで突き つけられた「大学問題」は北米大陸の北辺の孤独な時間のなかで消えさるどころか、 ますます私の心の中へ中へとのめり込んで来る感じであった。そのかなり内側のとこ ろで、私は突然インディアンと出くわしたのであった。この書物を読んで下さった方々 は、大学問題とインディアンの組合せが奇妙でもこっけいでもないことを認めて下さる であろう。私にしてみれば、これは「大学問題」に対する、私なりの「答案」として書いた つもりである。感傷は精神のポルノグラフィであるとはポール・ヴァレリーの言葉であっ たろうか。アジ・ビラを書いたつもりはないが、私は生硬な文章でポルノグラフィを書い てしまったかもしれない。いま読みかえしてやや自嘲に傾かないわけではない。しかし、 「インディアン」は私にはあまりにも私事でありすぎた。客観的な北米インディアン史を、 日本語で書く仕事は、アメリカ史の専門家におまかせしたい。
|
|
1 ソンミ 2 人喰人(カンニバル)について 3 感謝祭 4 オペチャンカヌウ 5 キング・フィリップ 6 イロコワ 7 ワシントンと「小さな亀」 8 テクムセ 9 セコイア 10 涙のふみわけ道 11 セミノール戦争 12 我々にとってインディアンとは何か あとがき 文献解題 参考文献
|
![]()
|
ジェイムス・タウンにあっても、プリマスと同じく、発足当初の食糧欠乏をはじめとする 苦難は筆舌につくし難いものがあった。1607年から三年間に、ここに上陸した入植者 の数は900人に上ったが、1610年の生存者はわずか150人、と記録されている。強 奪、窃盗、脅迫などの強引な手段にうったえて、インディアンから食糧を得ようとした ジョン・スミスに、ポワターンは「あなた方は、愛によって我々から得られるものを、どう して力ずくで取ろうとするのか」といったと伝えられる。
実際、少なくとも最初の10年の間は、老ポワターンにとって、ジェイムス・タウンを地上 から一気に抹殺することも、あるいは飢えるがままに放置することも、意のままであっ たはずである。しかし、彼はそれをしなかった。「・・・・我々が、むしろインディアンの襲 撃を予期した時に、彼等が、とうもろこしを我々に運んで来てくれたのは、全く神の恩寵 という外はない・・・・」とジョン・スミスは記している。ジョン・スミスが、その不逞行為の ゆえにインディアンに捕らえられ、ポワターンの面前で、あわや処刑されようとした時、 突然、娘のポカホンタスは、父にその助命を乞うた。ポワターンは、愛する娘の願いを 容れて、ジョン・スミスを釈放し、これを契機に、町の白人達との交遊がすすみ、ポカホ ンタスはやがて、ジョン・ロルフなる白人の妻となる。1613年ポワターンは白人達と和平 の協約を結び、1618年の彼の死まで、その約束に忠実であった。
ロマンテックな伝説が示すように、インディアン側には、素朴な情緒的要素があったか もしれぬ。しかし、白人の側には一片の感傷もなく、ただそこには、バージニア植民地 経営の冷たい計算があった。彼等は、ロンドンから銅製の王冠をとり寄せ、“キング” ポワターンの戴冠式を行うという茶番劇まで用意した。その空々しい滑稽さは、あくまで も誇り高い老ポワターンが海賊まがいのジョン・スミスの前にひざまずき、頭を下げて 冠をいただくことをためらったとき、極まった。
ポカホンタスを妻とした・ジョン・ロルフは、インディアンからタバコの栽培を学び、ここに 最初のバージニア・タバコ園の経営者が誕生する。インディアン達は「自分で喫む分だ け作ればよいのに・・・・」とロルフを笑ったという。しかし、最後に笑ったのは、もちろん 白人達であった。ここにバージニアは、決定的なドル箱を得た。タバコは連作を拒む。 二年あるいは三年ごとに作地をかえなければならぬ。栽培の規模が拡大するにつれ て、それは数千エーカー(1エーカーは、訳4000平方メートル)の作地変更を要求した。 新しく森林、沼沢を拓くより、インディアンの畑を奪う方がはるかに経済的なことは明白 であった。インディアン達は、泣きながら、自分の土地を追われて去った。
もともと、新大陸の広大な土地は、最初から、不動産投資あるいは投機の対象として、 明確に意識されたのである。しかし、インディアン側には、土地の個人所有、永続的な タイトルという概念が、全く欠けていた。一般的にいって、すべての土地は、部族全体の 共有であり、農耕も、共同作業ふう(コミュナル)に行われた。母なる大地を人工的に分 割所有し、使用の有無にかかわらず、他人に狩猟も一時的農耕も許さないという、白人 達の土地所有の概念は、インディアン達の理解の外にあった。「土地は、水や空(空気) と同じことだ」と彼等はしばしばいったという。土地は、それを必要とするものが、適当に 使用すればよいという素朴な立場に立って、インディアン達は、はじめ、白人達の要求 を快く受けいれた。しかし、やがて植民地の人口が急増し、また新大陸の土地に対す る貪欲さが、限りを知らずふくれ上がっていったとき、インディアン達が不安と危惧にお そわれたのは当然であった。他方、食糧その他についてインディアンへの依存が減少す るにつれて、白人達は、次第に彼等を、植民地の発展をさまたげる野蛮人としてとらえる 見方を強めていった。ポワターン自身の存命中にも、すでに事態の本質の露呈はおおう べくもなかった。しかし、彼の死までは平和はまがりなりにも保たれたのであった。
インディアンが、とうもろこしや、七面鳥をたずさえて来て白人達の空腹をいやした時、白人 達はそこに神の恩寵のみを見た。やがて、邪魔者と化したインディアンの、効率よい虐殺に 成功するたびに、彼等はそこに再び神の加護を見出し、あるいは、頑迷な異教徒を多数殺 戮することによって、彼等の神への奉仕をなし得たとすら考えた。彼等の感謝祭には、はじ めから、インディアンは「不在」であった。カリフォルニアの一キリスト教系大学の雑誌(1969 年11月号には、サンクス・ギビングの、明快な解説がある。「このお祭りは、ニュー・イングラ ンドでは、ひろく行われるようになった。人々は、作物の豊かなみのり、インディアンに対する 勝利といった、よろこばしい事件を、神に感謝して、この日を祝ったのである。・・・・」
|
