

Two Bear Woman - Piegan
Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)
![]()

Red Cloud - Ogalala
Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)
失意の底にあったRed Cloud(レッド・クラウド) 「ともいきの思想」阿部珠理著を参照されたし
![]()
 AllPosters |
古本においては、Amazonが一番充実しているかも知れません。 またブラウザ「Firefox」ではリンク先が正常に表示されない場合があります。 |
![]() 既読の文献
既読の文献
![]() 各文献の前の
各文献の前の![]() をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
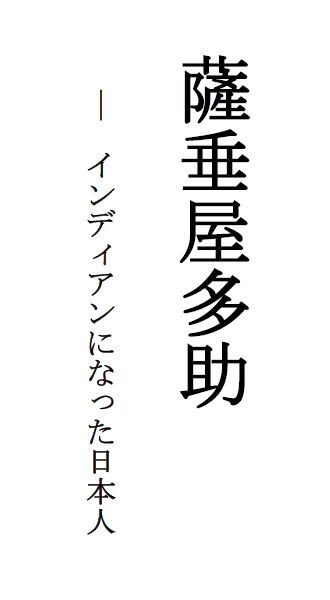 |
スーザン小山・著 かつ400年前に生きた彼らが未来に残した想いを掬い取るものだけに許された 物語。それがスーザン小山さんが書かれた小説「薩垂屋多助 インディアンに なった日本人」である。実際に江戸時代初期に徳川家康に外交顧問として仕え たイングランド人航海士・三浦 按針(ウィリアム・アダムス)と多助との出会い。 才覚を認められ通訳として彼・三浦 按針の元で様々な経験を積み、インド生ま れの娼婦との恋を経ながら、イギリスに旅たつ多助。そこで彼の一生を決めた のはディズニー映画でも有名なアニメ「ポカホンタス」、その彼女を育んだラナペ 族(ポウハタン族)との出会いだった。この小説には過去の歴史的事実に、 「多助」という架空の日本人を織り込むことによって、現代に新たな命を吹き込ん でいる。 スーザン小山さんが書かれたインディアン関連の5冊の文献(2冊は全国学校 図書館選定図書)は素晴らしいが、この「薩垂屋多助 インディアンになった 日本人」は彼女の集大成とも言える感動の小説である。ラナペ族(ポウハタン 族)の未来への想い、多助の未来への想い、それはスーザン小山さん自身が 「多助」そのものであることに気づかされる。歴史的事実や背景を基に、400年 前のインディアンの魂の叫びを聴き取った第一級の作品である。 「私がこれから言うことを心して聞け。私は今夜この世を去る。だが私はひとり で逝くのではない。戦士や族母たち、そして多くの老若男女もまた死ぬであろう。 ラナペ族は今夜、民族として絶えるのだ。だがわれらの誰かがラナペの血を 後世に伝えなければならない。我らがこの地に生きたあかしを、この大地は 我らのものであることを、我らの赤い道と天地の真実を七代の子孫に伝える ために、そして七代の子孫がさらにその七代の子孫に伝えるために、誰かが 生き続けねばならぬ」 多助は部族最高の精神指導者の言葉を聞きながら、それが自分の心に、まるで 以前から聞いていたことがらのように自然に響くことに奇異の念と感動を覚えた。 かたわらの三人は頭を垂れ、その言葉にじっと聞き入っている。同じ思いでいる のであろうか。だがトモコモの深い目の色は、多助には見えない中空の何かを 見据えていた。その言葉が再び静かに響く。 |
アメリカ先住民から学ぶ―その歴史と思想」 阿部珠理 著 NHK出版 する上で最も優れた文献の一つになるだろう。著者の先住民に対する造詣の深さ と長年のフィールドワークを通して、インディアンの歴史と思想の核心に迫っていく 本書はアメリカ先住民とは、アメリカ・インディアンとは何かと知りたい人にとって先 ず読んでほしい文献であり、多くの発見をもたらしてくれる。私自身、阿部珠理さん が今までに出版した文献から多くのものを発見し学んできたが、それは本書におい ても平衡感覚に優れた著者ならではの輝きが宿っている。尚、本書はNHKラジオ 第2放送で2011年10月から12月の毎週12回にわたって放送される。 最貧部族であるが、調査を初めて以来約二〇年、冬は零下二〇度に達する保留地 で、凍死者や餓死者の報告に接したことがない。翻って、先進国の一員として物質 的繁栄を謳歌してきた日本では、孤独死や餓死のニュースは、今や珍しくはない。 ここから私たちは、先住民社会の「貧しさの中の豊かさ」と日本社会の「豊かさの中 の貧しさ」を読み取ることができるかもしれない。 この講座では、アメリカ先住民の過去から現在までの歴史を繙き、その社会と文化 の劇的な変容をさまざまな事例から学ぶとともに、その変容の引き金になった外的 要因と内的要因を考える。そこからは、近代西欧の植民地主義と先住民社会の相剋 における歴史の普遍が垣間見えるだろう。さらに先住民社会の「貧しさの中の豊かさ」 に着目して、その豊かさの内実を明らかにしてゆく。それこそが、彼ら民族を再生に 導く源泉だと考えるからだ。先住民社会を私たちの社会に照射して、今後の私たちの 生活と社会を展望することが、アメリカ先住民を学ぶことのもっとも重要な意味だ ろう。 (本書 はじめに より抜粋引用) |
|
アメリカ・インディアン闘争史 ディー・ブラウン 著 鈴木主税 訳 草思社 この本は暴露している。そこには人間とも思われない白人によって繰り返される インディアンへの虐殺の歴史が緻密な記録をもとに描かれ、またどのような迫害に あっても白人との共存を模索していた崇高なインディアン首長の姿を見ることが出来 るであろう。 半世紀の間に西部の開拓は完了したがそれは同時にインディアン征服の完了 とも重なっている。すなわち1890年のウーンデッド・ニーの虐殺をもってインディ アンの組織的抵抗は終わりをとげ、同時にフロンティアも消滅した。1860年から わずか30年間にシャイアン、ユート、アパッチ、スー、コマンチ、ナヴァホ、カイオワ、 アラパホの各部族は次々と滅ぼされた。白人にとって土着アメリカ人であるイン ディアンとは、開拓されるべき自然の一部であり、物理的に排除されるべきもので しかなかった。フロンティア開拓にまつわる神話をアメリカ史はほこりとしている。 だがそこに犠牲となったインディアンの声がきかれることはまれである。著者は 条約会議でのインディアンの発言の速記録などをもとに本書をかきあげた。彼ら の言葉は雄弁であり、詩的でさえあり、そのいたましい歴史とともにわたしたちの 心を打たずにはおかない。・・・・・・・・・・・・・・・・本書より引用 |
|
アート・デイヴィッドソン著 鈴木清史+中坪央暁訳 明石書店 世界中の子どもたちに。世界の人びとが自分たちの生活様式で生きていくことが できることを知ってもらうために。 (本書より・アート・デイヴィッドソン)
|
|
|
|
|
写真で綴る北アメリカ先住民史 アーリーン・ハーシュフェルダー著 日本語監修 猿谷要 赤尾秀子・小野田和子訳 BL出版 日本で発行されたことはなかったかも知れない。視覚的にもとても見やすく、イン ディアンが辿ってきた苦難の道を振り返ることが出来るこの文献は、初めてイン ディアンに関心を持つ人々にとって最良の文献の一つに数えられるのではと思う。 私自身にとっても、今まで見たことがない写真が数多く掲載されており、心を打た れてしまいました。4300円もする高価な文献ですが、それだけの価値はある 文献ではないかと感じています。ただこの本の編集をした方が書いたものかどうか はわかりませんが、「世界史のなかでもひときわ知的興味をそそる悲しみに満ちた 彼らの歴史」という紹介文の言葉に何か抵抗を感じずにはいられませんでした。 ヨーロッパ人探検家と接触して以来、何百年にもわたり故郷を守る戦いをつづけ てきました。本書は世界史のなかでもひときわ知的興味をそそる悲しみに満ちた 彼らの歴史を、16世紀から20世紀にいたるまで、時を追って詳細に綴ります。 ヨーロッパからの移民がおしよせるなか、先住アメリカ人たちは白人文化への 同化を強制され、父祖伝来の土地を守るために戦い、現代でもなお、アメリカ社会 の一員として、先祖から受け継いだ信念や風習を守りぬこうとしています。本書は 豊富な写真とわかりやすい解説に加え、ネイティヴ・アメリカンの居住地域や戦場 を地図で示し、胸をうつ先住民のことばを引用して、過去の事実をいきいきといま によみがえらせています。 (本書より引用) |
|
ヨラン・ブレンフルト 編集代表 大貫良夫 監訳・編訳 朝倉書店
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正義と賭博と部族国家 スーザン・小山 著 三一書房 きたインディアンとアメリカ司法制度の問題点を明らかにしていく(同著・帯文より)」こ の書は、現代においてもインディアンが絶えず社会的にも文化的にも白人からの迫害 にさらされている現実を問い掛け、アメリカ社会に潜む暗部を明らかにしていくもので ある。またこの書はインディアンに関心のある方たちだけでなく、アメリカという国、 白人とは何者かを真に知りたい人にも読んでいただきたい本である。明治より「西洋 に習え」を合い言葉に近代化を進めてきた日本が陥っている「アメリカ・白人」という憧 れの対象の真の姿をこの本は良心を持って描き出しており、また移民として著者を受 け入れてくれた国の将来への期待とが交差しているからである。この書は現在のイン ディアンが置かれている政治・司法・社会的側面を考察している数少ない本の一つに 数えられる。 民主主義の実践者たる市民が、どれだけその原則に忠実であろうとしているかで ある。以上述べたさまざまなことがら、そして本書で検討している「シンプソン裁判」 や「ハウス裁判」の相互関係は、一見脈絡のないジグソウ・パズルのように見えよ うが、これらはすべて、司法の公正とその矛盾を指摘する題材としてあげたもので ある。私個人としては部族政府の権限を合衆国の人々がもっと正確に把握し理解 すれば、この国は単に物質力の豊かさだけでなく、内奥の美しい原理原則の国と して真実偉大な国となるに違いないということを、自分を移民として受け入れてくれ た国に住む毎日のなかで、ことあるごとに考えながら暮らしている。国民とそれを 代表する政治家も、この白人の国はインディアンから与えられたものであること、 永遠にインディアンの国土であることを深く肝に銘じ、最高裁判事ヒューゴー・ブラッ クのいったように、偉大な国家として偉大な人物のようにきちんと約束を守れば、 世界の誰からも尊敬される真の指導者になることは間違いない。その感慨を日本 の人々と共有したいと思ってこの本を書いた。部族の立場を真に理解することが、 合衆国という、日本ともっとも密接な関係にある国家をもっと良く理解する一助に なると深く信じている次第である。 (本書より抜粋引用) |
|
富田虎男著 雄山閣出版 野蛮なゆえに滅ぼされた過去の人なのであろうか?本書は彼らの正当な歴史的 役割を評価し、勝者のつくりあげた歴史像の虚偽を追求する」と本書・帯文に書か れているように、多くの文献を土台にして書かれた力作である。本書は「歴史公論」 に連載されたもので、植民地時代から19世紀後半のドーズ法やインディアン再組 織法などの矛盾を深く考察している。 ようやくその緒についたところである。研究成果の蓄積も一、二を除いて無いに等 しい。このような状況のなかでインディアン史を通して書くことは、無謀のそしりを免 れないかもしれない。ましてインディアン史への関心はすでに20年も前から抱きな がらも、研究そのものは遅々として牛歩の如くであった筆者がそれを試みるのは、 蟷螂の斧に等しいかもしれない。しかし、ここ10年、アメリカ合衆国ではインディアン 史に関する研究がめざましく進展した。また筆者の周辺でも、インディアン史に関心 を抱く学生や市民の方々がとみにふえてきた。このように客観的条件が整ってき たにもかかわらず、筆者の主体的条件は必ずしも十分に整ったとはいえないが、 与えられたこの機会に、あえてインディアンの歴史を書くことを決心した。もちろん、 本書は均衡のとれた網羅的なインディアン通史ではない。それを書くことは、筆者 の能力をはるかに超えることである。通史ではなく、これはあくまで筆者が重要だ と感じたインディアン史上の諸問題にについて、史料と研究成果によりつつ筆者な りにまとめた、ひとつの歴史叙述の試みにすぎない。しかし、筆者はここで、従来 の白人社会中心の視点からつくられた合衆国史上のインディアンにまつわるさま ざまな「神話」や通俗的理解に対して、ひとつの挑戦を試みている。筆者の意図は、 従来の合衆国史から無視あるいは抹殺されてきたインディアン側の部分を、たん に付加したり補填することにあるのではなく、むしろインディアンや黒人やその他 のこれまでその主体的な役割を無視されてきた人びとの歴史的役割を正当に 評価することによって、全体としてのアメリカ合衆国史像を再構築することにある。 これはそのための作業の一過程である。1982年6月 (本書 はじめに より引用) |
|
阿部球理・編著 明石書店 (本書より引用) アメリカ学会に集う研究者である。およそ10年前、非力ながら編者がアメリカ学会に 「先住民分科会」を組織したおり、集ってくれた方々が大半である。私は、アメリカで 活況を呈している「アメリカ・インディアン・スタディーズ」をモデルに、分野横断的な アメリカ先住民学の活発な議論が、学会で始まることを望んだ。それが日本における 「アメリカ先住民学」となって成長し、若手研究者が活躍する日が来ることを望んで いる。事実分科会では、合衆国の「アメリカ・インディアン・スタディーズ」の学位を 取得した少壮学者や、私が指導する3名の博士課程後期の院生たちが発表し、こと に院生たちは、その発表をもとに本書に寄稿することができた。こうした分野の広が りが、日本社会ではあまり知られていないインディアンへの理解を深める貢献になれ ば嬉しい。 (阿部球理) 一体どのように捉えたらよいのであろうか。まず、彼らは「女々しい」や「男女」といっ た、からかいや嘲り、侮蔑の対象としてみなされたわけではなかった。異端視され、 社会の片隅で細々と暮らさなければならない人びとではなかった。ベルダーシュと は、先住民社会において、畏敬、あるいは部族によっては畏怖の念を抱く対象と された人びとであったのである。しかしながら同時に、先住民社会とは、男女のあり 方を性別による役割分業を明確化することで規定している社会でもある。ベルダー シュという、男性でもない女性でもない、どっちつかずの存在がなぜ先住民族たちの 間で許されたのかを、「二分法」と「相互補完性という先住民社会に共通の概念を 基に考えてみたい。 (石井泉美) |
|
|
|
|
横須賀孝弘著 日本放送出版協会 から描いた文献で、歴史にその多くのページを割いて紹介している。それと共に 現在のスー族の一人ひとりのインディアンのあるがままの姿を描き、彼らの聖なる 儀式(ユイピ、サン・ダンス、赤い矢の儀式)や民族の祭典パウワウの様子を詳しく 描き出している。また本書はそれに留まらずインディアンを美化し神格化しすぎて いる最近の傾向にも一石を投じ、その実像を著者なりに解釈している。この傾向は この私のページでも当てはまることだが、白人入植以降インディアンの部族間の 対立・戦争は古き時代のものとは異質なものとなってきたと私は捉えている。詳しく は「インディアンの残虐性の真否」をお読みいただければと思うが、多くのインディ アンの言葉に接するとき、私自身また著者とは違った想いを感じてならない。だが、 近年のインディアンに関しての行き過ぎた美化が産みだした弊害も存在することも 事実であろう。それは「リトル・トリー」に象徴される偽書において、インディアンの 魂が商業主義に利用されていることがまず上げられる。それは彼らが今でも虐げら れている民族であることなど眼中にはなく、自らの私腹を肥やすためだけに利用し ているに過ぎない現実があり、このような偽書は精神世界と呼ばれる分野では顕著 に見られる傾向にある。私自身このホームページを通して主に白人入植以前のイン ディアンの精神文化の実像を探っていきたいと思っている。そしてインディアンに限 らず先住民族が現在置かれている実状と何がそうさせたのかをも理解し、私たちが 歩むべき社会とはどのようなものでなくてはならないのを共に探っていきたいと願っ ている。その為にもインディアンの実像をみなさま自身が自らの手で確かめてみる ことが必要不可欠なのかも知れない。その意味で、本書は美化されすぎている 最近の出版界の傾向に、一石を投じた価値ある文献と言えよう。そして、どんなに 解釈や想いが異なろうが著者も私も彼らインディアンが好きなのだということを。 りだった。総じて、暮らし向きは決して豊かとは言えない。八方塞がりな社会状況の 中で、抱える悩みも多いに違いない。それでも、みんな生きることを存分に享楽して いるようだった。しかも、部族の明日のこともきちんと考えている。例えば、ジョーだ って、確かに酒には弱いが、決してただの酔いどれではない。73年のウンデッドニ ー占拠では仲間とともに戦っているし、部族の進むべき道について考えを訊けば、 しっりとした意見を返してくる。子供の頃から憧れつづけてきた北米インディアン。 野に生きる知恵に富み、逞しく勇敢な、私にとってのスーパーヒーロー、「大平原の 戦士」たち。しかし、その面影は、祭りや儀式など特別の場を別にすれば、今の彼 らにはない。それは、武士道に生きたサムライの姿を現代の日本人に求めても虚 しいのと同じことだ。それでもやっぱり、私は彼らが好きだ。栄光の歴史を背負った 人々の末裔だからではない。彼らを人間として好きになったのだ。彼らのことを想い、 彼らの暮らす居留地の情景を心に浮かべると、そのたびに胸が締めつけられるよ うな懐かしさを感じる。遠い異国の人々であり、不便な片田舎の土地なのに、奇妙 な懐かしさと心のやすらぎを感じるのは、一体なぜなのだろうか? (本書より引用) |
|
インディアンと呼ばれた人びとの苦難・抵抗・希望 清水和久著 明石書店
|
|
グラフィティ・歴史謎辞典15 スチュアート・ヘンリ著 光文社文庫 現状を紹介することは出来ない。北東部とか南西部など異なった地域性を踏まえ ながら簡単な紹介しか出来ないのだろう。ただ、本書の良い点は図版などが多い ことにある。本書はインディアンだけでなく、イヌイットの北米大陸の先住民たちも この図版などを通して紹介されている。 ペリーベイのはずれ、時は1975年の6月末、30人乗りの双発旅客機がツンドラ の砂利敷き滑走路を走り、もうもうと土煙を上げながら飛び立っていくのを見送り ながら、私は頭の中を懸命に整理しようとしている。ツンドラの真っ只中なのに、 見わたす限り雪はどこにも見あたらない。足元には可憐な黄色い花が咲いている。 定期便が運んでくる郵便や生鮮食料品をもって村へ三輪オートバイに相乗りして 去っていく十数人のイヌイットはジーパンとトレーナーにスニーカーという出立ちだ。 私がそれまでいだいていた北極のイメージといえば、年じゅう雪と氷に閉ざされて いる世界、毛皮服を着こんだイヌイットが犬橇を走らせている、という世間なみの 先入観だった。目の前に広がっている情景はあまりにもこのイメージとかけ離れ ている。本書では、ここからはじまった私の北極における考古学と民俗学調査の 成果、そして私自身の認識の変化をたどりながら、日本にはまだよく知られてい ない北アメリカの先住民の歴史と現状を紹介したいと思う。とはいっても、先住民 の全民族を紹介するにはあまりにも頁が少なく、表面的な事柄を取り上げ、全体 的な時の流れを示すのにとどめざるをえない。 (本書 はしがき より抜粋引用) |
|
チェロキー・インディアン涙の旅路 アレックス・W・ビーラー著 片岡しのぶ訳 あすなろ書房
|
|
ハーシュフェルダー&R・スィンガー著 愛川信子訳 明石書店 ティティ」「家族」「ふるさと」「しきたりと儀式」「教育」「厳しい現実」の項目に記された 現代の子供たちの想い。 たちが事実だと言っていることが正しいかどうか確かめよう」と勧めています。事実、 ビバリー・R・スィンガーと私がこの文集のための原稿を選んだ時、私たちのなかに あったのはこの思いでした。先住アメリカ人の若者たちはあらゆることについてたく さん書いていますが、私たちはあえて作文や詩の選択の範囲を、この若者たちの アイデンティティ(訳注 自己証明)、家族、共同体、儀式、歴史、教育、厳しい現実 についての誤解を正すものに狭めました。若者たちは知性と威厳と機知とすぐれた 洞察力でこれらの問題に触れています。若者たちの言葉は、過去百年にわたる アメリカ先住民の生活の現実に対して、生き生きとした、そしてしばしば雄弁な証言 となっています。この若者たちがわれわれに語るべきことは多いのです。 アーリーン・B・ハーシェフェルダー (本書より引用) |
|
![]()
![]() 未読の文献
未読の文献
各文献の前の![]() をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
アメリカ・インディアンの歴史」 グレッグ・オブライエン著 阿部珠理訳 東洋書林 のバランスの良さにあるだろう。アメリカ・インディアンに関する歴史書は、時と して先住民を一方的な被害者として描いたり、中立を目指すあまりヨーロッパ の植民地主義の加害性を充分に明らかにしない態度をとったりするものもあっ た。本書は、ヨーロッパ社会とのコンタクトがもたらした先住民社会および文化 の変容の要因と過程を、できうる限り公正に記述するという姿勢に貫かれて いる。 例えば、インディアン社会の衰退を考える際、その背景として伝染病や白人と の戦い、ヨーロッパの市場経済に巻き込まれる過程で激化する部族間抗争、 諸部族間の伝統的な敵対関係を利用して植民勢力を拡大しようとするヨーロッ パ諸国と、彼らへの先住民部族の自主的な協力などがあげられる。ヨーロッパ 植民勢力の明白な先住民劣等視と彼らの際限ない強奪の一方で、それを容易 にした先住民社会の分断と分裂も明らかになる。そしてそれらが、地域によって 異なる先住民部族社会に共通する歴史であることが納得される。 (本書 訳者あとがき より引用) |
|
アメリカ・インディアンの抵抗史 J・コスター著 清水和久訳 三一書房
|
|
ロナルド・ライト著 香山千加子訳 植田覺監修 NTT出版
|
|
| |
L.H.モルガン著 青山道夫訳 岩波文庫
|
|
|
アメリカ・インディアンの宗教運動と叛乱 ジェイムズ・ムーニー著 荒井芳廣訳 紀伊国屋書店
|
トーマス・R・バージャー著 藤永茂訳 朝日選書
|
|
阿部珠理著 角川書店
|
|
酋長オセオーラとセミノール・インディアン」 ウィリアム・ハートレー エレン・ハートレー著 鈴木主税訳 現代史出版会 部のフロリダ半島に住むセミノール族が、傑出した若い酋長、オセオーラの 指揮のもとに、アメリカ合衆国の移住政策に抵抗して戦った記録である。これ は、新大陸に渡った白人と先住土着アメリカ人の交渉の歴史では、第二次 セミノール戦争として知られている。独立国としての基礎固めを一応終わった アメリカ合衆国は、この戦争にケリをつける(勝ったとは言えない)ことによって、 東部全域から先住民族をほぼ完全に駆逐したわけである(戦いの舞台は、 このあと西部に移り、1890年のウンデッド・ニーの虐殺によって、インディアン の武力抵抗がやむまで同じような侵略と抵抗がくり返された)。新大陸に渡った 白人にとって、アメリカの自然は、征服し、西欧文明の技術によって最大限に 利用すべき対象だった。旧大陸を食いつめて海を渡ってくる白人が、それこそ イナゴのようにふえ、どんな手段を使ってもそれを養わなければならなかった からである。その白人の努力を妨げたのは、きびしい気候や荒々しい自然 だった。しかし、それよりももっと大きな問題は、自然を征服すべきものとは 考えず、そこにとけこんで暮らしている先住民であり、その生き方だった。その 後の両者の交渉の歴史を、ここでくわしく述べる必要はあるまい。白人は、恫喝、 懐柔、詐欺、殺戮など、あらゆる手をつくして、土着アメリカ人の土地を取りあげ ようとした。当然抵抗が起こり、それは軍事力を駆使してのジェノサイドにつな がった。 (本書 訳者あとがき より抜粋引用) |
|
ロバート・A・トレナートJr著 斎藤省三訳 明石書店 子供を白人社会に同化させることを目的とした学校である。はじめの40年間、 主な目標はインディアンの若い子供を昔ながらの生活から切り離し、彼らを 伝統文化から遮断し、彼らに白人中産階級の価値観を植え込むことであった。 「同化」と一言で言っても、その意味するところは1890年から1930年にわ たって繰り返し変わっている。絶えず変更される連邦政府の教育政策のおか げで学校の目標がその時々によって変わってしまう。そういう意味では学校 運営も国家の動向と基本方針に左右されるものである。本書の基底にある ものは変化してやまない同化教育の方針と、その方針が具体的にフェニックス・ インディアン学校にどのように適用されていったかの実態を掘り下げ、報告す ることである。・・・・本書「まえがき」より引用 |
|
エドマンド・ウィルソン著 村山優子訳 思索社 いるように、かつて「ニューヨーカー」に数回にわたり掲載されたものに若干の 修正を加えて単行本として刊行されたものである。内容は一見イロクォイ族の 現状のルポルタージュという形式をとっているが、単に事実の記録と報告に とどまらず、著者の一貫した産業文明に対する鋭い批判と人間へのたゆまぬ 関心が文明および文明社会を無批判に賛美する人々に対して挑戦的とも言え る姿勢で問題を突きつけているという点が、本書の高く評価される所以であろ う。また最初の部分に、これも「ニューヨーカー」に既に掲載されたジョーゼフ・ ミッチェルの短いがすぐれたモホーク族の報告を収録してあるが、これも現代 文明へ適応してゆこうとする努力と伝統的文化への断ち難い思いの間で揺れ 動き、さまよう現代のインディアンの姿を真摯に、また温かい共感をもって描写 しており、それを併せて読者に呈示することによって現代文明に対する疑問を 投げかけている。(中略) 著者が、本書を著すに至った最初の動機は、この ニューヨーク州の先住民イロクォイ族の土地係争問題への関心であった。そし て直ちに、イロクォイ族が<州あるいは連邦>政府の不正義の犠牲になって いることを悟り、彼の知的好奇心と正義感をこの問題に捧げたのである。本書 の中でイロクォイ族の各保留地における土地係争問題の経過が非凡な冷静さ と明敏さをもって記述されている。しかし本書の内容を非常に豊かにし、かつ 奥深くしているのは、単に土地問題を中心とする人種・民族間抗争という視点 にとどまらず、近代文明対伝統的文化、国家(ないし州)権力対市民の権利と いう視点に立ってこの問題を把握しようとしたことである。 (本書 訳者あとがき より引用) |
|
スー族の酋長が記したアメリカ・インディアンの歴史 D・チーフ・イーグル著 神田栄次訳 誠文堂新光社
|
|
スティーブン・J・クラム著 斎藤省三訳 明石書店
|
|
ジャック・M・ウェザーフォード著 小池佑二訳 パピルス
|
|
W・T・ヘーガン著 西村頼男・野田研一・島川雅史訳 北海道大学図書刊行会
|
|
コロンブスと闘う人びとの歴史と現在 上村英明著 解放出版社 先住民族の権利回復運動が大きな飛躍をとげる歴史的な「チャンス」と言える。 しかし残念ながら、この日本では、「国際先住民年」に対する関心は市民か ら行政まで極めて低い。解放出版社から、先住民とは、どういう人びとで、 その人権がどういう状況に置かれているのかという視点から、本を執筆しな いかと連絡を受けた時には、正直に言うと、躊躇してしまった。先住民族は 北極圏から南太平洋までの世界各地で、それぞれの生活を営んでいる。 先住民族としての共通の運命を背負っているが、その歴史的背景、そして、 文化や価値の独自性に至っては、実に千差万別であるからだ。そもそも、 先住民族の歴史と現状、権利を一冊の本にすることなど、それこそ、無謀 な冒険以外のなにものでもない。しかし、例え「冒険」であるにしても、誰か がやならければならないと、しばらくして、思い直すようになった。それは、 第一に、日本における先住民族の権利問題への関心があまりに低く、ある 種の総括的な入門書が、どうしても必要であると痛感することが何度かあっ たからである。第二に、国際的な先住民族への関心の高まりに影響されて、 先住民族の権利問題が紹介されるようにはなってはきたが、そうした紹介も、 上澄みだけをすくうことが多く、基本的な問題や、その歴史がすっぽり抜け 落ちている場合が少なくないからである。先住民族との共生は、言語や風俗、 伝承、行事それだけを取り出し、記録したり、保存したりして達成できると 思われた時代から、はるかかなたに進んでしまった。現在では、民族自決権 や土地権、資源権、環境権が世界各地で議論されており、その土俵の上で 初めて、文化や伝統の維持、発展の問題も検討されるという時代になった のである。こうした状況を理解してもらうためには、誰かが先住民族の置か れている世界的状況とその歴史を包括する本を書くという「冒険」を行うこと しかなかった。 (本書・あとがき 上村英明 より引用) |
|
青木晴夫著 講談社現代新書
|
|
ナンシー・Y・デーヴィス著 吉田禎吾&白川琢磨訳 ちくま学芸文庫
|
|
ルーシー・マドックス著 丹波隆昭 監訳 開文社出版
|
|
アメリカ先住民文学の先駆者たち」 西村頼男著 開文社出版
|
|
西村頼男・喜納育枝 編著 ミネルヴァ書房
|
|
アメリカ先住民文学 青山みゆき著 開文社出版
|
|
L・ハンケ著 佐々木昭夫訳 岩波新書 に終わりなし、また、過去を描く書物は絶えず改訂を施さるべしという古い箴言 が、真理を語るものであることがよくわかる。この改訂は新しい材料の発覚か ら来ることが多く、また誰でも知っている資料から新しい解釈が出てくることも ある。本書を執筆するに当って、私は、これまで利用されたことのない手稿を 含めて、当面の問題に関するあらゆる資料を動員しようと試み、また、私自身 の見解を打ち出すに先立って、従来のすべての解釈に検討を加えようと努めた。 そして、「過去は序幕である」(シェークスピア作『テンペスト』中の言葉)から、 いや少なくとも時折はそうであるから、私は1550年の思想上の闘争が今日に もつながる問題であることを示そうと試みた。アリストテレスの地理上の概念が アメリカ発見に影響したことは、かなり前から知られている。だが、スペインに よる征服期に、彼の先天的奴隷人の説がアメリカのインディオに適用されたと いう事実が、まともに研究されるようになったのはごく近年のことである。一般的 に言って、15世紀以前には本当の意味での人種的偏見なるものは存在しなか った。人類はさまざまに対立する人種ではなく、「キリスト教徒と異教徒」のふた 通りに分かれていたからである。ヨーロッパの、アフリカとアメリカそして東洋の 発展が局面を一変させたのであり、それゆえ世界的規模で人種問題を考えよ うとする者にとって、スペインが経験したことの詳細は大きな意味を持つ。二人 の優れたスペイン人、バルトロメ・デ・ラス・カサスとフワン・ヒネス・デ・セプル ベダが、1550年バリャドリでこの問題について論戦を行ったことは、西欧世界 の知性の歴史における最も興味深いエピソードのひとつである。この時、一個 の植民国家が、おのれが帝国の版図を拡大するのに用いている手段は正義 にかなうか否かという問題を、公の組織によって究明しようとした。これはそれ 以前に例のないことであり、また今後とも決して起こり得ぬことであろう。また この時、何世紀も前にアリストテレスが立てた理論に従って、一人種全体に 劣等者、生まれながらの奴隷人との烙印を押そうとする、近代世界における 最初の試みが見られるのである。この問題に関する激しい論戦、その大論戦 がアメリカに対するスペイン王の政策に及ぼした影響、同じ理論を他の民族に 適用しようとする、以降の時代に見られた試み、16世紀の闘争の現代世界に とっての意味、これらの事柄が本書の内容を成す。 (本書 序 より引用) |
|
歴史を糧に未来を拓くアメリカインディアン 青柳清孝 著 古今書院
|
|
鎌田遵著 岩波新書
|
|
インディアンと植民者の環境史 ウィリアム・クロノン著 佐野敏行 藤田真理子訳 勁草書房
|
|
エリコ・ロウ 著 生活人新書
|
|
東岡耐 著 現代書館 ブルジョア的諸原則に妥協する文明改良思想にすぎない。それは母なる 大地の支配・収奪を容認する自然征服思想である。それは有色人・異邦人 の奴隷化を正当する奴隷主思想である。それは非ヨーロッパ人の植民化・ 帝国的収奪を正当するヨーロッパ帝国主義思想である。それは原始共同体 諸部族に文明化を強要する文明帝国主義思想である。それは無際限的な 「文明の進歩」を信仰する文明至上主義思想である。それは生産力の限り なき発展を盲目的に美化する生産力至上主義である。それは原始共同体 諸部族の征服・強奪と植民地従属国人民の搾取・抑圧から一定の利益を うけている植民帝国内の平民派、小奴隷主的プロレタリアートの改良思想 にすぎない。これに対して、当のマルクス主義者は目を三角にして反論する であろう。マルクス主義こそは誰が何といおうと完全無欠の唯物思想であり、 人類の解放思想であり、普遍的な革命思想である、と。よかろう! アメリカ 合衆国という史上最悪の盗賊帝国の歴史を通じて、マルクス主義文明史観 に対し具体的にチャランケ(談判)することにより、マルクス崇拝者がつくりあ げた輝ける偶像を徹底的に破壊することにしよう。文明社会はいまや急坂 をころげるごとく、奈落に向かっている。階級文明的ないっさいのものの 存立基盤が音をたてて瓦解しはじめた。この人類の未曾有の危機を革命的 に揚棄するものは階級文明社会の、あるいは奴隷主植民社会の諸体系の 中で矛盾の解決をはかろうとするマルクス主義の中にはありえない。それは 腐り切った奴隷主帝国を根本から粉砕しようとする植民地奴隷の革命戦争、 そして汚辱にまみれた階級文明総体の解体をめざす原始共同体諸部族の 革命闘争の中にのみ存在する。赤人被抑圧人民の生きる辺境最深部に 退却し、そこから合衆国帝国主義打倒の狼煙をあげたゲバラ、その闘いを 跳躍台として、世界社会主義共和国の大義のもとに、国際革命戦争を目的 意識的に遂行する新潮流があらわれた。アメリカ盗賊合衆国に災厄あれ! アメリカ盗賊合衆国を美化する一切の勢力に災厄あれ! 第二・第三のベト ナム革命戦争に光栄あれ! 第二・第三のリトルビッグホーン戦に光栄あれ! (本書・はしがきより引用) |
|
![]()
![]() 未購入(新刊も含む)の文献
未購入(新刊も含む)の文献
![]()
アメリカ・インディアン闘争史 ディー・ブラウン 著 鈴木主税 訳 草思社 上巻より以下、引用抜粋。 「いまペクォート族はどこにいるのか? ナラガンシット族、モヒカン族、ポカノケット族、またかつて強力だった他の多くの 部族のわが同胞たちは、いまやどこにいるのか? 彼らは、白人の貪欲と弾圧にあい、さながら夏の太陽にあたった 雪のように消えてしまったのだ。こんどはわれら自身が、戦わずして破壊に身をゆだね、家を、偉大な精霊に与えられた われらの土地を、死者の墓とわれらにとって貴重で神聖なすべてのものを、むざむざ明け渡してしまうのか? 私は、 おまえたちが私とともに、『断じてそうはさせぬ!』と叫ぶことを知っている。」・・・・ショーニー族 テクムシ それはクリストファー・コロンブスとともにはじまった。彼こそが人びとにインディオの名を与えたのである。かのヨーロッパ人 たち、つまり白人は、それぞれ異なった言語を話し、その言葉をインディエン、インディアナー、あるいはインディアンと発音 した。ポー・ルージュ、すなわち赤い皮膚(レッド・スキン)という言葉は、それよりあとに生まれたものだった。異邦人を迎え る時の習慣に従って、サン・サルヴァドル島のタイノー族は、コロンブスとその部下たちに贈物を捧げ、彼らをていちょうに もてなした。 「これらの人々は非常に従順で、平和的であります」と、コロンブスはスペイン国王と王妃に書き送った。「陛下に誓って 申し上げますが、世界中でこれほど善良な民族は見あたらないほどです。彼らは隣人を自分と同じように愛し、その話し ぶりはつねにやさしく穏やかで、微笑が絶えません。それに、彼らが裸だというのはたしかですが、その態度は礼儀正しく、 非のうちどころがないのです」 当然こうした事柄は、未開のしるしではないにしても、弱さのあらわれとして受けとられ、硬直なヨーロッパ人たるコロンブス は、確信をもって、「これらの人びとが働き、耕し、必要なすべてのことをやり、われわれのやり方に従う」ようにしむける べきだと考えた。その後の四世紀あまり(1492年から1890年)にわたって、数百万のヨーロッパ人とその子孫たちは、自分 たちの生き方をこの新大陸の住民たちに押しつけようとしてきたのであった。 コロンブスは、自分をもてなしてくれた友好的なタイノー族十人を誘拐し、スペインにつれ帰り、そこで彼らに白人の生き方 を教えようとした。その一人はスペインに着いてからじきに死んだが、その前に洗礼を受けさせてキリスト教徒にすることは できた。スペイン人は最初のインディアンを天国に送りこめたことを非常に喜び、急いでこの朗報を西インド諸島全体に ひろめた。 タイノー族とアラワク族はヨーロッパの宗教に改宗することを拒まなかったが、ひげを生やした大勢の異邦人たちが黄金や 珍しい石を求めて自分たちの土地を物色しはじめた時には、強く抵抗した。スペイン人は略奪をほしいままにし、村を焼き 打ちした。さらに、多くの男や女や子どもたちを誘拐し、船積みしてヨーロッパに送り、奴隷として売りとばした。アラワク族 の抵抗は、相手をして銃やサーベルの力に訴えさせるという結果を招き、部族全体が雑滅させられた。こうして、1492年 12月12日にコロンブスがサン・サルヴァドル島の岸に足を踏み入れてからわずか十年たらずのうちに、数十万の人びとが ほろんでしまったのである。 新大陸の各部族間の通信はおそく、ヨーロッパ人の蛮行のニュースの伝播は、新たなる征服と植民地建設の急速な ひろがりにほとんど追いつかなかった。しかし、英語を話す白人が1607年にヴァージニアにやってくるよりずっと以前に、 ポーハタン族はスペイン人の文明的な手練手管についての噂を耳にしていた。だが、イギリス人はもっと手のこんだ方法 を用いた。ジェームズ・タウンに植民地を建設し終わるまで平和を確保しておくため、彼らはワフンソナクックの頭に金の 王冠をのせてポーハタン王に叙し、その部族の者たちを働かせて、白人植民地に食物を提供させることを説得させた。 ワフンソナクックは反抗を訴える臣下の声に耳を傾けようとする気持ちと、イギリス人との約束を守ろうとする意志との 板ばさみになって動揺したが、白人のジョン・ロルフが娘のポーハタンと結婚してからは、明らかに自分がインディアンより も白人に近いのだと考えたようだ。ワフンソナクックが死ぬと、ポーハタン族は蜂起して復讐を叫び、イギリス人をもともと 彼らがやってkちあ海の彼方へ追い返そうとした。だがインディアンたちはイギリス人の武器の武力を過小評価していた。 たちまちのうちに八千人のポーハタン族は一千人たらずに減ってしまった。 マサチューセッツでは、事態はいくらかちがったかたちではじまったが、結末はヴァージニアとほとんど同じだった。1620年 にプリマスに上陸したイギリス人は、新大陸の友好的な原住民たちから援助を受けなかったならば、その大半が餓死して しまったにちがいない。サマセットという名のペマクィド族の者と、それぞれがマサソイト、スクァント、ホボマという名の三人 のワンパノーグ族の者が使者を買ってでて、旧大陸を逃れた巡礼者(ピルグリム)たちのところにやってきた。彼らはいず れもいくらか英語を解したが、それは以前に岸にたどり着いた何人かの探検家たちから学んだものだった。スクァントは 一人のイギリスの船乗りにさらわれ、スペインで奴隷として売られたが、別のイギリス人に助けられて逃亡し、やがて国に 帰ることができた。彼とその他のインディアンたちは、プリマスの植民者を救いがたい子どもだと見なしていた。そして 部族の貯えから穀物を分けてやり、どこでどうやって魚をつかまえたらよいかを教え、最初の冬を無事に切り抜けさせた。 春になると、インディアンは白人に穀物の種子を与え、それを撒き、耕作する方法を教えた。 数年のあいだ、これらのイギリス人とその隣人のインディアンたちは平和に暮らしていたが、さらに多くの白人が続々と 船に満載されて岸に着いた。斧のひびきと伐り倒される樹木の音は、いまや白人たちがニュー・イングランドと呼んでいる その沿岸の土地全体にこだました。植民地はしだいに混みあって、白人がごったがえすようになった。1625年に、植民地 の何人かがサマセットにペマクィド族の土地をさらに1万2千エーカーだけ分けてくれと求めた。サマセットは、土地が偉大 な精霊から与えられ、それは空のように限りがなく、誰が所有するものでもないということを知っていた。しかし、これらの 異邦人たちを彼らの奇妙なやり方でからかってやろうと考えて、サマセットは土地を譲渡するための儀式をとり行い、紙に 自分のしるしをつけて相手に与えた。これこそは、イギリス人植民者に与えられたインディアンの土地の最初の譲渡証書 であった。 だが、いまや数千人にふくれあがった植民者の大半は、わざわざそのような儀式をとり行なう手間をはぶいた。1662年に ワンパノーグ族の大酋長マサソイトが死んだ時には、その部族の者は荒野に押し出されていた。マサソイトの息子の メタコムは、団結して侵入者に抵抗しないかぎり、すべてのインディアンの運命は暗たんたるものになると考えた。ニュー・ イングランドの植民者は、メタコムをポカノケットのフィリップ王に叙して、その歓心を買おうとしたが、彼はナラガンシット族 をはじめその地域の他の部族と同盟を結ぶために努力を重ねた。 1675年、植民者による一連の横暴な行動に腹をすえかねて、フィリップ王はインディアン連合軍をひきいて戦争をはじめ、 各部族を滅亡から救おうとした。インディアンは五十二の植民地を攻撃し、そのうち十二を完全に破壊したが、数ヶ月の 戦闘ののち、植民者の火力によってワンパノーグ族とナラガンシット族はほとんど絶滅するに至った。フィリップ王は殺さ れ、彼の首はその後二十年にわたってプリマスの町でさらしものにされた。捕らえられたほかのインディアンの女や子ども といっしょに、フィリップの妻と子どもは奴隷として西インド諸島に売られていった。 オランダ人がマンハッタン島にやってきた時、ペーテル・ミネウィットはその島を六十グルデン相当の釣針とガラス玉で買い 取ったが、インディアンたちにはそのまま居残るようにすすめ、彼らの高価な生皮や毛皮をがらくた同然の品物と交換し つづけた。1641年、ウィレム・キーフトはモヒカン族に貢税を課し、ラリタン族をこらしめるためにスターテン島に兵を派遣 した。だが、非があったのはインディアンの側ではなく、白人植民者の方だった。ラリタン族は自分たちを捕らえようと する相手に抵抗し、兵隊は四人のインディアンを殺した。インディアン側が四人のオランダ人を殺して、これに報復すると、 キーフトは二つの村の全住民を眠っているあいだに虐殺せよと命じた。オランダの兵士は、男や女や子どもたちに銃剣を 突き立て、その身体を切りきざみ、さらに村に火を放ってそこを平らにしてしまった。 さらに二世紀にわたり、白人植民者が内陸を目ざして、アレゲニー山脈の細道をたどり、西に流れる川にそって大いなる 沼地(ミズーリ)に到達する過程ではこれと同じような事件が何度もくり返された。 東部の部族のうちで最強かつ最も進んでいたイロクォイの五部族は、平和のために努力を重ねたが、それは徒労に 終わった。自らの政治的独立を維持するため、数年にわたって血を流しつづけたあと、彼らはついに敗北のうき目を みた。一部はカナダに逃れ、また西に活路を求めた者もあり、さらに保留地の監禁状態の中で余生を長らえた者も あった。 1760年代に、オッタワ族のポンティアックは五大湖地方の諸部族を結集し、イギリス人をアレゲニー山脈の彼方に追い 返そうとしたが、果たせなかった。彼の大きな失策はフランス語を話す白人と同盟を結んだことだった。フランス人たちは、 決定的なデトロイト包囲のさなかに、ポー・ルージュ(赤い皮膚・インディアン)にたいする援助をひきあげてしまったので ある。 それから一世紀のちに、ショーニー族のテクムシは、中西部および南部の諸部族からなる大連合軍を組織し、自分たち の土地を侵略から守ろうとした。その夢は、1812年戦争の戦闘でテクムシが死んだためにはかないものとなった。 1795年から1840年にかけて、マイアミ族は戦いにつぐ戦いに明け暮れ、何度も条約に調印しては、彼らの豊饒なオハイオ 渓谷の土地を譲り渡してゆき、最後には譲るべき土地が皆無になってしまった。 1812年戦争ののち、白人移住者がイリノイ地方に流れこんできた時、ソーク族とフォックス族はミシシッピー川を渡って 逃げた。小酋長の一人ブラック・ホーク(黒い鷲)は後退をがえんじなかった。彼はウィネバゴ族、ポタワトミ族、キカプー 族を同盟させて、新しい植民地にたいして宣戦を布告した。だが、ウィネバゴ族のある集団が、白人の兵隊酋長から 二十頭の馬と百ドルの金で買収されてブラック・ホークを裏切り、彼は1832年に捕われの身となった。彼は東部に運ばれ て監禁され、公開されて人びとの好奇の目にさらされた。1838年にブラック・ホークが死ぬと、成立したばかりのアイオワ 准州の知事は、その頭蓋骨を手に入れて、自分の執務室に飾った。 1829年、インディアンたちからシャープ・ナイフ(鋭いナイフ)と呼ばれていたアンドリュー・ジャクソンが合衆国大統領に 就任した。辺境にあって活躍していた頃、シャープ・ナイフとsの配下の兵隊は数千人におよぶチェロキー、チカソー、 チョクトー、クリーク、セミノールの各部族に属するインディアンを殺したが、これらの南部のインディアンの数はなお多く、 白人との条約で永遠に自分たちのものとして割りあてられた土地にしっかりしがみついていた。議会に送った最初の 教書で、シャープ・ナイフは、これらのすべてのインディアンをミシシッピ川以南に移住させるよう勧告した。「私は、 ミシシッピー川の西の広大な地方を彼らに分けあたえ・・・・インディアン諸部族がそこにとどまるかぎり、その保有を 認めることを妥当だと考える」と。 そのような法を制定したところで、東部のインディアンにたいする約束不履行の実例の長いリストにさらに一例をつけ 加えるだけだったにもかかわらず、シャープ・ナイフはインディアンと白人がともに平和に暮らすことはできないと確信し、 自分の計画によって二度と破られることのない最後の約束がかわされると信じた。1830年5月28日、シャープ・ナイフの 勧告は法律となった。 2年後、彼は陸軍省内にインディアン総務局をつくり、委員を任命して、インディアンたちの運命を左右するこの新しい 法律の適切な運用をはかった。さらに1834年6月、議会はインディアン部族との交易と交渉を規制し、辺境に平和を維持 するための法律を通過させた。こうして合衆国のミシシッピー川以西で、「ミズーリおよびルイジアナ州、あるいはアーカン ソウー准州に含まれない」すべての部分はインディアンの住むところとなるはずであった。いかなる白人も、許可なくして インディアンの土地で交易を行うことは許されず、またいかなる白人もインディアンの土地への移住を許されないことに なった。合衆国軍隊は、この法の規定を侵害したことがわかれば、いかなる白人をも逮捕するはずであった。 だが、これらの法律が効力をあらわす以前に、新たな白人移住者の波が西に押し寄せ、ウィスコンシンおよびアイオワ 准州が形成された。そのためにワシントンの政策立案者たちは、「永遠のインディアン国境」をミシシッピー川からさらに 西経95度線へと移す必要にせまられた(この線は、現在のミネソタ・カナダ国境のウッズ湖から、ミネソタおよびアイオワ 州をたち切って南進し、ミズーリ、アーカンソー、ルイジアナ諸州の西の境に沿ってテキサス州のガルヴェストン湾に 達する)。インディアンを95度線の彼方にとどめ、許可なしの白人にそこを越えさせないために、ミシシッピー川にのぞむ スネリング砦から南にのびて、ミズーリ河畔のアトキンソンおよびリーヴェンワース砦、アーカンソー河畔のギブソンおよび スミス砦、レッド川にのぞむタウソン砦、そしてルイジアナのジェサップ砦に至る一連の軍事拠点に兵士が駐屯した。 時に、クリストファー・コロンブスがサン・サルヴァドルに上陸してから3世紀あまり、イギリス人植民者がヴァージニアと ニュー・イングランドにやってきてから2世紀以上が経過していた。この時までには、岸辺でコロンブスを歓迎した友好的な タイノー族は、完全に抹殺されていた。タイノー族の最後の一人が死ぬよりはるか以前に、彼らの単純な農耕文化は破壊 され、奴隷の働く綿作農業がそれにとってかわっていた。白人植民者は熱帯の森林を伐りひらき、耕作面積をひろげて いた。綿は土壌を疲弊させた。森林という防壁にさえぎられない風は、畑を砂漠でおおいつくした。はじめてこの島を目に した時、コロンブスはそこを「非常に広く、まったく平らで、樹々はこの上なく青々としている・・・・全体が鮮やかな緑に 染められていて目に快い」場所として描いた。コロンブスのあとからやってきたヨーロッパ人は、その植物とそこに住む もの・・・・人間、動物、鳥、魚・・・・を根こそぎほろぼし、そこを荒地に変えてしまうと、あっさり見捨ててしまったので ある。 アメリカの本土では、マサソイトとフィリップ王のワンパノーグ族が、チェサピーク族、チカホミニ族、大ポーハタン連合の ポトマック族ともども、すでに消滅していた(ただポカホンタスのみが記述されているだけだった)。ペクォート、モンタウク、 ナンティコーク、マチャプンガ、カタウバ、チェロー、マイアミ、ヒューロン、エリー、モホーク、セネカ、モヒカンの各部族は 四散し、わずかな生き残りを数えるのみとなった(アンカスの名だけが記憶されていた)。彼らの音楽的な名前はアメリカの 土地と結びついていつまでも残ったが、その屍は燃えつきたおびただしい村落の中で忘れられ、あるいは2千万の侵入者 がふるう斧のために急速に消滅してゆく森の中で失われた。そのほとんどがインディアンの名前を持ち、かつては甘い水 をたたえていた流れは、すでに沈泥と人間の廃棄物でにごっていた。そして大地そのものも荒らされ、酷使されていた。 インディアンの目には、それらのヨーロッパ人が自然のすべてのもの・・・・生きている森とそこに住む鳥やけもの、草の 生い茂った林間の空き地、土地、そして空気そのもの・・・・を憎んでいるかのようにうつった。 「永遠のインディアン国境」の制定につづく10年間は、東部の諸部族にとって悪い時期だった。大チェロキー族は、白人 との戦い、病気、ウィスキーの害をしのいで100年あまりも生きのびたが、いまや抹殺されようとしていた。チェロキー族は 数千の人口を擁していたので、彼らの西部への強制移住は段階的にゆっくりと実施される予定だったが、その土地に アパラチアの金が発見されたため、ただちに大規模な移動が要求されるに至った。1838年秋、ウィンフィールド・スコット 将軍の指揮する軍隊は、チェロキーをかり集め、収容所に押しこんだ(2、300人がスモーキー山中に逃げこみ、何年も のちにノース・カロライナに小さな保留地を与えられた)。その収容所から、彼らはインディアン居住地域をめざし、西に 向かって旅立った。冬の長い旅の途中で、チェロキーの4人に1人が、寒さや飢えや病気のために命を落とした。彼らは その行進を「涙の旅」と呼んだ。チョクトー、チカソー、クリーク、セミノールの各部族も、その南部の故郷をあきらめた。 北部では、ショーニー、マイアミ、オッタワ、ヒューロン、デラウェア、そしてかつては強力だった他の多くの部族が、 みすぼらしい品物や錆びた農機具、穀物の種子の袋をたずさえて、歩いたり、馬や馬車に乗ったりして、ミシシッピー川 の彼方へと旅立っていった。彼らのすべてが、誇り高い自由な平原インディアンの土地に、まるでつてをもたぬ避難民 となってたどり着いたのである。 避難民たちが「永遠のインディアン国境」に守られて落ち着くか落ち着かぬかに、軍隊がインディアンの土地を通って西に 進撃しはじめた。合衆国の白人・・・・たびたび平和を口にするが、めったに平和を実現したことのない者たち・・・・は、 メキシコのインディアンを征服した白人との戦いにおもむいたのである。1847年にメキシコとの戦争が終わった時、合衆国 はテキサスからカリフォルニアに至る広大な領土を獲得していた。その土地のすべては、「永遠のインディアン国境」の 西にあった。 1848年、カリフォルニアに金が発見された。2、3ヶ月のうちに、ひと山あてようとする数千人の東部人がインディアン・ テリトリーを通っていった。サンタ・フェ・トレールやオレゴン・トレールにそった地域に住み、狩猟を行っていたインディアン たちにとって、許可を得て交易者やわな猟師や伝道師を乗せて走る乗合馬車を時どき見かけるのは珍しいことでは なかった。だが、突如として街道に馬車があふれるようになり、それらの馬車は白人を満載していた。その白人たちの 大半はカリフォルニアの金を目当てにしていたが、中には東西に方向を転じてニュー・メキシコに向かったり、北西に 針路をとってオレゴン地方を目ざしたりする者もいた。 こうした「永遠のインディアン国境」侵犯を正当化するために、ワシントンの政策立案者は明白な宿敵という考えをひねり 出し、その言葉によって領土拡張熱を至上の高みへとひきあげた。ヨーロッパ人とその子孫は、宿命的にアメリカ全土を 支配するよう定められている、彼らは優秀な民族であり、したがってインディアン・・・・その土地、その森林、その鉱物資源 を含めて・・・・にたいして責任がある、というわけだった。その土地のすべてのインディアンを抹殺し、あるいは駆逐して しまったニュー・イングランド人だけが、マニフェスト・デスティニー(明白な宿命)の考えに反対した。 モドク、モハヴ、ペイユート、シャスタ、ユマの諸部族、さらに太平洋沿岸のおよそ100を数える他のあまり知られていない 部族は、その問題についてまったく相談を受けなかったが、カリフォルニアは1850年に合衆国の第31番目の州に昇格し た。そしてコロラドの山中で金が発見されると、新たに投機師の大群が平原を越えてむらがった。新しく広大な2つの准州、 すなわちカンザスとネブラスカがつくられ、平原の各部族の領土のほとんど全部をそこに組み入れた。1858年にミネソタ州 が州に昇格し、その境界は「永遠のインディアン国境」なる95度線の彼方に100マイルもひろがった。 こうして、シャープ・ナイフ・アンドリュー・ジャクソンによってインディアンとの交易と交渉を規制する法律が制定されてから、 わずか4分の1世紀にして、白人の移住者は95度線の北と南の両面からこれをおかし、さらに白人の鉱山師や交易者の 先行分子はあえて中心部にまで浸透したのである。 1860年代初頭のその当時こそ、合衆国の白人がおたがいに戦争をはじめた時期だった。それは青色服(北軍)と灰色服 (南軍)の戦い、すなわち南北戦争である。1860年には、アメリカの各州と准州にはおよそ30万人のインディアンがいたと 考えられ、その大半はミシシッピー川の西に住んでいた。さまざまな推定によれば、その数は最初の移住者がヴァージニア とニュー・イングランドにやってきた当時にくらべて、2分の1から3分の1に減少していた。生き残ったそれらのインディアン たちは、いまや東部と太平洋沿岸で膨張をつづける白人人口・・・・3000万あまりのヨーロッパ人とその子孫たち・・・・に はさまれ、圧迫されていた。残されていた自由な部族が、白人の内戦で自分たちの領土にたいする圧迫が多少なりとも 緩和するだろうと信じたならば、彼らはじきに幻滅の悲哀を味わうことになったのである。 西部で最も数が多くて強力な部族は、スーあるいはダコタであり、それはいくつかのより小さなグループに細分されて いた。サンティー・スーはミネソタの森林地帯に住み、すでに多年にわたって植民地の膨張に押されて後退をつづけて いた。ムデカウントン・サンティーのリトル・クロー(小さい馬)は、東部の諸都市を旅する機会を得て、合衆国の力には 抗しうべくもないと確信した。彼はしぶしぶ自分の部族を説得して、白人の進む道を明け渡した。別のサンティーの指導者 ワバシャも不可避の事実を受け入れたが、彼もリトル・クローもそれ以上自分たちの土地を譲り渡すことは何としても 反対する覚悟だった。 大平原の西のはずれには、全員が馬を乗りまわし、完全な自由を満喫していたテトン・スーがいた。彼らは白人移住者に 屈服した森林地帯に住むサンティーの従兄たちをいくらか軽蔑していた。いちばん数が多く、自分たちの土地を守るおのが 能力に最も自信をもっていたのは、オグララ・テトンだった。白人が南北戦争をはじめた当時、彼らの傑出した指導者は 38歳の俊敏な戦士団酋長、レッド・クラウド(赤い雲)だった。まだ若過ぎて戦士にはなれなかったが、クレージー・ホース (狂った馬)は聡明で恐れを知らぬ10代のオグララだった。 アトン・スーの一分派であるフンクパパ族のあいだでは、20代半ばの一人の若者がすでに猟人かつ戦士として名声を 博していた。部族会議の際に、彼は白人のいかなる侵略にも断固として反対した。その名はタタンカ・ヨタンカ、すなわち シッティング・ブル(すわった雄牛)であり、ゴールという名の孤児の少年の良き師であった。オグララ族のクレージー・ ホースとともに、彼は15年後の1876年に一つの歴史をつくることになった。 まだ40歳には間があったが、スポッテド・テイル(まだらの尾)はすでに、西部のはずれの平原に住むブリュレ・テトン族の 主たるスポークスマンとなっていた。スポッテド・テイルは男前の柔和なインディアンで、すばらしい宴会と従順な女がことの ほか好きだった。彼は自分の生き方と住んでいる土地が気に入っていたが、戦争を避けるためには喜んで妥協するつもり だった。 テトン・スーと近い関係にあったのは、シャイアン族だった。ずっと以前には、シャイアンはサンティー・スーのミネソタに 住んでいたが、しだいに西に移住して馬を乗りこなすようになった。いまでは北方シャイアン族はパウダー川とビッグホーン 地方をスー族と共有し、近くに野営することもしばしばだった。40代のダル・ナイフ(鋭いナイフ)がこの部族の北に住む グループの傑出した指導者だった(自分の部族の中ではダル・ナイフはモーニング・スター(明けの明星)として知られて いたが、スー族は彼をダル・ナイフと呼び、同時代の記述の多くもその名称を用いている)。 南方シャイアン族はプラット川にそって南下し、コロラドおよびカンザス平原に村をつくった。南方の分派のブラック・ケトル (黒い釜)は、若くして偉大な戦士となった。中年の終わりに達した彼は公認の酋長だったが、サザーン・シャイアンの若者 やホタミタニオ(ドッグ・ソルジャー=戦士団の一つ)は、男ざかりのトール・ブル(背の高い雄牛)やロマン・ノーズ(ローマ人 の鼻)のような指導者に追随する気持が強かった。 アラパホ族はシャイアンの古くからの協力者で、同じ地域に住んでいた。そのうちのある者はノーザン・シャイアンと行動を ともにし、他の者はサザーン・レイヴン(小さなワタリガラス)が、当時の最も良く知られた酋長だった。 カンザス・ネブラスカの野牛(バッファロー)棲息地の南にはカイオワ族がいた。カイオワ族の老人の中にはブラック・ヒルズ をありありと思い出せる者もいたが、この部族はスー、シャイアン、アラパホの連合勢力に押され南下した。1860年までに は、カイオワ族は北部平原の諸部族と平和な関係を保ち、コマンチ族と同盟を結んでいた。コマンチの支配する南部の 平原に、入りこんでいたのである。カイオワ族は数人の偉大な指導者を擁していた。年とった酋長サタンダとローン・ウルフ (一匹狼)、聡明な政治家キッキング・バード(陽気な小鳥)などである。 たえず移動し、多くの小集団に分かれていたコマンチ族は、部族全体を統轄する指導者を持たなかった。きわめて高齢 のテン・ベアーズ(10匹の熊)は、戦士の酋長というよりは詩人だった。1860年には、のちにコマンチ族をひきいて、その バッファロー棲息地を守るための最後の闘争をすることになる混血のクアナ・パーカーは、まだ20歳になっていなかった。 乾燥しきった南西部には、スペイン人を相手に250年にわたってゲリラ戦を展開してきた古強者のアパッチ族がいた。 スペイン人は彼らに手のこんだ拷問と四肢切断の技術を教えこんだが、ついにこの相手を屈服させることはできなかった。 ・・・・おそらく6000人足らずのいくつかのバンドに分かれていた・・・・が、その荒涼たる自然の恵みに乏しい土地を頑強に 守ることにかけては、彼らはすでに定評があった。60代の終わりにさしかかったマンガス・コロラドは、合衆国の友好条約 に調印したが、その領土に鉱山師や兵隊が流入したことで、すでに白人に幻滅していた。その義理の息子のコチーズは、 なお白いアメリカ人とうまくやっていけるだろうと信じていた。ビクトリオとデルシャイは白い侵入者を信用せず、つねに 白人を敬遠していた。50代になっていたが、なお生皮のように丈夫だったナナは、英語を話す白人に、自分がそれまで ずっと戦ってきたスペイン語を話すメキシコ人と似たようなものだと考えていた。20代のジェロニモは、まだその実力を 発揮していなかった。 ナヴァホ族はアパッチと関係があったが、ほとんどの者がスペインの白人の生き方を見習い、山羊や羊を飼育し、穀物 や果物を栽培していた。この部族には、牧夫または織工として富み栄えたバンドもあった。ほかのナヴァホ族はひきつづき 遊牧民として暮らし、旧敵のプエブロ族や白人移住あるいは自分たちの部族の裕福な者を襲った。口ひげを生やし、背が 高くて、がっしりした体格の家畜飼育者、マヌエリトがその大酋長だった。彼は1855年のナヴァホ族の選挙で選ばれたので ある。1859年に、数人の無鉄砲なナヴァホがその領土にいた合衆国市民を襲った時、アメリカ陸軍は罪人を追及する かわりに、ナヴァホ族の泥の小屋を破壊し、マヌエリトとそのバンドの成員の所有になるすべての家畜を射殺するという やり方で報復した。1860年までには、マヌエリトとナヴァホ族の彼の追随者たちは、ニュー・メキシコ北部およびアリゾナに おいて、合衆国を相手に宣戦布告なしの戦いをくりひろげていた。 アパッチ族とナヴァホ族の領土の北のロッキー山中には、攻撃的な部族で、その南に住むより平和的な隣人をとかく 襲撃したがるユート族がいた。最も良く知られたその指導者のウーレイは、白人とのあいだに平和な関係を結ぶことを 望み、傭兵となって他のインディアン部族にあたることさえ辞さないほどだった。 西部の果てに住む部族のほとんどは、あまりにも小さく、あまりにも細分化されているか弱すぎて、さほどの抵抗力を 持たなかった。カリフォルニア北部とオレゴンの南部にいたモドク族は、1000人足らずの勢力をもって、自分たちの土地 を守るためにゲリラ戦を展開していた。カリフォルニアの植民者からキャプテン・ジャックと呼ばれたヤントプッシュは、 1860年にはまだ一介の若者にすぎず、指導者として試練にぶつかるのはそれから12年後のことだった。 モドク族の北西に位置したネ・ペルセ族は、ルイスとクラークの探検隊が1805年にその領土を通って以来、白人と平和 関係を保って暮らしていた。1855年に、この部族に属するあるバンドが、ネ・ペルセ族の土地を合衆国に植民地として 譲渡し、大きな保留地の内部にとじこめられて暮らすことに同意した。部族のほかのバンドは、ひきつづきオレゴンの ブルー・マウンテンとアイダホのビタールート山脈のあいだを徘徊していた。北西部は広大だったので、ネ・ペルセ族は、 いつでも白人とインディアンの双方が自分なりに適当だと考えたやり方で利用しうるだけの土地はあると信じていた。のち にジョゼフ酋長として知られるヘインモット・トーヤラケットは、1877年に戦争か平和かをめぐって重大な決断に迫られる ことになるが、1860年には彼はまだ20歳で、酋長の息子だった。 ペイユート族のネヴァダ地方では、のちに西部のインディアンにたいして、短期間ながら強力な影響力をおよぼすことに なるウォヴォカという名の未来の救世主が、1860年にはまだわずか4歳だった。 このあとの30年のあいだに、これらの指導者たちとさらに多くの者が、歴史と伝説の舞台に登場することになった。 これらの人びとの名は、彼らをほろぼそうとした者たちの名前と同じように、やがて広く知られるようになったのである。 老若を問わず、彼らのほとんどが、1890年12月に傷つい膝(ウーンデッド・ニー)においてインディアンの自由が象徴的な 終わりを告げるよりずっと以前に、大地に埋もれてしまう運命にあった。それから1世紀をへだてた、この英雄不在の 時代にあっては、あるいは彼らこそがすべてのアメリカ人のうちで最も英雄的な存在なのかもしれない。 |
![]()

Soyaksin - Blood
Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)

![]()