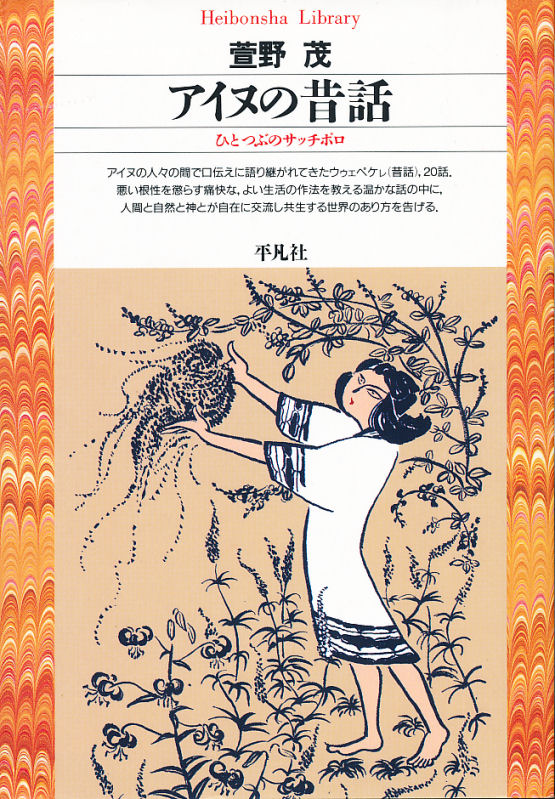
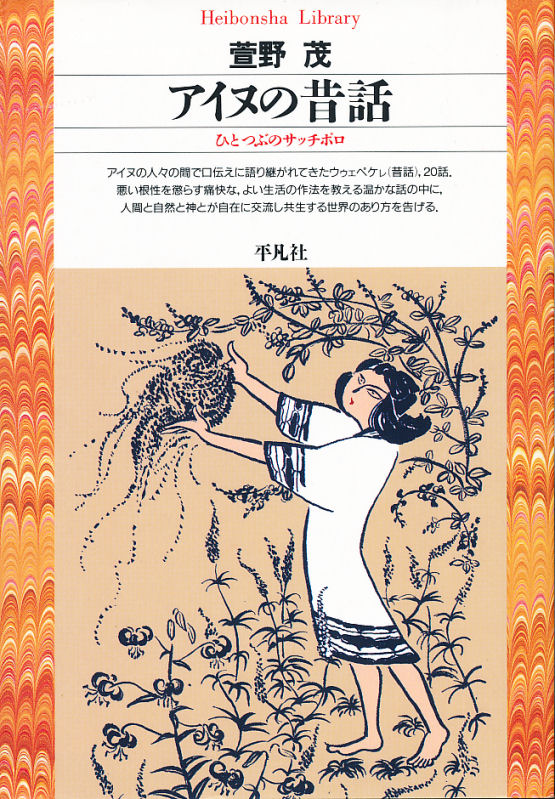
![]() 「アイヌの昔話 ひとつぶのサッチポロ」
「アイヌの昔話 ひとつぶのサッチポロ」
萱野茂 著 平凡社
|
問わずにはいられない。子どもへの躾や教育、それは親や教師などから押し 付けられたものだと、自我の欲求との折り合いがつくはずもない。ただ、それ が自分自身が主体的に、そしてその昔話の世界がまるで子どもの心の世界 に溶け込んでしまったら、その昔話に宿る教訓は子どもの力となり生きる指針 をも与えるものになるのかも知れない。民族が太古の昔からの経験を通して、 次の世代に引き継がなければならない大切なものを伝えていく。まるでそれは 太古の生きた人間からの贈り物であり、彼らが生きた証でもあるのだろう。私 たちは、この昔話に込められた想いを感じることが出来るのだろうか。 (K.K)
|
![]()
|
悪い根性を懲らす痛快な、よい生活の作法を教える温かな話の中に、人間と 自然と神とが自在に交流し共生する世界のあり方を告げる。 (本書より引用)
|
|
本書 はじめに より引用
ありませんでした。石油ランプがあればいいほうで、ランプがあっても、たまたま石油 を買うお金がないため、灯の点らない三分芯のランプが、ほやの片方を黒くしてぶら 下がっていたものです。
そのような暗い生活の中で、祖母はかつては、孫のわたしをこよなく愛し、自分が知っ ているすべてのアイヌ語を、小さい孫に受け継がせようと努力していたかのようでした。 昭和8年4月、わたしは二風谷小学校へ入学、学校では日本語の教科書、サイタ、サイ タ、サクラガサイタ。ススメ、ススメ、ヘイタイススメ。家へ帰ると祖母が語るウゥェペケレ というアイヌのむかしばなしに耳を澄ませ、目をかがやかせ、物語の主人公になったよ うな気持ちで胸をわくわくさせながら聞いたものです。
家庭での祖母との語らいは、完全にアイヌ語だけ、家族同士では日本語とアイヌ語が ごちゃまぜという具合でした。そんな環境のなかで育ったわたしは、母国語であるアイ ヌ語と、外国語である日本語と、両方聞き覚えてしまったのです。それが昭和20年1月、 祖母が亡くなるまでつづきました。祖母が亡くなったとたんに、身辺からアイヌ語が消え、 わたし自身もアイヌぎらいになっていました。それがふとしたことがきっかけで、一度捨て たアイヌ語や文化を、見直し、ひろい上げたのが昭和28年であったでしょうか。
手はじめに、村から持ち去られるアイヌの生活用具を自費で買い集め、流出を食い止 め、つぎに録音をしはじめたのです。民具、つまり生活用具からはいって、ことばの大事 さを知り、録音をはじめてから20年の歳月が流れました。
この本の話は、いままで録音してあった500時間、そしてたくさんの話のなかから選び 出したものです。17,18年もむかしの録音テープを再生翻訳しながら、子どものとき、祖母 が聞かせてくれた数多くのむかしばなしやアイヌ語が、これほど役立つとは思いもしな かったことです。
それにしても、アイヌ語の現状はどうなのだろうか。むかしのままのアイヌ語でむかし ばなしを語れる人がいるにはいるが、聞いて理解できるアイヌが少なく、生活様式も 一般化してしまいました。長い歴史の中で形づくられてきたことば、民族の文化遺産 アイヌ語が、いま、地球上から消えようとしていることは、まぎれもない事実です。そう したなかで、この小さいむかしばなしの本が、アイヌ文化を知るために、そしてことば の命を復活させるために、少しでも役に立てばいいなあと考えています。
|
![]()
|
|
|
2012年5月24日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |
|
2012年5月21日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |
