

![]() 「重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ『ノート』抄」シモーヌ・ヴェイユ著
「重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ『ノート』抄」シモーヌ・ヴェイユ著
田辺保・訳 講談社新書
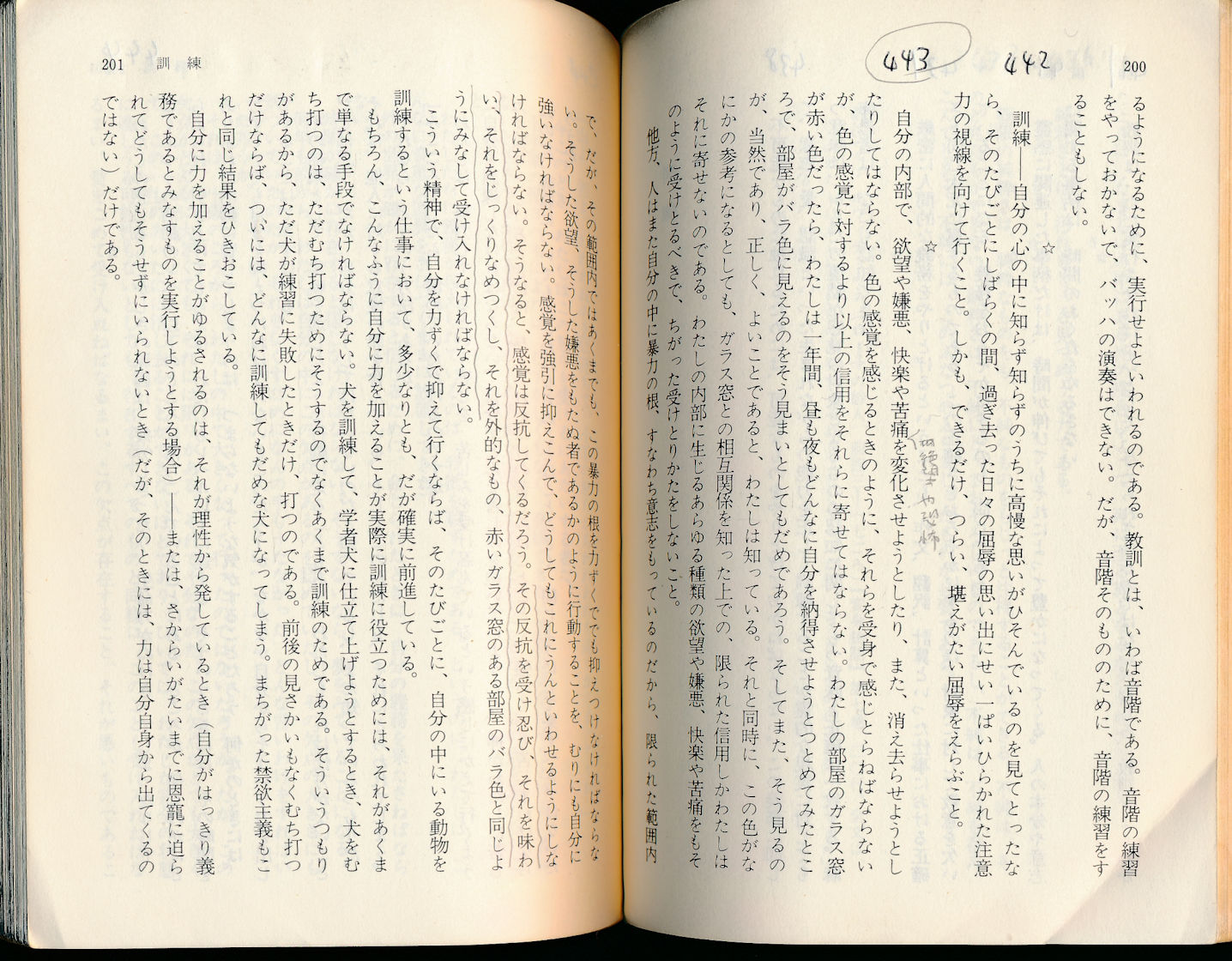
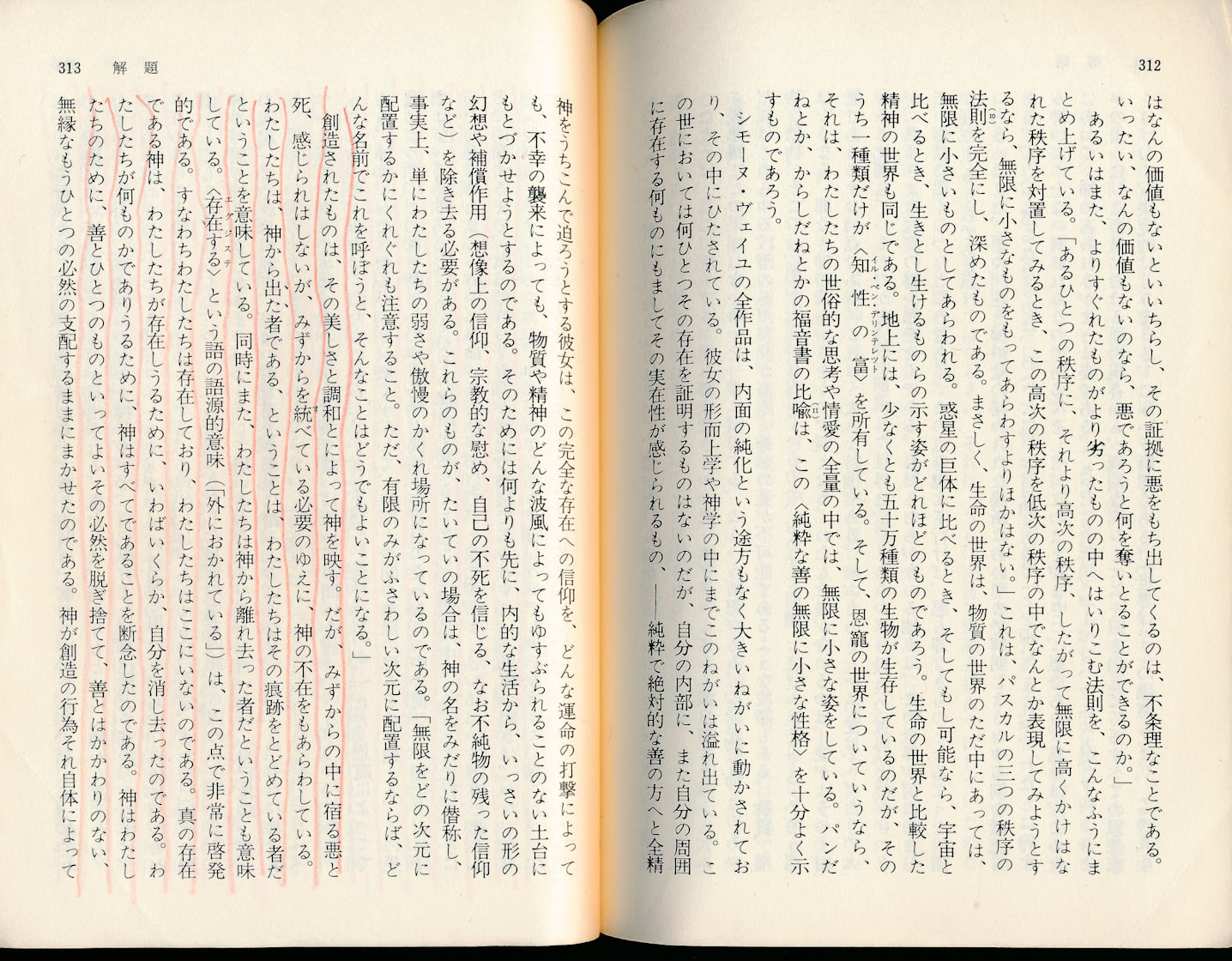
![]()
 本書 訳者あとがき より抜粋引用 の手によって選び出され編集された断想の集積であることは、ティボン自身による「解題」の中に詳細にその 経過が報告されている。ティボンはこの十分に好意と共感のたたえられた文章の中で、彼女と知り合うにい たった機縁、次第にシモーヌ・ヴェイユという稀有の人間の素地があきらかにされて行く過程、彼がさいごに 見出した彼女の本質を経緯と愛情をこめ、公正に描き出して行くのだが(そこにティボンという人の包容力に 富んだ、重厚な人柄もしのばれるといっていい。ティボンがペラン神父と共に著した別の一書「私たちの知って いたままのシモーヌ・ヴェイユ」の中では、かれの筆づかいはさらに熱を帯び、遠く失われた対象への愛慕の 情を抑えきれずにそこここに洩らしている)、この一文を少し注意して読んでみると、むろん好もしい恥じらいの 表白は必ず添えられているのだが、必要より以上に、自分自身とシモーヌ・ヴェイユとの内的なつながりが強調 されているふうに思えるし、その友愛関係や「ふたりで交わされた長い会話」のおかげで自分には彼女の思想 に近づき、そのととのわぬ表現形式を整理しうる資格が与えられているのだと少々弁明じみて(あるいは、自己 確認のためのように)記されているのもいくらか気にかかるのである。ティボンの善意や、対象への愛着の深さ を疑うことはできないであろう。一種畏怖にも似た尊敬の思いをシモーヌ・ヴェイユに対して抱きつづけて、その 生前にも、また死後においても、肉声を通じ、またペンのあとをたどりながら、ティボンが彼女の思想をたえず 自分のたましいの糧とくみとろうと心をうちひらいていたことも確かであろう。そのかぎり、たとえ厳密な意味で の客観化の作業をすすめることの不可能をかれ自身は意識していたとしても、むしろ望むうるかぎりの広い心 で対象の純粋な本質を包みこみ、ある程度の秩序において配列し、ともかくも一応の整然とした印象を与えう るような形で読者に提供できる編者として、現実の彼女を知っていた人の中でティボンほどの適任者がほかに あったとは考えられない。ティボンという人の、フランス人としてたぐいまれな融和力の資質をわたしは否定でき ないのである。 あるが、後に田辺 保 訳で講談社から「重力と恩寵」という題で出版 される。「重力と恩寵」のヴェイユの言葉はこちらに掲載しております。 |
本書 解題 より抜粋引用 追われた両親が、仮の宿をもとめていた。マルセイユへもわたしは、何度か彼女に会いに行った。カタラン街 のその小さなアパートの一室からは、かがやかしいばかりな水平線のかなた、はるか遠くまでを見おろすこと ができるのだった。そのあいだに、彼女の両親は、アメリカ合衆国への出発の準備をととのえていた。彼女は 不幸な祖国への愛着をたちきれず、迫害をこうむりつつある友人たちと運命を共にしたいとの望みにもえて いたから、両親について行ったものかどうか長いあいだためらっていた。さいごにはその決心をしたのだが、 それも向こうへ行けば、ソ連か英国へ渡ってこられる便宜がありそうな希望をいだいていたからである。わたし がさいごに彼女と会ったのは、1942年5月の初めだった。駅まで送りに出ていたわたしに、書類でふくらんだ 一個の折りかばんを手渡し、それを読んでくれるように、彼女の亡命中、あずかっておいてくれるようにと頼ん だ。別れぎわに、わたしは、わざと冗談めかして、自分の心の動揺を外にあらわすまいとして、「また会おうね、 この世か、でなけりゃあの世でね」といった。彼女はとたんに真顔になって、「あの世ではもう会えないのですよ」 とこたえた。この世で各自の〈経験的な自我〉を形作っている境界は、永遠の生命の中でひとつとされるとき、 消えてしまうという意味だったのだろう。わたしはしばらく、彼女が通りを向こうへ去って行くのを眺めていた。 わたしたちはその後、二度と会わないはずである。時間の中では、永遠なるものとの触れ合いは、おそろしい 程はかなく、過ぎ去ってしまうものである。 家へもどると、わたしは、シモーヌ・ヴェイユの原稿に目を通した。それは10冊ばかりのノートで、その中に 彼女は毎日、自分の考えついたことを書きとめていた。各国語での引用文が入りまじり、厳密には彼女しか わからない記号がちりばめられていた。そのときまで、わたしは彼女の作品としては、二、三の詩篇、「カイエ・ デュ・シュド」誌にエミール・ノヴィスというアナグラムによる匿名で発表したホメーロスに関する労作ぐらいしか 読んだことがなかった。以下に公表される各文は、これらのノートからの抜萃である。わたしはこのあともう 一度、シモーヌ・ヴェイユに手紙を書いて、これらのノートの中身がどんなにわたしを感動させたかを知らせる 機会があった。アルジェリアのオランから彼女は次のような手紙を書いてよこした。この手紙には個人的な 調子が含まれているのだが、その全部を引用させていただきたいと思う。そこで彼女自身が、本書の出版の 理由を説明し、弁明しているからである。 「なつかしいお友だち、今こそ、お互いに永遠の〈さようなら〉をいわなければならないときが来たように思われ ます。もうこれからは、たびたびお便りをいただくこともむずかしくなるでしょうし・・・三人の愛しあっているかた がたが暮していらっしゃるあのサン・マルセルのお家が、むごい運命の手からまぬがれるようにと祈っており ます。そこには、何かしらとても大切なものがあります。人間の生存はあまりにも脆く、あまりにも危険にさらさ れているので、ふるえずにはそれを愛することができません。わたし以外のみんなの人々が、あらゆる不幸の 可能性から完全には守られていないのだということを、真底から仕方がないのだと思うような気持ちには、これ まで一度もなれませんでした。これでは、神さまの御心に従う義務にはひどくそむいていることになりますが・・・ あなたは、わたしのノートの中には、思ったよりも多くのものがあって、思ってもいなかったものまでが見つ かった、でもそれはひそかに期待していたものだったといってくださいます。とすれば、それらはあなたの所有 にしてくださっていいのです。それらが、あなたの内部で変質をとげて、いつか、あなたの著作のどれかの中に あらわれてきてくれたらうれしいのにと思っております。なぜなら、どんな思想でも、わたしと運命をともにする よりも、あなたと運命をひとつにする方がずっといいに決まっていますもの。この世で、わたしはきっとよい運命 をもつことができないだろうという気がしています。〈あの世でなら、もっとよい運命になるはずと当てにしている からではありません。そんなことは、信じられないことです〉。わたしは、ほかの人と運命をともにするのが適し ているような人間ではありません。人間というものは、多少の差はあれ、だれでもそういったことは予感できる ものなのですね。けれど、わたしにもどうしてなのかわからないのですが、ふしぎにも、わたしの思想には分別 が欠けていたように思われるのです。こうしてわたしの所にまでやってきてくれた思想に対しては、どうかよい 落ち着き場所を与えてやればいいと、わたしはそれだけしかなにも望んでおりません。それらの思想が、あな たのペンの下に宿る所を見つけ、形をかえてあなたという方の姿を反映するようになれば、どんなにうれしい ことでしょうか。そうなればわたしもいくらか責任感や心の負担が軽くなるというものです。真理は、とても考え 及ばない程、あわれみを存分にふりそそいで、わたしにその姿をときとして見せてくれようとしているふうです のに、このわたしは、自分のかずかずの欠点のゆえに、見えてくるままの真理に仕えることもできずにいるの です。そう思いますと、重いものが心にのしかかってくる感じがいたします。どうか、このすべてを受けとってくだ さいますように。わたしも飾り気なしに申し上げているのですから、どうか何もおっしゃらずに。真理を愛する人 にとっては、実際にものを書くにあたって、ペンをもつ手も、その手と切り離せない肉体もたましいも、その社会 的な外被をもすべて含めて、その重要性なんて、無限に小さいものにすぎません。等級などつけられないぐら いに無限に小さいものです。ですから、実際にだれが書いたのかということなどは、それがわたしであろうと、 またあなたであろうと、わたしの尊敬する作家のだれかであろうと、せいぜいこの程度の重要性しか、わたしは 認めることができません。わたしが多少とも軽蔑している作家についてだけ、だれが書いたかということが問題 になります。 これらのノートについては、あなたがもし聞かせてやりたいと思われる方がありましたら、よいとお考えになる 一節を読んでくださっても結構ですが、一冊であろうとだれの手にも渡らないようにしてくださいますようにという ことはもう申し上げたでしょうか・・・三、四年のあいだ、わたしのうわさを聞かれることもなければ、完全にあな たのものになったのだとお考えになってください。 あなたに、こういうことを何もかも申し上げるのは、心の屈託を少しでもなくして出発したいからです。ただひと つ、まだわたしの中に残っていて、十分成長しきっていないものまでを全部、あなたにおゆだねすることができ ないのは、残念です。けれど、ありがたいことに、わたしの中にあるものは、どうせ価値がないものか、でなけれ ば、完全な形では、わたしの外側の、清らかな場所に宿っているもので、そこにあれば、どんな損傷を受ける こともありませんし、いつでもまた下へおりてくることもできます。こうしてみますと、わたしに関することなんぞ、 なにひとつどんな重要性もないといっていいわけです。 それにまた、わたしはこう思っていたいのです。お別れはいくらかショックでしょうが、今後は何ごとがわたしに 起ころうとも、そんなことであなたが決して悲しんだりなさらないだろうと。また、ときにわたしのことを思い出し てくださることがありましても、子どものころに読んだ本の思い出と同じようにみなしてくださることだろうと。わた しは、自分の愛する人々に、どんな苦しみも決して与えはしないと確信していたいので、どの人の心の中にも、 あくまでもどんな小さな場所をも占めていたくないのです。 あたたかい慰めになるお言葉のかずかずをわたしに語りかけ、また書きよこしてくださったあなたの広いお心 を、わたしは忘れません。もっとも、今は、このわたしがそうなのですが、そういうお言葉ですら信じられない 状況にあります。それでもやはり、こういうお言葉が支えであることにかわりはありません。おそらく、十分すぎ るほどにそうなのでしょう。これから先もずっとお互いに手紙のやりとりをすることができるものかはわかりま せん。でもそんなことはそうたいしたことではないのだと考えなければならないのでしょう・・・ もしわたしが聖人でしたら、あのお手紙の中に述べられていたお申し出を承知することもできたでしょう。わたし がとてもさもしい人間である場合にも同じく承知することができたでしょう。なぜなら、先の場合には、わたし自身 の我意なんてとるに足りないわけですし、後の場合にはそれだけが何よりたいせつになるからです。でも、わた しはこのどちらでもないので、問題にはならなかったのです・・・」 シモーヌ・ヴェイユはさらに、カサブランカから、次いでさいごにニューヨークから、手紙をよこした。このあと、 非占領地帯までドイツ軍が占拠したため、わたしたちの文通は途絶えてしまった。1944年11月、彼女のフランス への帰国を待っていたわたしは、共通の人たちを通じて、すでに1年前に彼女がロンドンで死んだことを知らさ れた。 ひたされている。彼女の形而上学や神学の中にまでこのねがいは溢れ出ている。この世においては何ひとつ その存在を証明するものはないのだが、自分の内部に、また自分の周囲に存在する何ものにもましてその 実在性が感じられるもの、・・・純粋で絶対的な善の方へと全精神をうちこんで迫ろうとする彼女は、この完全 な存在へと信仰を、どんな運命の打撃によっても、不幸の襲来によっても、物質や精神のどんな波風によって もゆさぶられることのない土台にもとづかせようとするのである。そのためには何よりも先に、内的な生活から、 いっさいの形の幻想や補償作用(想像上の信仰、宗教的な慰め、自己の不死を信じる、なお不純物の残った 信仰など)を除き去る必要がある。これらのものが、たいていの場合は、神の名をみだりに僭称し、事実上、 単にわたしたちの弱さや傲慢のかくれ場所になっているのである。「無限をどの次元に配置するかにくれぐれも 注意すること。ただ、有限のみがふさわしい次元に配置するならば、どんな名前でこれを呼ぼうと、そんなことは どうでもよいことになる。」 創造されたものは、その美しさと調和によって神を映す。だが、みずからの中に宿る悪と死、感じられはしない が、みずから統べている必要のゆえに、神の不在をもあらわしている。私たちは、神から出た者である。という ことは、わたしたちはその痕跡をとどめている者だということを意味している。同時にまた、わたしたちは神から 離れ去った者だということも意味している。〈存在する〉という語の語源的意味(「外におかれている」)は、この 点で非常に啓発的である。すなわちわたしたちは存在しており、わたしたちはここにいないのである。真の存在 である神は、わたしたちが存在しうるために、いわばいくらか、自分を消し去ったのである。わたしたちが何もの かでありうるために、神はすべてであることを断念したのである。神はわたしたちのために、善とひとつのもの といってよいその必然を脱ぎ捨てて、善とはかかわりのない、無縁なもうひとつの必然の支配するままにまかせ たのである。神が創造の行為それ自体によってしりぞいて行ったあと、この世界にはたらく主要な法則は、重力 の法則であり、それは、存在のどの段階においても類比するものが見出される。重力とは、何よりもとくに〈神か ら遠ざかる〉力である。重力は、被造物おのおのを押しやって、自己保有または自己拡大を可能とするすべて のものを求めさせようとする。トゥーキュディースの言葉を用いるならば、自分にできるかぎりのあらゆる権力を 行使させようとする。心理的には、あらゆる自己肯定、また自己回復の理由としてもちだされるもの、わたした ちが揺らぎだした自分の生を内側から固めるため、つまり、神の外側で神と対立したままでいようとして用いる あらゆるひそかな言いぬけ「自己欺瞞、夢への逃避、まやかしの理想、想像の中で過去や未来に踏み入ること など)が、そのあらわれである。 シモーヌ・ヴェイユは、次のような言葉で救いについての問いを放っている。「わたしたちのうちにあって、重力 にも似たものから、どうしてまぬがれればよいのか。」 ただ、恩寵によってである。神は、私たちのもとへ来よう として、時間と空間の無限の厚みをのり越える。その恩寵によって、この世を動かしている必然と偶然との盲目 のたわむれの中で何ひとつ変化するわけではない。恩寵は、水のしずくがその構造を変えることなしに地層の 中へとしみこんで行くようにわたしたちのたましいの中へとはりこむ。そして、そこで、わたしたちがふたたび神と なることに同意するまで、黙って待つ。重力が創造の法則であるとすれば、恩寵の働きは、わたしたちを〈脱 創造〉させることである。神は、わたしたちが何ものかでありうるために、愛によってもはや、自分がすべてでは なくなることに同意した。こんどは、わたしたちが、神がふたたびすべてとなるように、愛によって自分たちが無 となることに同意しなければならない。すなわち、それは、わたしたちの中の〈われ〉、「罪と誤りによって映し出 され、神の光をはばむ影、わたしたちが存在ととりちがえる影」をうち砕くことである。このまったき謙遜、無と なることへの無条件の同意を除いては、ありとあらゆる形の英雄的行為、自己犠牲は、あいかわらず重力と 虚偽に従っているのである。「ささげもの。この〈わたし〉以外の何ものもささげることはできない。そして、世に ささげものといわれているものはすべて、この〈わたし〉の代わりのものの上に貼りつけられたレッテル以外の 何ものでもない。」 〈われ〉を死なしめるためには、人生のあらゆる災厄に、裸のまま、なんの防備もなしに立ち向かい、真空や 狂気の不安を受け入れ、不幸に際して決してつぎないを求めず、何よりも自分の内部で想像力の働き出すのを 止めなければならない。「恩寵がはいってこられそうな割れ目をふさごうと、たえず働きかけている」想像力の 働き出すのを止めなければならない。なぜなら、〈われ〉とは、つねに消えようとする現在のまわりに過去と未来 とが凝結したものにほかならないからである。思い出や希望は、想像上での自己高揚(わたしはこうだった・・・、 わたしはこうなるだろう・・・など)に際限のない余地を与えようとするもので、不幸の有益な効果を無にしてしま う。だが、現在のこの瞬間に忠実であることによって、人間はまさに無にまで小さくされ、永遠へといたる門も そこにひらかれる。  |
![]()
マルセイユのシモーヌ・ヴェイユ 1941年(32才)
2015年12月22日(冬至)の夜明け(6時01分〜7時36分)の光景です。
|

Revival Begins With Oneself | ubfriends.org
