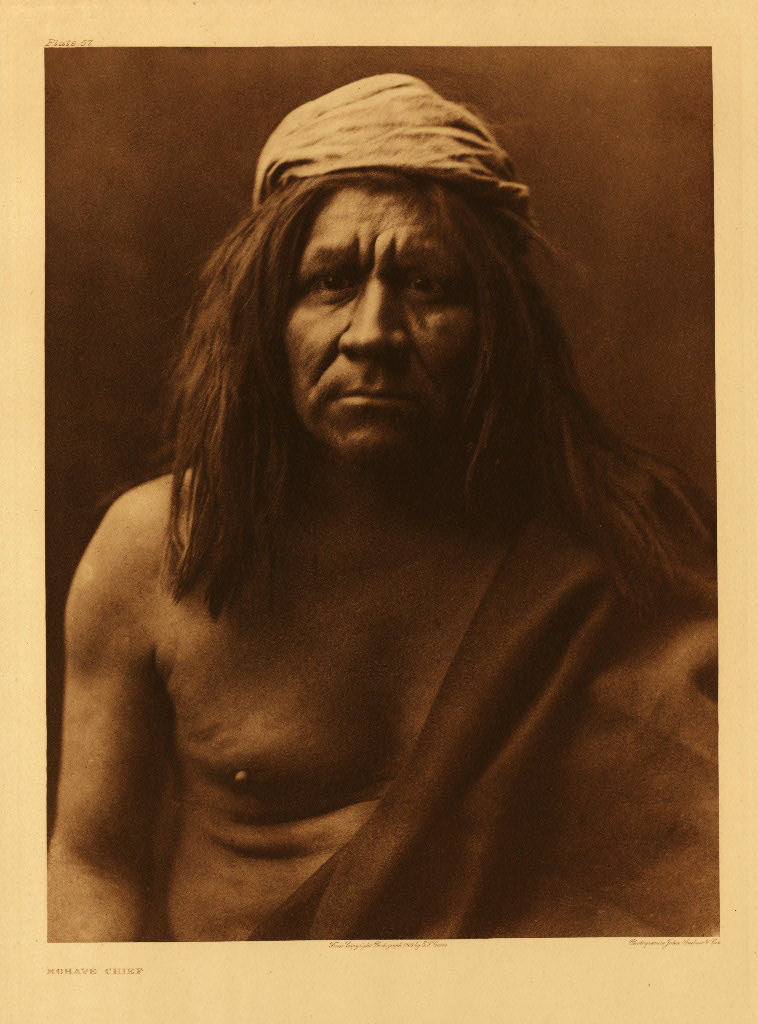
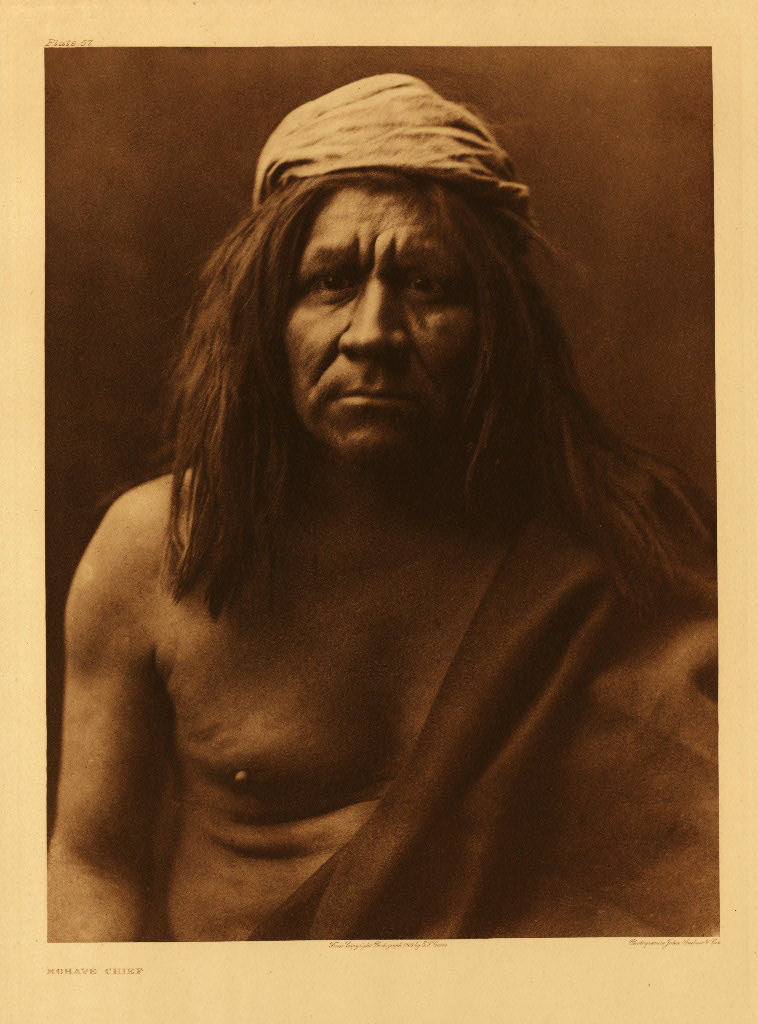
Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)
![]()
|
「写真集 世界の先住民族 危機にたつ人びと」明石書店より引用
ハロルドは書いている。「われわれは大量虐殺の傷を負っている。子どもたちは その傷を受け継いでいる。解決のできない痛みや悲しみは、世代から世代へと 受け継がれていく。これは絶望の源であり、われわれの伝統的な生活への侮辱 であるばかりか、喪失という深い井戸でもある。この痛みを捨て去るために、わ れわれは酒で自分たちを麻痺させてきた。われわれは、生活を蝕んでいるこの 悪循環を断ち切らねばならない。われわれは酔いから目を覚まさなければなら ない。そしてアルコール乱用の下にある傷ついたものを癒してやらなければなら ない。精神をやむ病気で苦しんでいる多くの先住民がいる。あたかも魂を失って しまったかのように」。ハロルドはアルコール依存症、精神の病気の治療は魂の 治療でもあるにちがいないと思った。そして魂の問題として、かれは人びとが自由 にかつ安心して暮らしていた昔のユピックの世界を眺めてみた。古くて完結してい た、ユピックの生活様式では、ユウヤラークは「人間の生き方」であった。文字に はなっていなかったけれども、この考え方は人間の生活のありとあらゆる部分を 支配し、人間同士の、そしてすべての生き物との間にある正しい行動を定めてい た。そのころには、すべてのものが魂をもっており、すべての出来事が精神的な 根拠をもっていた。アンガルクーク(Angalkuq)と呼ばれたメディスン・マンは精 神世界を理解し、人間の生き方の解釈をしていた。メディスン・マンは仲間の問題 の理解と解決方法を求めて、月や、海の底、地球の内部に行ったことがあるとい われている。ベーリング海の海岸線に白人がたどり着いて以来、これらすべてが 変わり始めた。最初、ユピックは、植民地化しようとしていたロシア人を退け、自分 たちの宗教を捨て改宗することを勧めていたキリスト教の宣教師に抵抗した。しか し、かれらの意志はすぐに覆された。貿易商、捕鯨人、それに宣教師たちは、ユ ピックの人たちが免疫をもたない病疫をもち運んできた。1900年ノームに端を 発したインフルエンザが野火のようにアラスカ中に広がっていった。バクテリアや ウイルスのことなどまったく知らなかったユピックの長老たちは、病気を精神の弱 まったせいとした。「混乱、苦しみそして絶望は想像できない」と大量虐殺について ハロルドは書いている。「子どもたちは、父親、母親、兄弟、姉妹が病気になってい くのをなすすべもなく見ていた。まずある家族が嘔吐し、熱を出して震え始める。そ して次から次へとうつっていく。メディスン・マンのアンガルクークの努力は無駄で あった。多くの家族が死んでいった。村全体が姿を消した。あちらこちらでほんの わずかの子どもたや大人が助かっただろう。しかし、アンガルクークでさえ病気に なり、絶望のうちに死んでいった。そしてかれらとともに、エスキモーの昔からの精 神世界であったユウヤラークの大半が姿を消した。生き残ったものたちは戸惑い 恐れながら眼を開いた。死体で埋まった戦場に残された兵士のように、かれらは 衝撃で貝のように身を堅くしていた。かれらは悲しみ、生き残ったことに罪を感じ ていた」。ハロルドは、大量虐殺の生存者は、外傷性後遺症症候群で苦しんでい ることに気がついたのである。
自分たちの文化が突然、外部からの衝撃によって死に絶えたことで、孤児となって しまった人びとは、近代という時代に生きるユピックの第一世代になってしまった。 ひ弱になり混乱した状況の中で、かれらは痛みを抑え、否定という沈黙の中に自分 たちの古い文化を埋めてしまわねばならなかった。ユピックの親は子どもたちに教 えることをやめ、宣教会や学校の教師に子どもたちを手渡してしまった。かれらは、 子どもたちが固有の言語を話すと、せっけんでもって子どもたちの口を洗ったので ある。訳がわからなくなり、脆弱になってしまったため、生き残ったユピックは、新し くやってきた人びとに自分たちの生活を譲ったのである。伝統的な踊りや宴会は 姿を消した。太鼓は投げ捨てられたり、人目につかないように隠されてしまった。 親は自分自身を恥じていた上に、それを子どもたちにも伝えたので、こうしたこと を甘んじて受け入れたのである。ハロルドは言う。「大量虐殺の生存者にとって、 逃避は不可欠となった。かれらは酒を飲み、麻薬に手を出した。衝撃的な経験を 押し殺すためには、幻覚や魂の中にそれを入れこまねばならない。そうするとい ずれそれが悪化し、生活を脅かし始める。彼らの子どもは絶望、寂しさ、混乱そ して罪を受け継いだ。なぜそうなのかを知らないまま、自分たちの仲間を風変わ りで、無知で笑いものであるとみなすようになり、軽蔑し始めた。何世代にもわた って押し殺した怒り、混乱そして劣等感と無力感は、いまや本当に若い人たちに も染み込んでしまっている。かれらはユピックであることを恥じているし、白人の ようになろうとしている。かれらは文化、言語、精神的信仰、歌、踊り、宴会、土 地、独立心、そして自己認識などすべてのことをあきらめてしまっている。かれ らは内に閉じこもり、深い沈黙の中で耐えられない感情を包み込んでいる」。 「われわれはめまいの中で何百年とさまよってきた。否定と沈黙の苦しみは われわれの特徴となってしまっている。これが、犠牲の上に犠牲を築きなが ら、ずっと最後まで続くわれわれの生活様式なのだろうか。あるいはわれわ れはより健全な生活様式、つまりいまの世界にふさわしいユウヤラークを復 活させるのだろうか」。
100年におよぶ苦しみの傷は一晩で治るものではない。治癒するには、時間は もちろんのこと、かつてユピックの人びとの印であった独立心と自立を主唱しな がら自分でそうしようとする機会が必要である。ハロルドが言うように、「先住民 は魂を取り戻さねばならない。そして自己認識と精神性を取り戻すためには、 われわれは危険を冒し、人生の困難と直面しなければならない。傷を取り除か ねばならない。そのとき初めて、母親たちは息子たちを真正面に見ることができ るし、息子たちは初めて父親を直視するだろう。そしてわれわれは再び家という ものに戻ることができるし、そこでは家族と村がよみがえるのである。そうでなけ れば、われわれは民族としての存続がなくなってしまうだろう。これは生存をかけ た問題なのである」。「いまのわれわれの生活は普通ではなく、まるで檻に入れ られた動物のそれである」とハロルドは言っている。「生まれたときから死ぬまで、 アラスカ先住民は政府の庇護のもとにおかれている。われわれは食べ物も、住宅 もそして身の回りの世話までも与えられているが、決して自由ではない。同化し 続けるために、先住民は自分以外のものになろうとしながら、結局は自分を殺し ているのである。この苦しみに終止符を打つ唯一の方法は、村や部族が自分た ちの仲間の衣食住と管理の責任を主張することである。われわれは“主権”の 意味を再度確立しなければならないのである」。
を参照されたし。 |
|
アラスカ・ユピック族(アメリカ合衆国)に地理的に近いイヌイット(カナダ)の関連記事です。
独立した立法、行政、司法権が与えられる準州は実質的に立国としての意味を持つ。日本 の5倍の広大な大地にはイヌイットと呼ばれる先住民が85%いるが、先住民族に共通して 見られる自己基盤喪失による自殺やアルコール・薬物依存症が、カナダの平均より3倍多く 性犯罪も7倍多い。このような悲惨な現実の中にも彼らは自らの民族の政治的・精神的自立 を目指して、30年近くも粘り強くカナダ政府と交渉してきた。初代の首相は34歳の先住民で あり、彼自身も高校時代酒を盗み禁固刑に服し兄が自殺した経験を持つが、その後立ち直 りヌナブット創設運動に加わってきた。世界中の多くの先住民が政治的・経済的・社会的そ して精神的に虐げられている現在において、この決定は多くの勇気と希望を与えるだろう。 (本文は朝日新聞1999年3月31日夕刊に書かれた記事を参考にしています)
|
 「神を待ちのぞむ」シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保・杉山毅・訳 勁草書房 より以下抜粋引用 はないと保証されていることである。あからさまな宗教的信仰の外側にあっても、ひとりの人間が、 真理を把握することのできる能力を一そう身につけたいという一ずなねがいをもって、注意力を こらして努力するならば、その度ごとに、たとえその努力が目に見えるどんな果実も産み出さな かったとしても、その能力は一そう大きくなっていくのである。エスキモーのある物語の中に、こん なふうにして光ができたのだと説いているものがある。「からすは、夜がいつまでもつづいて、食物 を見つけることができないので、光がほしいと思った。そこで、大地は照らし出された。」 もし本当 にねがいがあるならば、そして、そのねがいの対象が、本当に光であるならば、光へのねがいが 光を産むのである。注意力をこらしての努力があるところに、まさに本当のねがいがある。それ 以外の動機が何一つなければ、まさに光そのものが、ねがい求められているのである。注意力 をこらしての努力が、何年もの間、表面上はみのりのないままに終っているようにみえても、やが ていつの日か、この努力に正確に即応した光があらわれて、たましいを満たすのである。どのよう な努力でも、世界中の何ものも奪い去ることができない宝物に、なおいくらかの黄金をつけ加え るものである。  |
![]()
2016年4月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) アイスランド南部にあるセリャラントスフォス(滝)とオーロラ (写真1枚目はNASAより、それ以外は他のサイトより引用) 1枚目の写真、幻想絵画かなと思いましたが、滝の水しぶきで何度もレンズを拭きながら撮られた写真です。 オーロラのやや右側に明るく輝く星が織姫星(ベガ)、左側に輝く星が彦星(アルタイル)です。 ですから天の川が位置するところにオーロラが出現したんですね。 北欧では死者と生者の世界を結びつけているのがオーロラであり、イヌイットの伝説ではこの世で善い行いを した人はオーロラの世界へ行けると言われているようです。 死後の世界を意識することによって、初めて生の意味が問われてきたのかも知れません。 それはギリシャ哲学(ソクラテスやプラトンなど)よりも遥か太古の世界、ひょっとしたら私たち現生人類よりも 前の人類にも芽生えた問いかけのように感じています。 オーロラなど天球に映し出される様々な現象(太陽、月、天の川、星、彗星など)を通して、人類は異なる次元の 世界を意識し死後の世界とのつながりを感じてきた。 ただ、精神世界の本に良く見られる「光の国(星)からのメッセージ」的な言葉に違和感を感じているのも事実です。 自分自身の足元の大地にしっかりと根をはらずに、ただ空中を漂っている、或いは彷徨っているような感じしか 受けないからです。 アインシュタインの相対性理論、まだ理解は出来ていませんが、それぞれの立場によって時間や空間が変わる、 それは他者の立場(社会的・文化的・経済的)を想像することと同じ意味を持っているのではと感じます。 もし、相対性理論なしでカーナビを設定すると現在地よりも11キロずれたところを指してしまいますが、それが 人間同士や他の生命間のなかで実際に起こっている。 自分自身の根をはらずに、他者のことを想像することなど出来ないのではないか、その意味で私も大地に根を はっていないのでしょう。 一度でいいからオーロラを見てみたいです。 |
