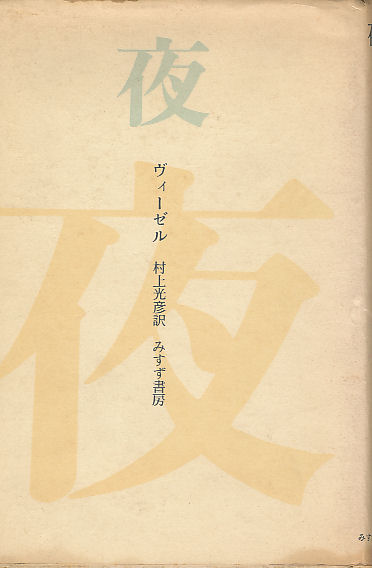
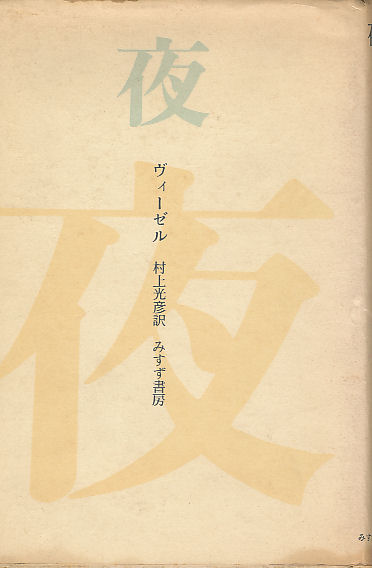
![]() 「夜」
「夜」
ヴィーゼル著 村上光彦訳 みすず書房 より引用
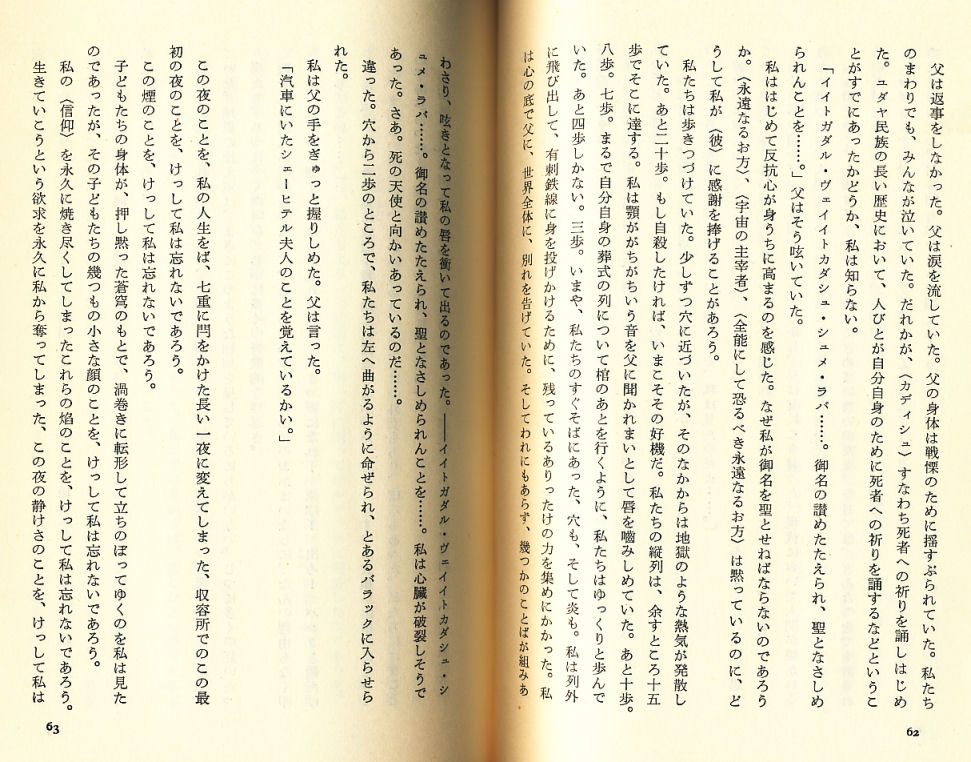
|
|
![]()
 下から2段目、左から7番目がエリ・ヴィーゼル ヴィーゼルは1944年、15歳の時にアウシュヴィッツ収容所に送られる。 |
|
自分の妹と母親とが、ほかの幾千もの人たちのあとを受けていまにも投げこまれようと しているその炉のなかから、黒煙の環がもくもくと湧き上がってきて、つぎつぎと空に ひろがっては崩れてゆくのを、彼の目は見つめていたのであるが、そのあいだに彼の 内部でどのようなことが生じていたか想像してみよう。「この夜のことを、私の人生を ば、七重に閂をかけた長い一夜に変えてしまった。収容所でのこの最初の夜のこと を、けっして忘れないであろう。この煙のことを、けっして私は忘れないであろう。子ど もたちの身体が、押し黙った蒼穹のもとで、渦巻きに転形して立ちのぼってゆくのを私 は見たのであったが、その子どもたちの幾つもの小さな顔のことを、けっして私は忘れ ないであろう。生きていこうという欲求を永久に私から奪ってしまった、この夜の静けさ のことを、けっして私は忘れないであろう。私の神と私の魂を殺害したこれらの瞬間の ことを、また砂漠の相貌を帯びた夜ごとの私の夢のことを、けっして私は忘れないであ ろう。たとえ私が神自身と同じく永遠に生き長らえるべき刑に処せられようとも、その ことを、けっして私は忘れないであろう。けっして。」
そのときのことを想像してみて、私がこの若いイスラエル人に会ったとたんに好きに なったのはいったい彼のどういうところなのか、ということが私にはわかった。それは、 復活しながら、しかもあいかわらず暗い岸辺・・・・彼は、辱められた累々たる屍体に躓 きながら、そのあたりを彷徨したのである・・・・の虜囚たりつづけているラザロのまな ざしにあったのである。彼にとって、神は死んだというニーチェの叫び声は、ほとんど 身体にじかに応える現実性を表わすものであった。すなわち、あらゆる偶像のうちで ももっとも貪欲な〈人種〉という偶像の要求により、人間を焼いて捧げる全燔祭が行な われたとき、この子どもたちの見ている前で、愛、柔和、慰めの神は、アブラハム、 イサク、ヤコブの神は、その祭壇から立ちのぼる煙のなかへと永久に姿を消し去った のである。そして、なんと多くの敬虔なユダヤ人の心のうちで、この死が成しとげられ ずにはいられなかったことか。あの恐ろしい日々のうちでも恐ろしい日、この子どもは もうひとりの子ども・・・・彼が言うには、不幸の天使のような顔をしていたとのことであ る・・・・にたいする絞首刑(そう、文字どおりの!)に立ち会ったのであるが、彼はその 日自分のうしろでだれかがこう言って呻くのを聞いた。「『神はどこだ。どこにおられるの だ。いったい、神はどこにおられるのだ。』そして、私の心のなかで、ある声がその男に こう答えていた。『どこだって? ここにおられる・・・・ここに、この絞首台に吊るされて おられる。』」
|
ごとに襲いかかってくるかもしれないのに、片時の間でも警戒心を解いてしまうのは危険なこ とではないだろうか。 そんなふうに考えていたとき、ヴァイオリンの音色が聞こえた。死者たちが生者たちのうえに 積み重なっている。この暗いバラックのなかで、ヴァイオリンの音色。ここで、自分自身の墓の の縁で、ヴァイオリンを弾く狂人はどこのだれだろうか。それとも、幻覚にすぎないのだろうか。 ユリエクに違いない。彼はベートーヴェンの協奏曲の一節を弾いていた。こんなに清らかな音 色は聞いたことは、いまだかつてなかった。このような静寂のなかで。彼は身体を抜き出すこ とに、私の気づかぬうちに私の身体の下から抜け出すことに、どのようにして成功したのであ ろうか。 まっくらであった。聞こえるのはただ、このヴァイオリンのみであった。あたかもユリエクの魂 が弓の役を果たしているかのようであった。彼はわれとわが命を奏でていた。彼の命のすべ てが弦のうえを滑ってゆくのであった。彼の失われた希望のかずかず。彼の黒焦げになった 過去、彼の火の消えた未来。彼は、もう二度と奏でることのないものを奏でていたのである。 私はけっしてユリエクを忘れることができないであろう。頓死者と死者とから成るこの聴衆に 聞かせたこのコンサートを、私はどうして忘れることができようか! 今日でもまだ、ベートー ヴェンの曲を聞くときには、私の目は閉ざされ、そして頓死者の聴衆に別れを告げている。 あのポーランド出身の仲間の蒼ざめて悲しげな顔が、暗がりのなかから浮かびあがってくる のである。 彼がどのくらいのあいだ演奏したか、私は知らない。眠りが私にうち勝った。目覚めたとき、 明けがたの光に照らされて、ユリエクがちぢこまって死んでいるのを、私は目のまえで見た のである。彼のかたわらには、踏みにじられ、圧し潰された彼のヴァイオリンが、場違いで しかも心を激しく揺さぶる、ちっぽけな死体となって横たわっていた。 |
それを貨車のなかに投げ込んだ。みんながとびかかった。何十人もの飢えた者が幾片かの パン屑のために殺しあったのである。ドイツの労働者たちはこの光景をひどく面白がった。 数年後、私はアデンで同種の光景を目撃した。私たちの乗っていた船の乗客が、《土人》 に硬貨を投げ与えて面白がっていたのである。《土人》たちは、潜ってお金を取ってくるの であった。貴族らしい風采をしたひとりのパリ婦人が、この遊びをたいへん愉快がってい た。私は不意に、二人の子どもが死にそうな殴りあいをしており、一方が相手の咽喉を締 めつけようとしているのに気付いた。そこで私は、その貴婦人に嘆願した。「お願いです。 もう小銭を投げないでください!」 「なぜいけないんですか」と、彼女は言った。「私は慈善 をするのが好きなのです・・・。」 パンが落ちてきた貨車のなかでは、まったくの闘いが始まっていた。たがいにとびつき、 踏みつけあい、引き裂きあい、噛みあったのである。目に獣のような憎悪を宿して、鎖か ら解き放たれた猛獣と化していた。途方もない生命力が、彼らを虜にし、彼らの歯と爪を 研ぎすましたのであった。列車に沿って、一群の労働者と野次馬とが集まっていた。彼ら はきっと、こんな積み荷を載せた列車をまだ一度も見たことがなかったのであろう。まも なく、あちこちからパン片が貨車のなかに降ってきた。見物人は、これらの骸骨じみた 人間が一口のパンをうるために殺しあうのを眺めていた。 一片、私たちの貨車にとび込んだ。私は身動きするまいと決心した。それに私は、鎖 から解き放たれた、この幾十人もの連中と闘うだけの力が自分にはないのを知って いた! 私は四つん這いになってゆく老人を、私からさして離れていないあたりに見 かけた。彼はいま、争いのなかから抜け出て来たのである。彼は片手を心臓のあた りに押しあてた。私ははじめ、胸を殴られたためかと思った。それから、わかった・・・ 彼は上着の下に一片のパンを隠していたのである。なみなみならぬ素早さで、彼はそ のパンをとり出し、それを口に持って行った。目が輝いた。しかめつらにも似た微笑 が、彼の死人のような顔を照らした。そして、たちまちにして消えた。人影が彼のそば にふと伸びてきたのである。そしてその影は彼にとびかかった。殴りつけられ、殴打 のでいで酔ったようになって、その老人はこう叫んだ。 「メイール、私のかわいいメイール! 私がわからないのかい。お父さんだよ・・・。 そんなことをして、痛いよ・・・。おまえはお父さんを殺すのかい・・・。パンがあるよ・・・ おまえの分も・・・おまえの分も・・・。」 彼はくずれ落ちた。まだ、小さなひとかけらを後生大事に握りしめていた。彼はそれ を、自分の口へ持って行こうとした。しかし、相手が彼にとびかかり、それをとりあげ た。老人はまだなにかを呟き、喘ぎ声を発し、そして死んだ。だれも気に留めもしな かった。息子が彼の身体を探り、パン片を取りだし、むさぼり食い始めた。彼は、あ まり食べることができなかった。二人の男が彼を見ていて、跳びかかったのである。 ほかの連中もこれに加わった。彼らがどいたあと、私のそばには二人の死者が並ん でいた。・・・父と息子と。私は15歳であった。 |
|
Elie Wiesel(1928〜)
|
|
2012年1月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。
|
