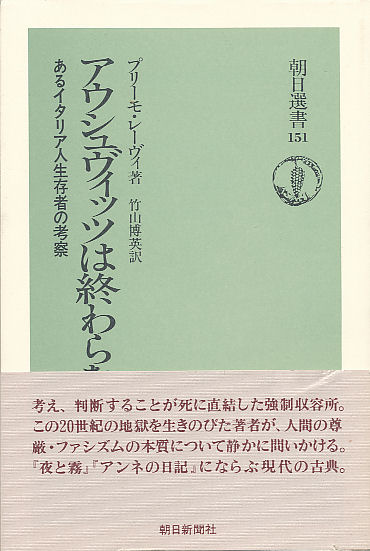
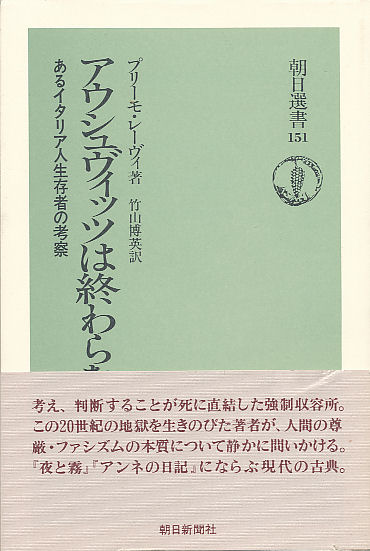
![]() 「「アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察」
「「アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察」
プリーモ・レーヴィ著 竹山博英訳 朝日選書 より引用
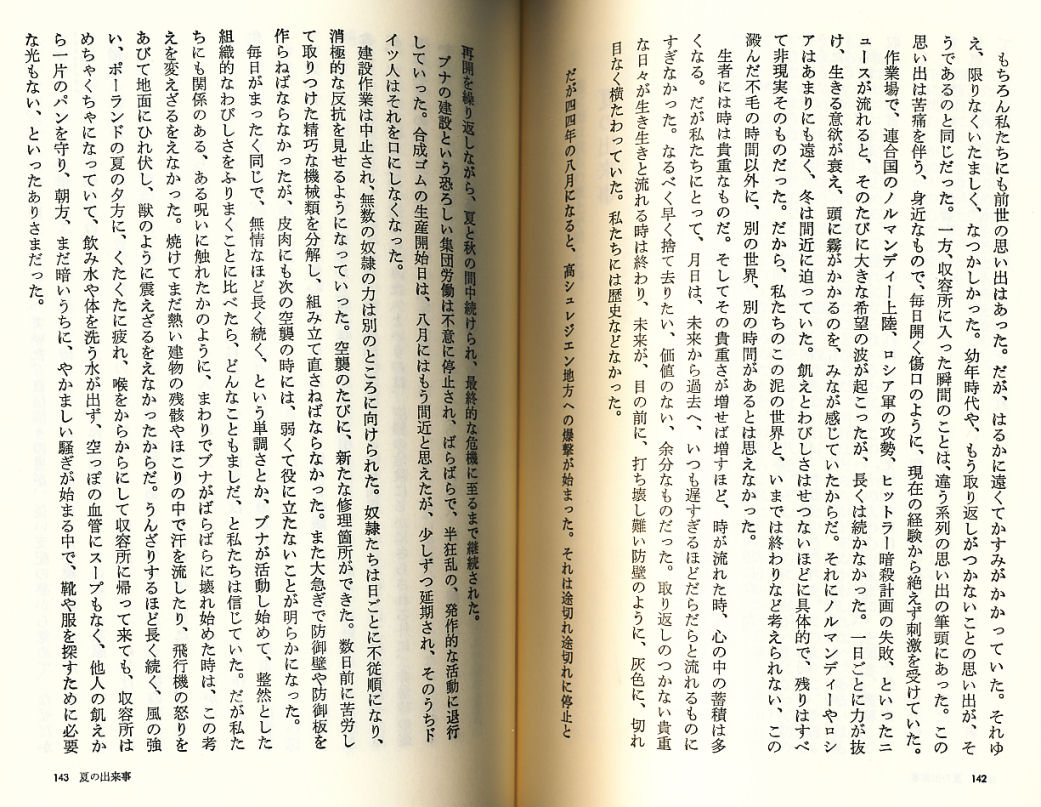
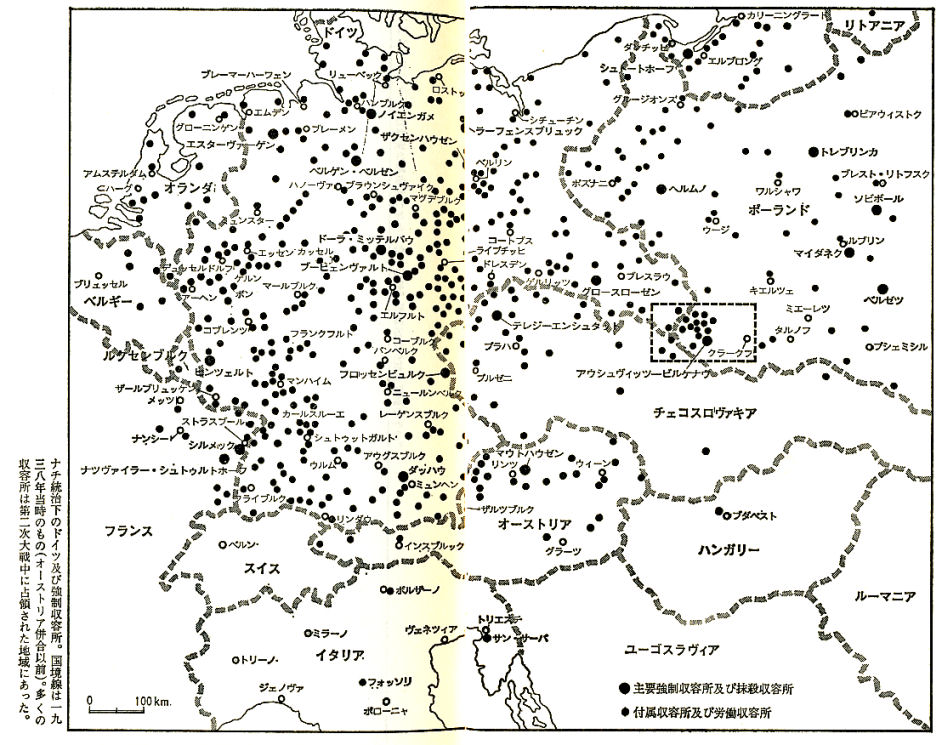
|
|
![]()

Primo Levi - a photo on Flickriver
Primo Michele Levi (July 31 1919〜 April 11 1987)
|
|
|
アウシュヴィッツの収容所の生活を描いた作品では、フランクルの「夜と霧」、エリ・ヴィーゼルの 「夜」などが、日本の読者にはなじみの深いことだろう。本書「アウシュヴィッツは終わらない」も、 こうした作品に続いて、アウシュヴィッツについての理解を深める役割を果たせるのではないか と思う。本書の特色は、まず、収容所の生活をきめ細かく具体的に描いたこと、収容所内の人間 模様を鮮やかに浮かび上がらせたことにある。だが何よりも、ものを考えることが死につながると いう、人間にとっての極限状態にあって、人間の魂がいかに破壊されてゆくかを、克明に、静か に描き出したことに、優れた点があるだろう。著者の抑制のきいた、簡潔で禁欲的な文体は、確 かに本書のドキュメントとしての価値を高めている。また著者の古典への造詣、特にダンテの 「神曲」を念頭に置いた叙述の進め方は、本書に「現代の地獄篇」たる趣を与え、作品の奥ゆき を深いものにしている。
だが著者が抑制のきいた静かな調子を選んだからといって、ファシズムに怒りを燃やしてはいな い、ということにはならない。これは巻末の「若い読者に答える」を一読すれば分かることだろう。 本書の刊行から30年後に書かれたこの解説で、著者は、本文の抑制のきいた調子を捨て、ファ シズムの蛮行を弾劾し、ファシズムの復活は決して許さないという固い決意を述べている。この 解説には、あくまでも理性に信頼を置こうとする著者の立場がはっきり見えていて、ヨーロッパの 主知的伝統を感じさせてくれる。著者は序文でこう述べている。「ファシズムはまだ死に絶えてい ない。虎視たんたんと復讐を狙っている。『この怪物を生み出した子宮はいまだ健在である』」と。 こうした言葉が、アウシュヴィッツという地獄を生き抜いた著者のような人物の口から出る時、その 重さははかり知れない。それは、むだな危惧だと言って笑いとばせないような、ずっしりとくる重さ である。
アウシュヴィッツの記録は、なぜか人の興味をひきつける。それは想像を絶する、おぞましい蛮行 への、好奇心のあらわれかもしれない。だがそれだけではないはずだ。おそらくアウシュヴィッツと いう現象に、人間の心の奥に潜む悪が顕在化していることを、みな無意識のうちに感じ取っている のだ。なぜいまアウシュヴィッツなのか、なぜすんだことをいまさらのようにむしかえすのか、という 問いには、私はこう答えたい。アウシュヴィッツという現象は、もう過去のものになった、ある邪悪 な体制が生み出した暴虐というだけにとどまらない、もっと一般的な、人間の心の奥にひそむ悪を も表わしている、と。アウシュヴィッツでなされた蛮行は、人をとまどわせ、判断力を停止させてしま うようなところがある。何百万人もの人間をガス室で殺し、焼却炉で焼き、死体の髪でじゅうたんを 織り、脂肪で石けんをつくったという事実を知る時、そのおぞましさは、人の通常の想像力を麻痺さ せ、判断力を停止させ、目の前に暗い淵を見るような思いだけを残す。この淵を飛び越すには、 想像力を途方もなく遠くまで飛翔させなければならない。だがそれは普通の人の飛翔力の限界を はるかに超えている。おそらく、こうした事実は、社会力学的に説明できるのだろう。だがそれと 並んで、人間の心の動き、人間の意識のありかたを解明する努力が必要だ、さもなければ、また 同じ誤りが繰り返されてしまう、という気がする。
|
|
序 若者たちに
旅 地獄の底で 通過儀礼 カー・ベー 私たちの夜 労働 良い一日 善悪の此岸 溺れるものと助かるもの 化学の実験 オデュッセウスの歌 夏の出来事 1944年10月 クラウシュ 研究所の三人 最後の一人 十日間の物語
若い読者に答える 注
訳者あとがき
|
|
2012年1月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。
|
