

「生きることと愛すること」 W・エヴァレット著 菅沼りょ・訳 講談社現代新書 1978年刊
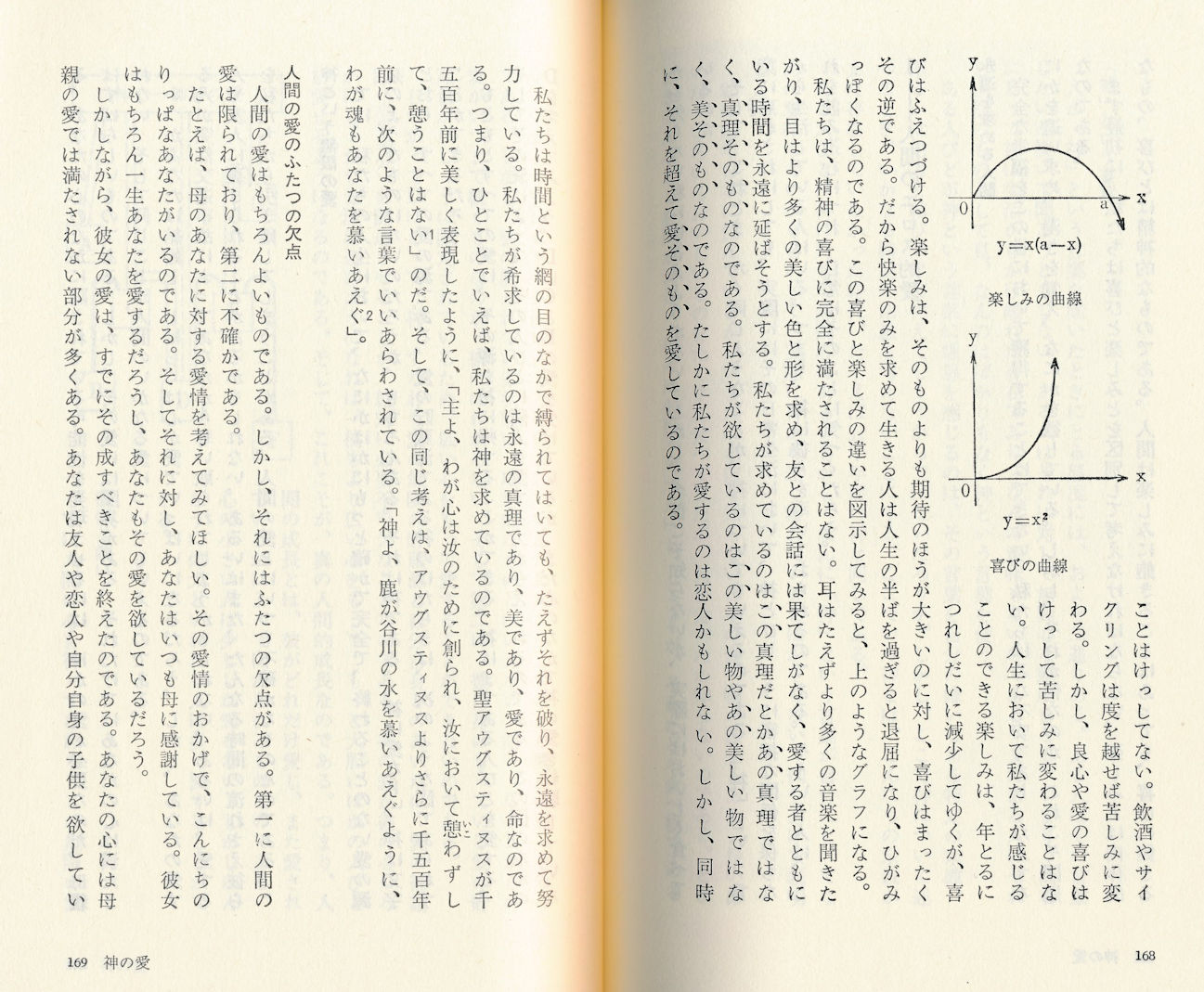
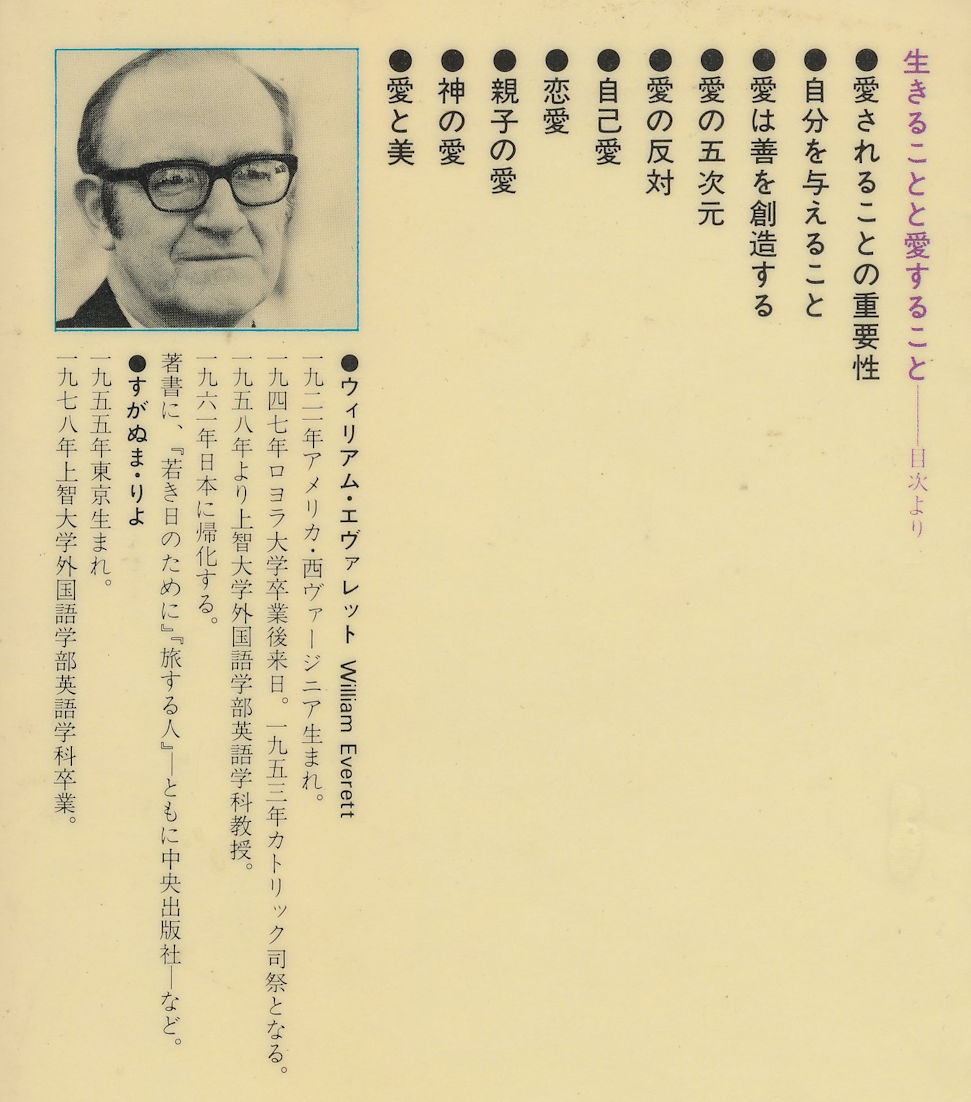
2017年6月30日投稿
![]()
小山信夫神父(イエズス会) 2004年10月13日、東京・練馬区の同会ロヨラハウスで急性肺炎のため逝去。83歳。 1921年米国生まれ。40年同会入会。 53年司祭叙階。神戸の六甲学院教師を経て、上智大学外国語学部英語学科教授を28年間務めた。 61年帰化し、ウイリアム・エベレットから改名。その後、京都の聖母女学院短期大学教授を6年間務め、 92年から東京で司牧活動に従事。 98年から2001年まで麹町教会助任司祭を務めた。1978年に出版した講義録『生きることと愛すること』 (講談社)は20万部を超えるベストセラーになった。 本書「生きることと愛すること」(1978年刊)より抜粋引用。 もっとも大きな欲望は、「なにかがほしい」という欲望であるといえるだろう。私たちは、この欲望を満たしてくれるものを よしとし、愛するという。これをプラトンは「エロスの愛」と呼んだ。 こんにちでは、「エロティック・ラブ」という言葉は男女間の性愛をさすようになったが、プラトンは、元来その言葉を自分 の欲望を満たしてくれるものに対する感情として、広義に用いていた。プラトンは「エロスの愛」を5段階に分けている。 もっとも初歩的な段階は、男女間の性的な愛であり、そこから新しい生命が生まれる。次の段階は、広く感覚的に美し いと感じるものに対する愛であり、第3段階は家庭や祖国に対する社会的な愛である。第4段階は、真理・知識・道徳を 追求する愛である。そしてもっとも高度なエロスの愛は、「美」(または善)そのものと一体になりたいという欲望であると いう。 このエロスの愛はプラトン哲学の中心的な原理となっている。彼は人間の美・善・自己完成への努力はみな、このエロス の愛によって説明しようとした。物質界において、石が引力によって無条件に地上に落下するように、人間はエロスの愛 の作用によって、不完全な自分を満たしてくれるものにひきよせられるのである。つまり、エロスとは、人間をよりすぐれ た人格にし、文化を進歩させ、美へ、そして完全へと駆りたてる原動力なのである。 も、てれくさかったり、見栄をはったりするからである。こんなことをしたら、人にばかにされるのではないか、笑われるの ではないかとか、人の思惑を気にしてしまう。しかし、思いきって実行してみると、しだいにそれが習慣となって、かえって 素直にいろいろな状況に対応できるようになるものである。逆に、相手を思いやれば思いやるほど、愛も深まるという ことも事実である。 サン=テグジュペリの「星の王子さま」が、自分の星に残してきた一輪のばらに対して抱いていた思いも、こうして生まれ たものではないだろうか。彼は地球でなん百というばらを見ていう。 「君たちは美しいけど、つまらない。君たちのために命を捨てる気にはなれないよ。そりゃ、なにも知らない人が通り かかったら、僕のばらも君たちとそっくりだっていうかもしれない。だけど、僕にとってあのばらは君たちなん百本よりも ずっとたいせつなんだ。だって、僕が水をかけた花なんだからね。覆いガラスをかけてやったんだからね。ついたてで 風にあたらないようにしてやったんだからね。ケムシを殺してやったんだからね。不平も聞いてやったし、自慢話も聞い てやったし、ときに黙りこくなっているときだって耳を傾けてやった花なんだからね。そのばらは『僕のばら』だから なんだ。」 もし、王子さまがこんなにばらのめんどうをみてやらなかったら、そのばらはけっして「彼の」たいせつなばらにならな かっただろう。一般的にいって、母親の子に対する愛情のほうが、子が母親に対する愛情よりも強いといわれるのは、 同じ理由によるのではないだろうか。 私たちは、ひとりひとり違った才能や個性をもっている。したがって、「自分の与え方」もひとりひとり異なっている。その 人にいちばんあったやり方で、自分を与えようとすればよい。ある人は重労働することによって愛そうとし、ある人は、 ピエロになって、みなを笑わせ楽しませることによって愛を表現する。ただ祈ることしかできない人もいるだろう。 しかし、それぞれが「自分にできること」をしながら、自分のもっているなにかを与えるのである。エマーソンのことばを 借りていえば、「指輪や宝石は贈り物ではなくて、贈り物がないときのいいわけである。ほんとうの贈り物たりうるのは、 自分自身の一部である。かくて、詩人は詩を、羊飼いは羊を、農夫は穀物を、鉱夫は宝石を、水夫はさんごと貝を、 画家は絵を、そして少女は手づくりのハンカチを贈るのである」。 「真に愛する人は、愛するときに、自分が心変わりすることなど考えない。これは、ほかの精神的な活動・・・たとえば、 価値の知覚や認識・・・のばあいと同様に、愛するときには相手の価値や本質に感情が向けられることを考えれば理解 できるだろう。一度2+2=4であるとわかれば、永久にそれを理解したのと同じである。『それだけですべてなのである』。 同様に、いったん愛の光のなかで他人を見、その人の本質を理解すれば、それですべてなのである。私はその真理に 従わなねばならないし、この愛に従わなければならない。私たちは真の愛を経験するやいなや、まるで『永遠の真理』を 認識したかのように、それを永遠に有効なものとして経験する。まったく同様に、愛が通常時において持続するかぎり、 それは必然的に『永遠の愛』として経験されるのだ。」 初期の著書「言語治療」において、フランクルは、ナチス政治犯捕虜収容所に入れられていたときに、妻に対して抱いた 感情について書いている。両親、兄弟および妻はみな収容所で死亡し、彼と妹だけが生き残ったのだった。 「愛は肉体的存在をはるかに超えるものである。愛のもっとも深い意味は、その人の精神的存在、内面の自己にある。 愛する人が実際に目の前にいようがいまいが、生存していようがいまいが、そんなことは重要ではなくなってくるので ある。私は妻が生存しているかどうか知らなかったし、それを知るすべもなかった。(収容所にいるあいだ、一通の手紙 も受け取らなかった)。しかし、それは問題ではなかったし、べつに知る必要もなかった。私の深い愛や思考、そして最愛 の人の映像には、なにものも手を触れることができなかったからである。もし、妻が亡くなったということを死っていたと しても、それによって、彼女の姿を思いうかべ、瞑想にふけることを妨げられなかっただろうし、彼女との精神的な対話 は生き生きとしたものであり、満足すべきものであったにちがいないと思う。『あなたの心に私を捺印のように押してくだ さい。愛は死と同じくらい強いものなので』。」 的にいって、人生には一定の型がある。人は若ければ若いほど自己愛に焦点を置き、老いてゆくにしたがって、比重を 隣人愛に移してゆくべきである。アルベルト・シュヴァイツァーはこのことを具体的にいいあらわしている。彼は30になる までは、自分を成長させるためにエネルギーを費やし、それ以後は人びとに貢献するように努力したいといっている。 「多くの人びとが私の周囲であれほど苦しんでいるのに、私がこのような幸福な生活を許されているのは不可解だった。 学校にいるときでも、私の同級生が粗末な家と、私たちグンズバッハの牧師館の子供たちの理想的な家を比較して、 なにかを感じざるをえなかった。大学で勉強して少々の成果を上げているときでも、この幸せを物質的・身体的理由の ために味わえない人びとのことが頭から離れなかった。 ある美しい夏の日の朝、グンズバッハで目をさますと、この幸せをこのまま受け入れてはいけない、という考えが おこった。この代償になにかを与えなくてはならない。小鳥たちが外でさえずっているあいだ、このことを考えながら、 起床する前に自分に次のことを納得させた。つまり、30までは科学と芸術のために生き、それ以後は直接人間に尽くす ために自分を捧げようと決心したのである。自分にとって、次のイエスのことばにどのような暗示が隠されているのか 考えてみた。『汝の生命を我に捧げる者は、それを見いだすだろう』。そしていま、その答えを見つけたのである。その とき、私は外面的にだけではなく、内面的にも幸福になったのである。」 たいていの人にとっては、30歳というよりも、結婚が境界線となる。独身でいるときは、当然自己愛がもっとも重要である。 しかし、結婚後は他人(配偶者・子供・社会一般)が私たちの生活の中心でなければならない。 実際には、自己愛と隣人愛とは、互いに密接に関係しているために、区別することがむずかしい。表面的に見れば、 シュヴァイツァーが医学を修めていたときは自己愛を満たしていたように見えるが、同時に隣人に尽くしていたともいえ よう。それは、人に尽くすための準備だったからである。だから、もし彼が死んで、アフリカに行かなかったとしても、彼は 人道的な愛を実践したといえよう。 ふつう、私たちは、彼がアフリカで人びとのために働いていたときに隣人愛を実践していたのだと考える。しかし、よく考え てみると、そのときこそ、彼が自分をもっとも愛していたことがわかる。なぜなら、神が望んだ彼の人格の完成への道を、 彼が歩んでいたからである。 自己を愛するとは、神を愛し、隣人を愛することである。自分を愛さない人は、神も隣人も愛することができない。閉じた 戸のかげでひとりで酒に酔っても、自分ひとりが傷つくだけですむ、と思うかもしれないが、そうではない。私たちはみな、 密接に結ばれており、自分を傷つけることは他人をも傷つけることになる。それを考えれば、ますます真の自己愛を達成 しなければという思いを新たにすることができるだろう。私は、人により多く与えるために、自分をより多く愛さねばなら ない。 いる。彼女は知恵遅れの子供をもっていた。 「私は多くのことを娘から学んだ。とくに娘は私に忍耐することを教えてくれた。私の家族は、動作ののろい人を黙って 見ていられない性格だった。そして私も、鈍感な人に対して我慢できないというこの性格をすっかり受けついでいた。そこ へ、どういうわけか精神薄弱の娘を授かったのである。それからは、私は苦しい道を歩まねばならなかった。しかし、その あいだに、人の精神はすべて尊敬に値するということを知ったのだった。すべての人は人間として平等であり、人間として 同じ権利をもっているということを、はっきりと教えてくれたのは、ほかならぬ私の娘だった。もしこのような機会に恵まれ なかったとしたら、私は自分より能力のない人間に我慢できない傲慢な態度をもちつづけていたにちがいない。娘は私に ほんとうの人間の意味を教えてくれたのであった。」 パール・バックは精神薄弱の娘から、世界じゅうのだれよりも多くのことを学んだのかもしれない。謙遜な人は、いろいろ な人から学べることができるのである。 母親とはよく忘れられる存在である。たしかに個人的には私たちはみな、母に感謝している。しかし、社会においては 母の日がもうけられているにすぎない。世間はベートーヴェン、エル・グレコ、ダンテをほめたたえるが、だれが彼らの 母のことについて語るだろうか。彼らは偉大な芸術家として高く評価されているが、彼らを創造した人たちについては どうだろうか。立派な絵画を制作するよりも、偉大な芸術家をつくりだすことのほうが、もっとすばらしいことではないだろ うか。これはよく見落とされている点である。 しかし、忘れられていないひとりの母親がいる。それはキリストの母マリアである。彼女にはこれまで、多大な尊敬が払わ れてきた。「聖書」はマリアについて多くは記していないが、キリストは母と30年前後暮らしていたのだから、母の影響は 絶大なものであっただろうと推察される。私たちから見ても、キリストの愛の理論と実践は、母によって教えられたと考え ざるをえない。よって、マリアが尊重され、すべての母のモデルとしてあがめられても不思議ではない。 みな、おのおのの人生を、その直線の上を行ったり来たりしながら生きている。神を愛することにより、その人は中心へと 向かい、必然的に、神とすべての人間に近づく。つまり、もし隣人を愛そうと思うならば、その唯一の方法は、自分の直線 の上を中心にむかって進むことである。しかし、そうすることにより、たんにその隣人のみならず、神にも近づくことになる のである。 この考えは、テイヤール・ド・シャルダンの思想の根本にあるものである。 「収斂(しゅうれん)性の構造をもつ宇宙のなかにおいて、ひとつの要素がほかの隣接する要素に近づくための唯一の 方法は、その円錐(えんすい)形を縮めることにある。つまり、自分を含む世界の層全体を、その頂点へと引き寄せること によってである。このような状況においては、いかなる人も神に近づかずして他人を愛することはできず、その逆もしかり。 このことは私たちもよく知っている。しかし、あまり知られていないのは、神、あるじは隣人を愛すれば、かならず地上に おいて精神の統合が促進されるのだということである。なぜなら、私たちを互いに近づけ、同時にまた神へと高めてくれる ものは、この統合の促進なのだから。したがって、私たちは愛するからこそ、そしてもっと愛するために、この世のあらゆる 苦闘、不安、熱望、愛情を喜んで分かちあうのである。それらが向上と統合の原理を含んでいるかぎり。」 デンマークの実存主義哲学者キェルケゴールも同じ点を強調している。 「精神的な愛は、ほかのすべての愛の表現の根底に、そしてなかになければならない。・・・(真の)愛の目的はその愛の 対象を神へと導くことにある。他人を愛するということは、その人が神を愛するのを助けることなのである。そして、他人に 愛されるということは、神を愛するよう助けてもらうことなのである。愛している人を神に導く助けにならないような愛は、 愛するという人間の概念にとどまるのである。 (中略) 「神の存在を感じる」ということは、次の例によって説明できるかもしれない。子供が、家にひとりで留守番をしているのと、 隣の部屋で母親が編み物をしていることを知りながら、自分の部屋でひとりでいるのとはまったく違う。そのとき、母のこと を意識して考えているわけではない。しかし、もし彼女が呼んで、はさみはどこか、と尋ねたとしても子供は驚かないだろう。 無意識のうちに、母がそこにいたことを知っていたからである。神の存在もそれに似ている。事実、神はいつでも、どこに でもいる。しかし、特別なばあいをのぞいて、自然や他人や私たち自身の内における神の存在が、私たちの意識のレベル にまでのぼってくることはない。 ほとんどの人は、主として自分の魂の外面的な部分において生きる傾向がある。私たちはみな、もっと祈りと自己反省に 時間をさき、私たち自身の内において、もっと神と親密に交わるようにしたいものである。時間がなくても、いつでも私たち の心の聖堂にはいり、神に会うことはできる。たとえば、中央線や山の手線の満員電車のなかでも・・・。 神はどこにおられるのか。事物の奥深くにおられる。神は「万物の中枢」なのである。 |
