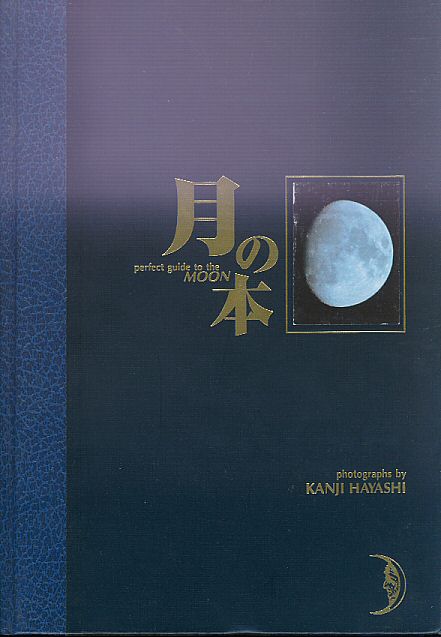
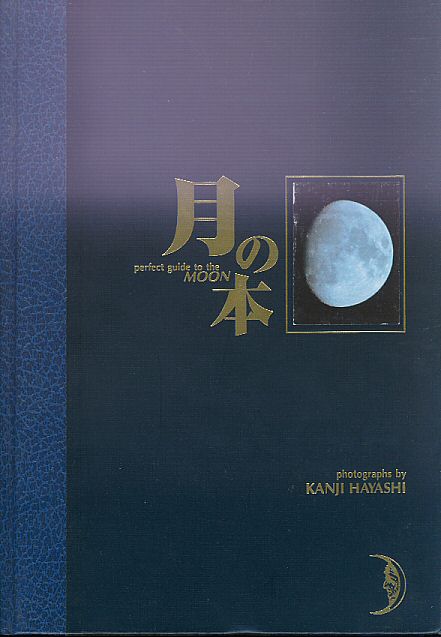
![]() 「月の本」
「月の本」
林完次著 光琳社出版 より引用
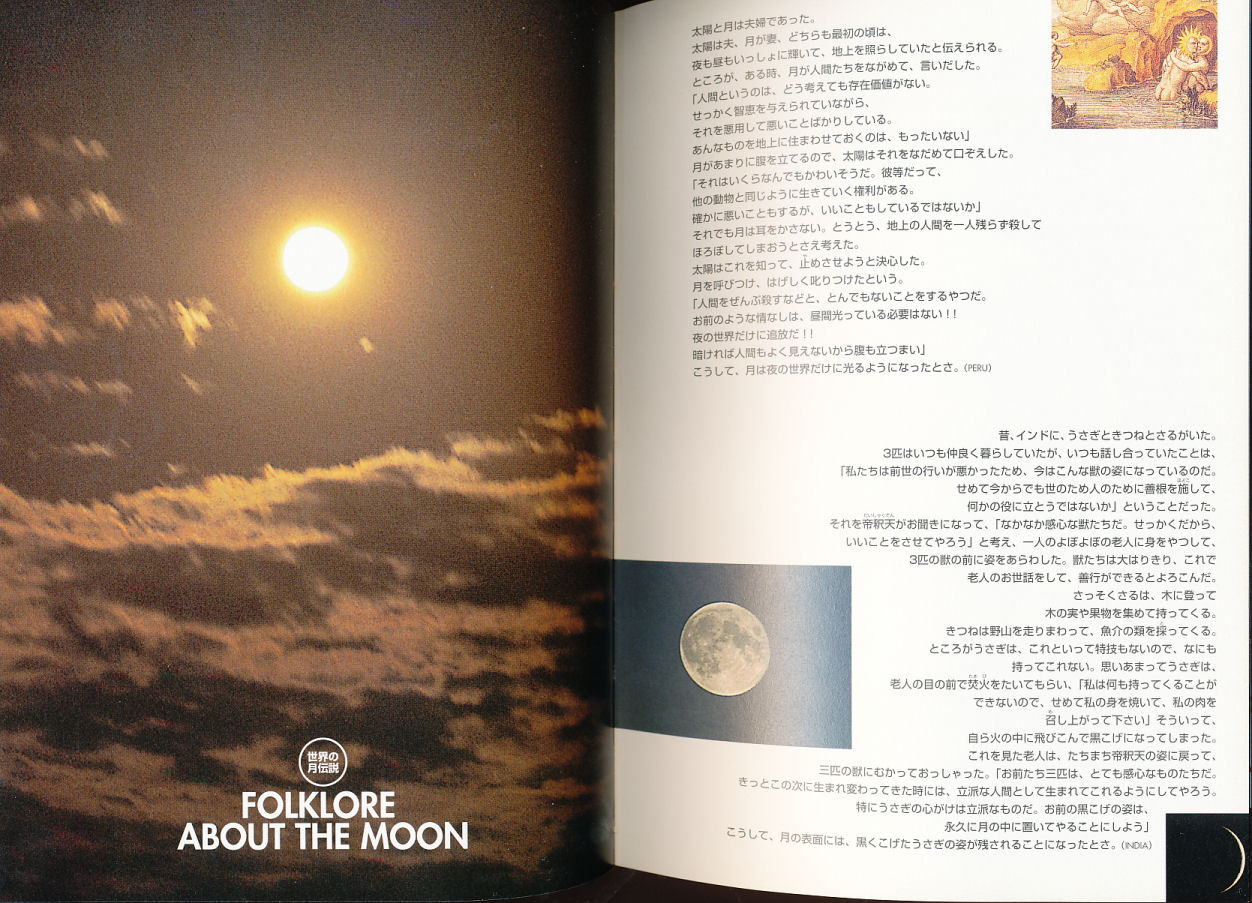

![]()
|
久しぶりに月を追いかけた。しんとした中空を行く月は、山並みや森を照らし美しかった。 三日月、上弦、満月、下弦と、満ち欠けをくり返す月は、いつも豊かな表情を見せてくれた。 ところが、撮影を進めていくうちに、満天の星空で撮影をしているときとは、まったく違う心理 状態であるのに気づいた。月に癒されていると同時に心が乱されるような、妙な気分である。 月齢からくるものなのか、月光からくるものなのか、あるいは月の引力が引き起こす潮汐現象 なのかは分からない。英語のルナティック(狂人)は、ラテン語のルナ(月)が語源になってい るところをみると、月の影響を受けたのかもしれない。ただし、限られた期間での撮影だった ので、その焦りだったかも。月齢と潮の干満を感知し、繁殖する魚などがいることは知られて いる。アメリカ・カリフォルニア州の海岸では、4月から8月の大潮の日に、グルニオンという いわしに似た魚が、満潮時に産卵しにやってくる。大潮のときなので、必ず新月か満月とい うことになる。同じように、人間も月のリズムに同調する「生物時計」をもっている。人間も、海 に生命の源をもっているので、少なからずその影響を受けているのだろう。この本は文学、 天文学、社会学、人類学、美術など、さまざまな角度からの月の謎や魅力を各分野の専門 家が分担編集したものである。月のガイドブックとして役立てていただければ幸いである。本 書には、図版や挿し絵などたくさん使われている。関係各位に感謝する次第である。
|
|
ついて研究を行った。先天的に目の不自由なこの男性は、睡眠リズムが周期的に ひどく乱れるため、何年も苦しんでいたのである。実験室内において脳波やホルモ ン、体内活動などの生物学的機能をかなりの日数をかけて記録してみた。すると、 この被験者の体温、緊張の度合い、正常時の睡眠パターンには、ある一定の周期 があることがわかった。それらはすべて、24.8時間という周期だったのである。太 陽の1日のリズムは24時間だが、月の1日のリズムは24・8時間である。つまり、こ の男性にみられた周期は、月のそれとまったく同じだったわけである。さらに驚いた ことに、彼の睡眠開始時刻は、実験が行われた地域の干潮の時刻とぴったり一致し ていたというのだ。
よく知られていることだが、生物の体内には、外的環境などの影響とは無関係に体 のリズムを保つタイマー、「体内時計(生物時計)」が組み込まれているという。人間 の体内時計は約25時間といわれるが、厳密には、月のリズムと同じ24.8時間な のかもしれない。
月が人間の生殖サイクルに関係しているという考えも古くからあった。インドでは、 新月や満月時に出産が多い、妊娠したときの月齢で性別が決まるとか、ナヴァホ・ インディアンの間では、月の引力が羊水を引っ張るため満月時に出産が多くなる、 といったいい伝えがあり、いまでも信じられている。さて、科学者たちの研究では、 1961年、ドイツのヒルマー・ヘカート博士が、人間の死や出産には、月のリズムが あることを立証し、また、1966年にはロバート・マクドナル博士が、満月と新月のと きには出産が多くなるという論文を学会報に発表した。誕生したときにはすでに生殖 サイクルが決定している、という説もある。旧チェコスロバキアのオイゲン・ヨナス博士 は、女の子の場合、誕生するときの太陽と月の位置がそのあとの排卵や月経などの 生殖リズムを決める、と考えている。また、排卵のリズムを正しくつかめば妊娠しやす い日がわかり、妊娠調節や産児調節はかなり高い確率で成功する、と報告している そうだ。月経や生殖サイクルと月齢についてはその後も多くの学者が研究しており、 両者の関係は、ほぼ認められているといっていいようだが、まだまだ研究途上のテー マであることもたしかなようだ。 (本書より引用)
|
|
2012年2月17日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)