 当サイトは、Amazon(新品、古本)のアフィリエイトに参加しています。 当サイトは、Amazon(新品、古本)のアフィリエイトに参加しています。
古本においては、Amazonが一番充実しているかも知れません。
またブラウザ「Firefox」ではリンク先が正常に表示されない場合があります。
|
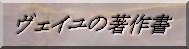
|
 |
|
 「重力と恩寵」 「重力と恩寵」
田辺 保 訳 講談社文庫
 時間を捨て去ること、重力と恩寵、不幸、宇宙の意味、労働の 時間を捨て去ること、重力と恩寵、不幸、宇宙の意味、労働の
神秘、清めるものとしての無神論、などの39の項目に彼女の深い
洞察が書かれている。なおこの本の「解題」には、一農夫として
大地に密着した生活を送りつつ、時代の流行思想とは無縁な
独自の思索をつむぎ出した農民哲学者のティボンが愛情を込め
て友情関係にあった彼女を感動的に描き出している。
1969年、「愛と死のパンセ」野口啓祐・訳 南窓社が出ているが、
この「重力と恩寵」と同じものである。
 シモーヌ・ヴェイユのそうめったにない作品を世人の目にさらす シモーヌ・ヴェイユのそうめったにない作品を世人の目にさらす
のは、わたしには苦痛である。これまでわたしは、ほんのわずか
な友人たちとだけ、彼女という人とその思想とを知るよろこびを
分かち合ってきたのだが、今日は、家族の秘密を洩らすような
堪えがたい思いを感じている。ただひとつわたしのなぐさとしてい
るのは、広く世に知られることによって、この清いものがけがされ
るのは避けられないとしても、それを越えて彼女の証言が、彼女
のたましいと姉妹のように通じあういくつかのたましいにまでたどり
ついてくれるだろうと思うことである。
・・・ギュスターブ・ティボン・同著「解題」より引用
|
| |
 |
|
 「神を待ちのぞむ」 「神を待ちのぞむ」
田辺 保 ・ 杉山 穀 訳 勁草書房
 「神を待ちのぞむ」は、シモーヌ・ヴェイユがマルセイユおよび 「神を待ちのぞむ」は、シモーヌ・ヴェイユがマルセイユおよび
カサブランカから、ペラン神父にあてた手紙六通と、フランスを離
れてアメリカにむかうとき、同神父に託した五編の文章とから成り
立っている。すなわち、1939年9月に第二次世界大戦がはじまり、
翌40年6月パリが陥落して、ドイツ軍が進駐してくると、ユダヤ系の
血を引く彼女はナチの粛清をのがれて、南部の非占領地帯へ移
らねばならなかった。一時、ペタンの仮政府がおかれていたヴィシ
ーに滞在したあと、40年10月に、両親とともにマルセイユにたどり
ついたのである。マルセイユにたどりついたのである。マルセイユ
で、翌年6月、ドミニコ会修道院長のジャン・マリー・ペラン神父と
出会う。シモーヌ・ヴェイユのキリスト教への接近は、この時から
はっきりと具体的な形をとりはじめる。
この時期にいたるまでの彼女の宗教的な体験については、本書
におさめられたペラン神父あての手紙、とくに「精神的自叙伝」と
いう題がつけられた42年5月15日付の第四の手紙にくわしく述べ
られている。この手紙は、いわば彼女の霊的遍歴の記録であり、
工場生活における「不幸」の発見、スペイン内乱参加においての
挫折感を経て、次第にキリスト教的な運命の受容の態度にいたる
過程がよくうかがわれる。ポルトガルの小さな漁村の夜、キリスト
教を「奴隷の宗教」であると直感する場面、アシジの礼拝堂で思
わずひざまずいて祈るところ、ソレム修道院での完成された宗教
的勤行に参加して深い感激を味わうあたりなど、とくに印象に残
る描写である。こうしてペラン神父の導きのもとに、キリスト教的
な求道を進めて行くのであるが、1941年の夏には、アルデーシュ
県サン・マルセルに、ペラン神父の紹介で、百姓哲学者として知
られたギュスターヴ・ティボンをたずね、農家で労働をしたいとい
う希望をのべる。そして、一ヶ月間、毎日、近隣の農家の女たち
にまじってはげしい畑仕事に従事するのである。最初、ティボン
のところに滞在していたとき、夕方、仕事がすむと、石のベンチ
にすわって、ティボンにギリシャ語を教え、ティボンからは、十字
架の聖ヨハネの著作などを借りて読んだ。(ギリシャ語のテキスト
として、「主の祈り」をえらび、仕事の最中にも原語でそれを暗誦
したと言う。本書中の「主の祈りについて」という一文は、こと時の
瞑想に独自な注釈をほどこしたものである。)ほどなく、彼女は
渡米の手続きのためにマルセイユへ呼びもどされ、ふたたび
ペラン神父の指導をうけるが、神父がしきりに洗礼を受けて
カトリック教会へ正式に所属するようにすすめたにもかかわらず、
彼女はついに最後までこれを拒み、1942年5月17日マルセイユ
を出発、途中カサブランカの収容所で半月ばかりを抑留された
のち、6月末ニューヨークへ到達する。この間の彼女の心境、
受洗をついに承諾せず、最後まで「教会の入口」にとどまった
彼女の内面的理由は、ペラン神父あての手紙にくわしく述べら
れている。これらの手紙は、シモーヌ・ヴェイユの教会観、キリ
スト教に対する見方を知る上に非常に興味深い、貴重な資料で
あると言えよう。彼女が、この世の機構としての「教会」を忌避し
たのは、もちろんすべての「社会的なもの」「党派」として存在する
諸機関のもつ独善性、排他性を見ぬいたのと同じ動機に出てい
るのであろうが、(「重力と恩寵」の中の言葉を借りれば、いわゆ
るこの「太った動物」)、ひろくギリシャ哲学やヒンヅーの宗教の
うちにもキリスト教的な真理の投影を見ずにはいられなかった、
とらわれない開かれた心のためであろう。こういう彼女の態度は、
単に諸宗教の教義に類似したものを求めて、一種の普遍的な
総合を目ざそうとするシンクレティズムとも見られようが、もとも
と基本的にはキリスト教的な深い運命の感覚、世界意識から
出発して、その原形ないしアナロジーを諸民族のたどりついた
古典的英知のうちに求めて行ったものと解すべきであろう。こう
いうところから、往々シモーヌ・ヴェイユの宗教的体験が「異端」
ときめつけられたり(たとえば、「二十世紀文学とキリスト教」の
著者シャルル・メレル師)、一たん書いた初版の序文を撤回した
ペラン神父の早計な誤解も生まれてきたのである。しかし現在
では、教会自身もシモーヌ・ヴェイユの望んだように「変化して」い
るのであり、当のペラン神父の序文を付して、刊行されたダニエ
ルウ師らの共著「シモーヌ・ヴェイユの疑問への応答」(1964年、
オービエ版)によれば、彼女の提起したさまざまな問題について、
その真理契機を十分に尊重しつつ、教会の教義の内容の「カト
リック」なひろい展望のうちにできるだけ包容して行こうとする寛容
な努力が見られるようである。この書物の中には、シモーヌ・ヴェ
イユによって、「超自然性」の確かさを教えられ、キリスト教信仰を
見出した一女性の感謝の告白までが含められている。
(本書「訳者あとがき」より引用)
|
| |
| |
|
 「根をもつこと」 「根をもつこと」
山崎庸一郎 訳 春秋社
 「根づくということは、おそらく人間の魂のもっとも重要な要求で 「根づくということは、おそらく人間の魂のもっとも重要な要求で
あると同時に、もっとも無視されている要求である。」という言葉か
らこの書は始まる。戦後の社会をどのように構築してゆかねばな
らぬのか人間の精神的な渇きを根底に置きながらヴェイユの鋭い
考察が始まる名著。第二次世界対戦中、自由フランス政府、すな
わち「闘うフランス国民委員会」(ロンドンにあった)のフランス活動
部門に配属される。ここで彼女はフランス潜入を希望したが容れら
れず、解放後のフランスの未来についての立案を命じられる。そし
てその報告書が「根をもつこと」だが寝食も忘れて書き続け、その
半年後、フランスで闘っている同胞の食料事情を思い、食物を拒否
し、「飢餓および肺結核による心筋縮退から生じた心臓衰弱」で八
月二十四日永眠。享年34歳。
 「この書物は,政治家たちがほとんど読むことのない、そしてまた、 「この書物は,政治家たちがほとんど読むことのない、そしてまた、
政治家たちの大部分には理解されることも、その適用法を知られ
ることもないあの序論という部門において、政治学に属している。
このような書物は、同時代の国政の運営に影響を与えることはない。
すでに政界に乗り出して、政治という市場の隠語に引っ込みがつか
ぬほど縛られている男女にとって、この種の書物が現れるのはつね
に遅すぎるのだ。本書は、余暇が失われてしまわぬうちに、思考能
力が政界場裡の生活や国会のなかで破壊されぬうちに、青年たち
によって研究されるべき書物の一つである。われわれとしては、
このような書物の効果が、別の世代の精神的態度に判然と現れる
であろうことをねがうほかはない。」・・・T.S.エリオット
(本書より引用)
|
| |
 |
|
 「超自然的認識」 「超自然的認識」
田辺 保 訳 勁草書房
 古代諸民族の伝承や各国の神話、民話の比較研究、聖書の章 古代諸民族の伝承や各国の神話、民話の比較研究、聖書の章
句についての独自の釈義、ところどころにはさみこまれた、比類の
ない、個性のひらめきを放つ鋭く深い省察のちりばめられた本書の、
やはり中心は、超自然的真理の、こういうきわめて厳正な科学的
研究という面に求められるべきでははないだろうか。その生涯を通
じて、ひたすら現実の底にかいくぐり、そのもっとも奥深い、なまの
リアリティに触れようとこころざしてきたのが、シモーヌ・ヴェイユの
霊的歩みであったとしたら、この現実を組み上げている必然的諸関
係の均衡をできるかぎり知性の光によってとらえつくそうとし、断片
的ながらともかくもその成果を言語表現によって記録しようと試みた
のが、晩年のこれらのノートの神髄であったといえよう。
表面にあらわれた、すさまじくもきびしい彼女の生きざまのまったく
背面に、ここに記されたような霊的経験が熟していたと知ることは、
わたしたちの魂にも抑えきれぬ深甚の激動をもたらさずにはおか
ないのである。この純粋な、つきつめた生き方は、内側において、
現実を把握するこの眼識と、痛烈なばかりの祈りに支えられていと
なまれていたのである。ダヴィ女史が、「魂を底からくつがえすよう
な祈り」と呼び、その言葉のもつ力を、ほんのわずかの間だけでも
もし信じられるとしたら、「恐怖にとらわれずにいられない」と、いみ
じくも評した、あのおそろしくも、感動的な祈りは、ノートの第五冊め
の中に見出される。「神にむかって叫ぶ。父よ、キリストの御名に
よって、このことをわたしにゆるしてください・・・」この祈りの文章を
読むとき、わたしたちにおそいかからずにいない震撼は、そのまま、
「ロンドン論集」の中のあの「愛の狂気」にかんする一条にみなぎっ
ていた戦慄感にも通じる。「愛の狂気、それがひとりの人間をとらえ
るとき、それは人間の行動と思考の様式を完全に変化させる。愛の
狂気は、神的な狂気と同種のものである」 日常的次元に生きる
わたしたちの目を引きさくたぐいの、シモーヌ・ヴェイユの在り方に
対して、またきわめて独創的で、奇抜で、人々の意表をつくその
思想に面して、ともすると一般の反応は、そんなことをしてなににな
るのかという疑問であり、常識や分別では到底割り切れない、実在
の裂け目の前にいきなり連れ出されたふうな戸惑いである。しかし、
シモーヌ・ヴェイユのような人たちにおいては、「飢餓が器官の機能
をこわしてしまうのと同じ程度に、魂の自然な均衡をうちこわすある
欲求がかれらの内部にあった」ことは確かであり、かれらは、「気が
狂っていた」ともいいきってしまうこともできよう。弱い人間のうちに
神が根をおろすならば、どういうことが起こるだろうか。ダヴィ女史
はたしか、土の鉢に植えこまれたかしの実が、鉢をくだいてしまう
キェルケゴールの例話を引いていた。今もなお、わたしたちを打ち
のめす、シモーヌ・ヴェイユの経験の本質とは、こういうものである。
既に、聖パウロも、「わたしは気が狂ったようになっていう」といった
ように、これこそは、「神の愚か(狂気)」なのである。すべての者に
うち捨てられ、あらしの荒野をさまようリヤ王のそばにさいごまで
つき従った、あの阿保の道化は、主人公が悲惨と孤独の境におち
いり、劇的状況がひときわ深刻の度を加えてくるとき、だれからも
聞かれなくてもいよいよ真実の叫びを放つということを、彼女自身
も書いていた。わたしたちのまわりに、目には見えぬ暗いとばりが
重くたれこめてきつつあるとの予感が切実なこの日頃、シモーヌ・
ヴェイユの言葉がますます非常な現実感をともなってひびいてくる
のに、わたしたちは耳をふさぐことができるだろうか。・・・・
(本書「訳者あとがき」より引用)
|
| |
 |
|
 「愛と死のパンセ」 「愛と死のパンセ」
野口啓祐・訳 南窓社
 ヴェイユが遺した多くの言葉をまとめたものが「愛と死のパンセ」で ヴェイユが遺した多くの言葉をまとめたものが「愛と死のパンセ」で
あるが、後に田辺 保 訳で講談社から「重力と恩寵」という題で出版
される。
 「重力と恩寵」 「真空とそれを埋めるもの」 「真空を受け入れよ」 「重力と恩寵」 「真空とそれを埋めるもの」 「真空を受け入れよ」
「超脱」「空想は真空を埋める」 「時間を捨てよ」 「対象なしに望め」
「自我」「被造性をみずから剥ぎ取れ」 「自我の抹殺」
「必然性に服従せよ」 「迷妄」「偶像崇拝」 「愛ということについて」
「悪とはなにか」 「不幸と苦しみ」 「暴力」 「十字架の意味するもの」
「必然と善の間にはいかなる距(へだた)りがあるか」「偶然は教える」
「愛さねばならぬ者は不在だ」 「無神論はわれわれを浄化する」
「待ち望むこと みずから意志すること」 「訓練せよ」 「知性と恩寵」
「読み取ることとは・・・」 「宇宙はなにを意味している」
「メタクシュ あるいは『橋』」 「美」 「代数学」 「集団の烙印」
「巨大な怪獣」 「イスラエル・・・あるいは全体主義国家」
「社会の調和」 「労働の神秘」
|

|
 |
|
 「シモーヌ・ヴェイユ・その極限の愛の思想」
「シモーヌ・ヴェイユ・その極限の愛の思想」
田辺保著 講談社現代新書
 あえてこのおそろしい光に近づこう---この一すじの純粋さ--- あえてこのおそろしい光に近づこう---この一すじの純粋さ---
この小さな本の中で、わたしが見つめてみたいと思うことは、ただ
この点につきるかもしれない。しかし、この純粋さは、火の矢となっ
てわたしたちを射とおす。この炎に身を焼かれる覚悟がなくては、
わたしたちは、シモーヌ・ヴェイユに一歩も近づくことはできないと
いえよう。ふつう一般の基準、わたしたちが日常なんの疑問もなく
用いている理屈や習慣に対して、彼女はつねに挑戦し、わたした
ちの安易さをうち破るのである。こういう彼女の前で、わたしたち
は、あるとまどいや恥じらいをおぼえずにはいられないとしても、
ここにはまた、わたしたちを変革する一つの力の存在をもたしか
にみとめずにはいられないであろう。マグドレーヌ・ダヴィ女史は、
「シモーヌ・ヴェイユのことを正しく語るには、彼女が立っている場
所に自分もまた、きっかりと位置することができねばならないので
あろう。そのときこそ、わたしたちの見る目が、彼女の見る目に達
するのであろう」と書いている。とはいえ、そこにまで達することの
不可能さを、わたしもまた、ダヴィ女史とともになげくことからはじ
めなくてはならない。この強烈な炎に近づいて行くことの危険を知
りすぎるほどに知りながらも、やはりわたしも光を指示するという
使命感につき動かされるのをおぼえずにいられない。いくつかの
彼女の著作もでそろい、機も熟した今、ともかくもこうして、わたし
自身の手で、貧しくつたない筆ながら、彼女の生涯と思想とを日本
の読書界に紹介できる機会が与えたれたことは、何よりも深いよ
ろこびであり、同時にまた、おそろしいことである。せめても、「この
光が人を焼きつくすものであっても、光をますの下にかくしておいて
もよいという十分な理由にはならない」というギュスターヴ・ティボン
の言葉だけに、ひそかな支えを求めつつ、読者とともに、この特異
な生涯をふりかえってみようと思う。
・・・・・本著 「はじめに---一すじの純粋さ」より引用
|
| |
| |
|
 「新装版 シモーヌ・ヴェイユの生涯」 「新装版 シモーヌ・ヴェイユの生涯」
大木健著 勁草書房
 肉体は病魔に蝕まれ、革命と戦争の暗い夜に苦悩した類まれな 肉体は病魔に蝕まれ、革命と戦争の暗い夜に苦悩した類まれな
魂の遍歴を記した研究書であると共に、同時代に生きたアルベー
ル・カミュ、シモーヌ・ド・ボーヴォワールとの共通点や対比を描き出
した書である。改めて本書の帯文に書かれている「不幸に対する敏
感さと真理に対する渇望と」を、彼女の生き方そのものに感じさせ
てくれる文献であり、ガブリエル・マルセルが言うところの「シモーヌ・
ヴェイユを理解するためには、真理に対する飢餓、現実に対する
渇きがなければならない」ことの真の意味を思い知らされる。
 シモーヌ・ヴェイユの書き残したものを読むと、そこに人をとまどわ シモーヌ・ヴェイユの書き残したものを読むと、そこに人をとまどわ
せるはげしさや、矛盾が少なくないことはたしかである。その行動に
は常識で考えられない愚かさもある。しかし、彼女は目を閉じてその
瞑想の中に世界の希望を捜し求めたのではない。また、泣く者ととも
に泣いていただけではない。彼女は、惨澹たる絶望的不幸の中に自
分自身の肉体を置き、人格を据え、その不幸の中核が彼女の目に
映るまでその場の苦難に耐え抜いた。そして、その絶望の砂の奥底
から、誰の目にもとまらぬほどささやかな萌芽を見つけ出したのであ
る。この苦闘から発したその言葉に矛盾があることはむしろ当然のこ
とであろう。われわれがこの苦闘の本質を見きわめることなしに、その
思想の局部をとらえて軽率に「これは賛成」「これは不賛成」と批判す
るにとどまるならば、われわれは<純金の預かり物>を受け取ること
はできないであろう。この荒野に呼ばわる声を聞くには、それ相当の
敬虔さと努力が必要なのである。彼女の苦闘によって発見された、
不幸と真理との血縁関係を示す細い沈黙の道があることを信じるなら
ば、われわれはまず姿勢を正さなければならないのである。
・・・・・・・本書「終焉の地ロンドン」より引用
|
| |
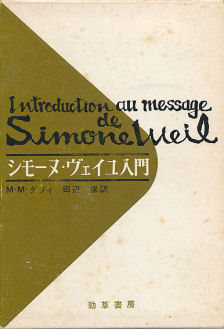 |
|
 「シモーヌ・ヴェイユ入門」 「シモーヌ・ヴェイユ入門」
ダヴィ 著 田辺 保訳 勁草書房
 ヴェイユを誰よりも深く理解し敬愛するダヴィ女史による解説。 ヴェイユを誰よりも深く理解し敬愛するダヴィ女史による解説。
 この本の原著者マリー・マグドレーヌ・ダヴィ女史には、あと二冊、 この本の原著者マリー・マグドレーヌ・ダヴィ女史には、あと二冊、
シモーヌ・ヴェイユにフランス語の研究書がある。(『シモーヌ・ヴェイユ』、
「二十世紀の証人」双書、1956年、「哲学」双書、1966年)。1956年版
の本には、有名な哲学者ガブリエル・マルセルが序文を寄せており、
その一ばん最初の部分でマルセルは原著者について次のような賛辞
を述べている。
「マリーマグドレーヌ・ダヴィ女史こそ、だれにもまして、シモーヌ・ヴェ
イユという人のおもかげ、他にまったく比類のないこのおもかげをよみ
がえらせるのにふさわしい人であると言えよう。女史こそ、熱情溢るる
心、範とすべき高邁さ、見るべき明哲な精神をかねそなえた人だから
である。・・・・シモーヌ・ヴェイユについて、これ以上に知性に裏づけら
れた敬愛の思いをもって語ることは、ついにこれまでだれにもできない
ことであった。」
(本書 訳者あとがき より引用)
|
| |
 |
|
 「シモーヌ・ヴェーユの世界」 「シモーヌ・ヴェーユの世界」
ダヴィー著 山崎庸一郎訳 晶文社
 マリー=マドレーヌ・ダヴィーほど、シモーヌ・ヴェーユの相貌、他の マリー=マドレーヌ・ダヴィーほど、シモーヌ・ヴェーユの相貌、他の
いかなる人間とも似ていないその相貌を想起させるにふさわしいひと
はいない。彼女に見られる心情の熱烈さと、範例とすべき寛大さと、
すぐれて明哲な知性との結合のゆえに、彼女はそれにふさわしいの
である。ありがたいことに、彼女がそのモデルについて描いた肖像の
なかには、いささかも聖者伝的なところはない。だが、これ以上に知的
な敬虔さをもってシモーヌ・ヴェイユを語ることは、たしかに不可能であ
る。ひとしく驚嘆すべきものである彼女の作品と生涯とを注意深く眺め
てみればみるほど、私にはますます確信をもって、この両者をなんらか
の公式のなかに閉じこめることが不可能であるように思われてくる。
マドレーヌ・ダヴィーはキルケゴールから借用された表現を用いて、シ
モーヌ・ヴェーユは真理の証人だったと語っている。そうかも知れない。
だがむしろ私は、はるかに希有のことであり、かついっそう逆説的でも
あるが、彼女は「絶対の証人」だったと言いたい。
・・・・・・・・本著「絶対の証人」 ガブリエル・マルセルより引用
|
| |
| |
|
 「回想のシモーヌ・ヴェイユ」 「回想のシモーヌ・ヴェイユ」
J.M.ペラン / G.ティボン著田辺保訳 朝日現代業書
 ヴェイユと深く親交を持っていた、ペラン神父と農民哲学者のティボン ヴェイユと深く親交を持っていた、ペラン神父と農民哲学者のティボン
による回想録
 真に偉大な人々の生涯をまったくそこなうことなしに語ることがどん 真に偉大な人々の生涯をまったくそこなうことなしに語ることがどん
なにむつかしいかについて、ボードレールは、あまり知られていないが、
次のような文章を書いている。「いったいだれが、太陽の伝記を書こう
なんて思いつくだろうか。この星が生命のきざしを示しはじめてからの、
単調と光と崇高さとにみちた歴史なんだが」。そして、事実、太陽の歴
史は、神についての歴史と同様に書かれることはないのだ。歴史にお
いて群集の堕落した欲望をそそりたてるようなものはいっさい、きっぱ
りとはねつけられているのである。人は、空虚なたましいを持てば持つ
ほど、あらゆるものごとの不変の本質を味わい知ることができず、現代
性だとか、新奇さだとかのピーマンで味つけされたものを必要とするの
だ。肝心の本質をなおざりにして、めずらしい出来事にばかり熱中し、
深い価値、真の実在性をもつもの、原初の光の単純さに近いものにあ
っては、存在と出来事、本質と実存とが一致する傾向があることを考え
てみようとしない。より高い世界においては、とくに何も起こることはな
いのだ。なぜなら、そこではつねに、同じことが起こっているからである。
夜明けのくるごとに、いつも同じさまで、純に清らかに生まれでてくる太
陽がそうであるように。また、同じ岸辺のあいだを、終わりなく流れてや
まない川がそうであるように。また、ふたりの人間が死に至るまで結び
つける真実な愛がそうであるように。何ものによっても弱められず、力
を失なわず、正しい者の上にも、正しくない者の上にも雨を降らせる
神の愛がそうであるように。こういったふうな真にわたしたちを養い育
て上げる実在の中には、ひとつとして、世間の好奇心をかきたてるよ
うな、意想外の偶然性や煽情的な新奇さは含まれていない。だからこ
そ、ともかくもいくらか見栄えがし、あまり重要でないなんらかの出来事
をそこに持ちこんでくる必要がでてくるのだ。たとえば、太陽が日食の
ために欠けたり、川が洪水をおこしたり、夫婦が口論しあったり、神が
物質の上に働きかけて奇跡をおこす必要があるのだ。あまりにも深く
内側に沈み、ただ持続して行くものであるために、煽情的ではありえ
ない。だからこそ、人々は気づかぬままに過ぎて行ってしまうのである。
シモーヌ・ヴェイユの真の偉大さも、こういう次元に属するものであった。
彼女の言葉の真実の意味をつかもうとするなら、幾重にも重なった
沈黙の厚みの中をくぐりぬけてこなければならない。そのときはじめて、
この言葉を告げるのが、もはや彼女その人ではなく、より高くにある霊
であって、彼女のたましいとからだはその従順な道具となっていたにす
ぎないことをさとるだろう。こういう至高の霊感のときには、ものを書く手、
考える頭は、もはやただ、「死すべきものと不死なるものとをつなぐきず
な」、「創造主と被造物とがそれぞれの秘密を交わしあう」ための、人格
を脱した仲介物になりおわるのである。
・・・本書「はじめに」G・ティボンより引用
|
| |
| |
|
 「純粋さのきわみの死・さいごのシモーヌ・ヴェイユ」
「純粋さのきわみの死・さいごのシモーヌ・ヴェイユ」
田辺 保 著 北洋社
 「純粋さ」とはなんだろうか。講談社現代新書版の小著「シモーヌ・ヴェ 「純粋さ」とはなんだろうか。講談社現代新書版の小著「シモーヌ・ヴェ
イユ」の初めに、こんな問いをおいた。十年前に世に出されたこの小著
でも、むろんこの課題はつねに意識の底にしっかりと保持していたつも
りだが、新書版では何しろ分量が十分ではなかった。シモーヌ・ヴェイユ
の、あまりにも多彩な、変化に富む生涯を、外側から、また内面的にも、
追うことばかりに賢明になり、一つのテーマで筋を通し、自分なりの解答
をさいごに見出してきたとはいいがたい。
・・・・・・・・・・・本著「あとがき」より引用
 本書の外面的な構成は、一応シモーヌ・ヴェイユゆかりの土地をめぐ 本書の外面的な構成は、一応シモーヌ・ヴェイユゆかりの土地をめぐ
る旅行記と、それぞれの場所においてもっとも重要なかかわりのある
主題の考察とをからみ合わせながら、著者自身の個人的なメモやノー
トを公開するという形をとりつつ、読者に対しても問題への主体的な臨
場感の興味を添えしめて行こうと意図している。もちろん、この試みが
どこまで成功しているかは、自信がない。読者のきびしい批判を仰ぎた
いと思う。各章は、シモーヌ・ヴェイユと「詩」、カタリナ派、イタリアの画
家たち、聖フランチェスコ、ジョー・ブスケなどとの関係をさぐってみた、
それぞれ独立した小エッセーと見てもらってよいのであるが(中略)、マ
ルセイユ、フィレンツェ、アッシジ、カルカソンヌ、パリなど、仏伊の各都
市の名を縦の軸として全体をつなぎ、全体に流動性と一貫性をつけよう
とした。シモーヌ・ヴェイユの研究家R・リースは、彼女の研究に向かう場
合、最初にどこを出発点にしてもよいといっている。彼女の思想は体系
ではなく、あらゆる細部が全体と関連し合い、一つのテーマを追えば必
ず他の諸テーマがつながって出てくる、「生きられた神話」であったから
である。本署においても一見して、個々別々の問題を各章で扱っている
かに思われるであろうが、全体を通読していただければ、ある有機的な
連関がその間にあるのに気づいていただけよう。
・・・本著「あとがき」より引用
|
| |
| |
|
 「ヴェイユの言葉」 「ヴェイユの言葉」
富原眞弓 翻訳 みすず書房
 本書 「編訳者 序」 より引用 本書 「編訳者 序」 より引用
本書は、シモーヌ・ヴェイユの残した断章を5つのカテゴリーに分類して
収録した。いうまでもなく、同じ断章でも読みによって異なるカテゴリーに
属しうる。それでもかまわない。この種の読みの多様性こそが、ヴェイユ
によれば知性の自由な行使を証し、人為的な整合性の欠如こそが、と
きとしてテクストの真正性の保証なのだから。大別して断章は執筆年順
に配置してあるが、場合により内容上のまとまりを優先した。
|
| |
 |
|
 「シモーヌ・ヴェーユ最後の日々」 「シモーヌ・ヴェーユ最後の日々」
ジャック・カボー著 山崎庸一郎訳 みすず書房
 この死をまえにした最後の時期、彼女の言辞に如実にうかがわれ この死をまえにした最後の時期、彼女の言辞に如実にうかがわれ
るように、彼女の知的自我の習慣的メカニスムは、若干の逸脱とも
呼ぶべきものを伴いながら、ときには解決不可能な神学的問題をめ
ぐる非現実的な雰囲気のなかで、いぜんとして運動していたかも知れ
ない。だがその反面で、彼女が実践した「愛の狂気」は、衰えてゆく
肉体のなかで自我の発言を徐々に封じてゆき、彼女の心情は意識
せずして神に満たされていなかったとだれに断言しうるであろうか。
真に内的な劇は立ち入る権利はないという意見も原著者ははっきり
表明しているが、われわれは本書のなかに、以上の線に沿った解釈
の方向をうかがうことができるし、この方向は、ヴェーユの包括的理
解にも重要な因子となりうるものと考えられる。この点は、貴重な新
資料と提出とならんで、本書の忘れてはならぬ価値であろう。
(本書 訳者あとがき より引用)
 1942年6月のマルセイユ出港から、ニューヨークを経て、翌年8月 1942年6月のマルセイユ出港から、ニューヨークを経て、翌年8月
に亡命先ロンドンで悲劇の死を遂げるまでの15ヶ月間は、ヴェーユの
最大の文学的活動の時期であった。ヴェーユの思想の独自性への
深い理解と、緻密な資料・証言蒐集から生まれた本書は、この最後
の日々に光を当て、短かりし生涯を通じてつねに真理のみを追究した
稀有の魂の内面のドラマを描き出す。
(本書より引用)
|


![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 各文献の前の
各文献の前の![]() をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。




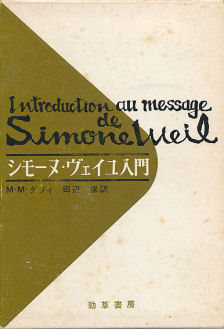


![]()
![]() 未読の文献
未読の文献![]() をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。
をクリックすると表紙・目次並びに引用文が出ます。![]()
![]() 未購入(新刊も含む)の文献
未購入(新刊も含む)の文献
![]()