|
 本書 より抜粋引用 本書 より抜粋引用
 おそらく終始、エイブリーを支えていたものは、自分の手で振られている試験管の内部で おそらく終始、エイブリーを支えていたものは、自分の手で振られている試験管の内部で
揺れているDNA溶液の手ごたえだったのではないだろうか。DNA試料をここまで純化して、
これをR型菌に与えると、確実にS型菌が現れる。このリアリティそのものが彼を支えてい
たのではなかったか。
別の言葉でいえば、研究の質感といってもよい。これは直感とかひらめきといったものと
はまったく別の感覚である。往々にして、発見や発明が、ひらめきやセレンディピティによっ
てもたらされるようないい方があるが、私はその言説に必ずしも与(くみ)できない。むしろ
直感は研究の現場では負に作用する。これはこうに違いない! という直感は、多くの場
合、潜在的なバイアスや単純な図式化の産物であり、それは自然界の本来のあり方とは
離れていたり異なったりしている。形質転換物質についていえば、それは単純な構造しか
持ちえないDNAであるはずがなく、複雑なタンパク質に違いないという思考こそが、直感の
悪しき産物であったのだ。
あくまでコンタミネーションの可能性を保留しつつも、DNAこそが遺伝子の物質的本体であ
ることを示そうとしたエイブリーの確信は、直感やひらめきではなく、最後まで実験台のそば
にあった彼のリアリティに基づくものであったのだ。そう私には思える。その意味で、研究と
はきわめて個人的な営みといえるのである。

博士号とかけて足の裏についた米粒と解く
そのこころはとらないとけったくそ悪いが、とっても喰えない
そんな戯れ言葉を先輩から聞かされていた。実際、思うに任せぬ実験に日夜明け暮れ、
ようやく博士号にたどり着いたはよいが、先の視界はあまり開けていないのが普通だ。
研究者としての就職口はごく限られている。幸運ならば大学助手のポジションにありつけ
る。ようやく好きなことをしてお金がもらえるようになる、と思ったら大きな誤りだ。お金を
もらえるようになるのは事実だが、それ以外はまったく違う。
助手に採用されるということはアカデミアの塔を昇るはしごに足をかけることであると同時
に、ヒエラルキーに取り込まれるということでもある。アカデミアは外からは輝ける塔に見え
るかもしれないが、実際は暗く隠微なたこつぼ以外のなにものでもない。講座製と呼ばれ
るこの構造の内部には前近代的な階層が温存され、教授以外はすべてが使用人だ。助手
・・・講師・・・助教授と、人格を明け渡し、自らを虚しくして教授につかえ、その間、はしごを
一段でも踏み外さぬことだけに汲々とする。雑巾がけ、かばん持ち、あらゆる雑役とハラス
メントに耐え、耐え切った者だけがたこつぼの、一番奥に重ねられた座布団の上に座るこ
とができる。古い大学の教授室はどこも似たような、死んだ鳥のにおいがする。
死んだ鳥症候群という言葉がある。彼は大空を悠然と飛んでいる。巧成り名を遂げた大教
授、優雅な翼は気流の流れを力強く打って、さらに空の高みを目指しているようだ。人々は
彼を尊敬のまなざしで眺める。
死んだ鳥症候群。私たち研究者の間で昔からいい伝えられているある種の致死的な病の
名称である。
私たちは輝くような希望と溢れるような全能感に満たされてスタートを切る。見るもの聞くも
ののすべてが鋭い興味を掻きたて、一つの結果が次ぎの疑問を呼び覚ます。私たちは世界
の誰よりも実験の結果を早く知りたいがため、幾晩でも寝ずに仕事をすることをまったく厭う
ことがない。経験を積めば積むほど仕事に長けてくる。何をどうすればうまくことが運ぶのか
がわかるようになり、どこに力を入れればよいのか、どのように優先順位をつければよいの
かが見えてくる。するとますます仕事が能率よく進むようになる。何をやってもそつなくこなす
ことができる。そこまではよいのだ。
しかしやがて、最も長けてくるのは、いかに仕事を精力的に行っているかを世間に示すすべ
である。仕事は円熟期を迎える。皆が賞賛を惜しまない。鳥は実に優雅に羽ばたいているよ
うに見える。しかしそのとき、鳥はすでに死んでいるのだ。鳥の中で情熱はすっかり燃え尽き
ているのである。

俗流進化論にマイクをまわせば、きっと彼らは次のように説明するはずだ。進化の原動力は
突然変異である。突然変異に方向性はなくランダムに起こる。生命の歴史のあるとき、ランダ
ムな突然変異が生じ、分節を持つ生物が生み出された。分節を持つ生物は、分節を持たない
滑らかな生物に比べ、不気味な形態となったが、文節を持つことの有利さをも享受することに
なった。たとえば、分節による機能の分担や繰り返し構造に伴う物質利用の効率化、あるいは
損傷の際、被害をその分節内だけにとどめることができる有利さやそのことによる修復のしや
すさなどである。こうして分節を持つ生物はより環境に適合し、分節を持たない生存競争に打ち
勝ち、今日、あまねく分節を持つ生物が広がったのである、と。
しかし私は、現存する生物の特性、特に形態の特徴のすべてに進化論的原理、つまり自然淘汰
の結果、ランダムな変異が選別されたと考えることは、生命の多様性をあまりに単純化する思考
であり、大いなる危惧を感じる。
むしろ、生物の形態形成には、一定の物理的な枠組み、物理的な制約があり、それにしたがっ
て構築された必然の結果と考えたほうがよい局面がたくさんあると思える。分節もその例である。

生命とは何か? それは自己複製するシステムである。DNAという自己複製分子の発見をもとに
私たちは生命をそのように定義した。
ラセン状に絡み合った二本のDNA鎖は互いに他を相補的に複製しあうことによって、自らのコピー
を生み出す。こうしてきわめて安定した形で情報がDNA分子の内部に保存される。これが生命の
永続性を担保している。確かにそのとおりである。
しかし、私たちが海辺の砂浜で小さな貝殻を拾ったとき、そこに生命の営みのあとを感じることが
できるのは、そして貝殻が同じ場所に同じように散在する小石とはまったく別の存在であることを半
ば自明のものとできるのは、そこに生命の第一義的な特徴として自己複製を感じるからだどうか。
おそらくそうではない。
自己複製が生命を定義づける鍵概念であることは確かではあるが、私たちの生命観には別の支え
がある。鮮やかな貝殻の意匠には秩序の美があり、その秩序は、絶え間のない流れによってもたら
された動的なものであることに、私たちは、たとえそれを言葉にできなかったにしても気づいていたの
である。
 
|
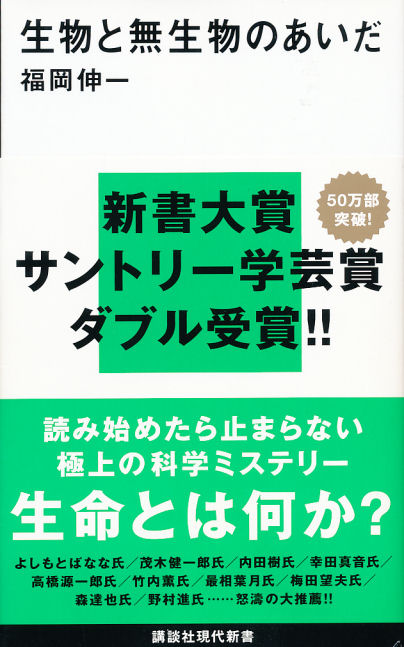
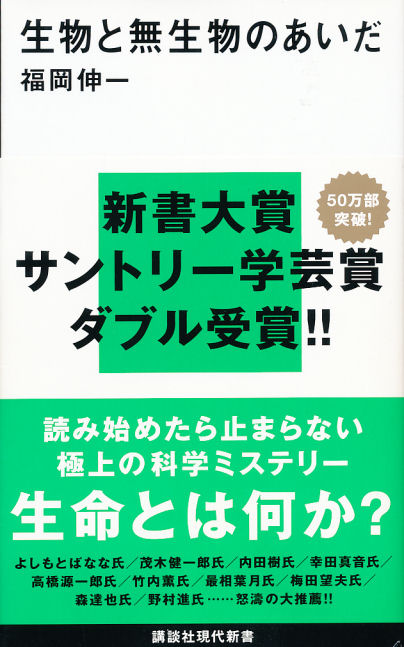
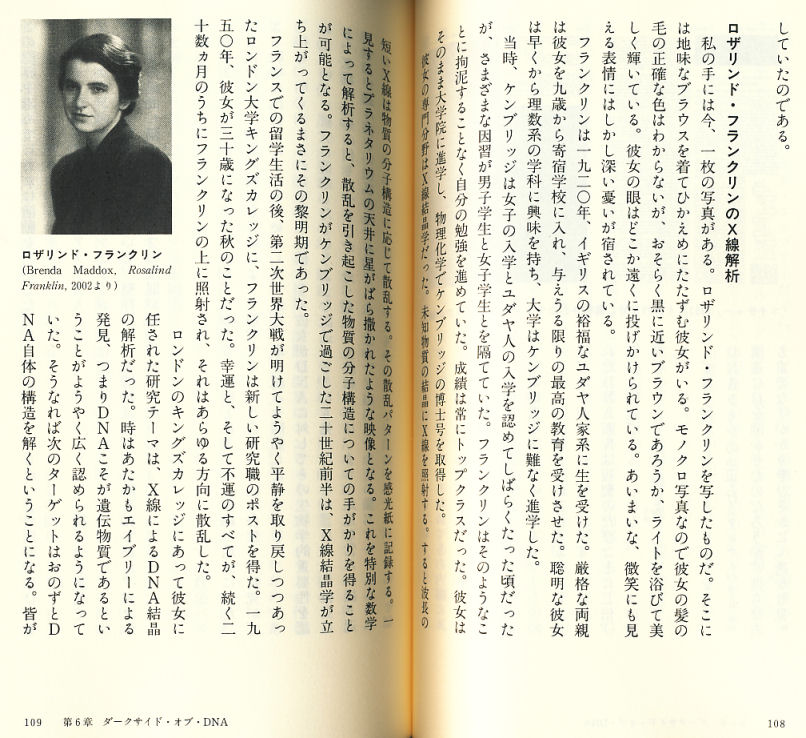
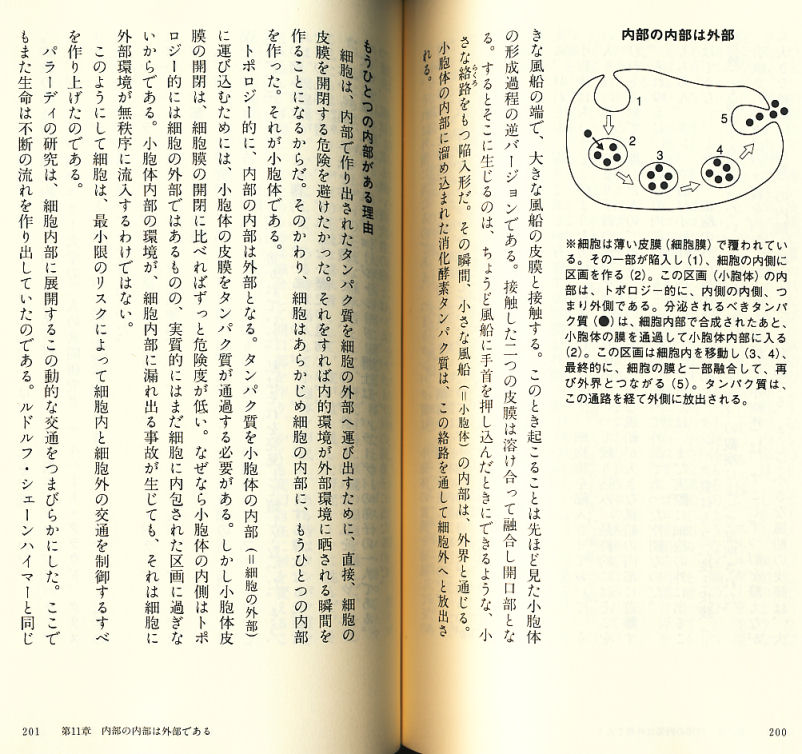
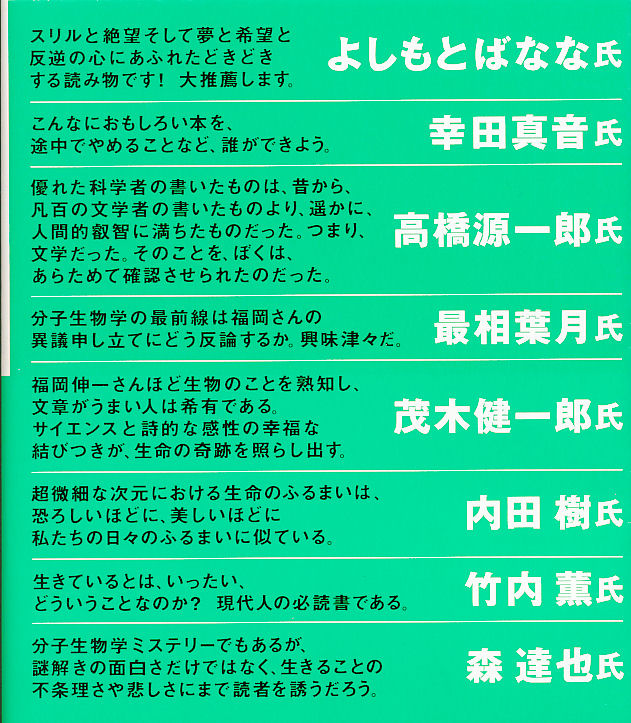
![]()

![]()

