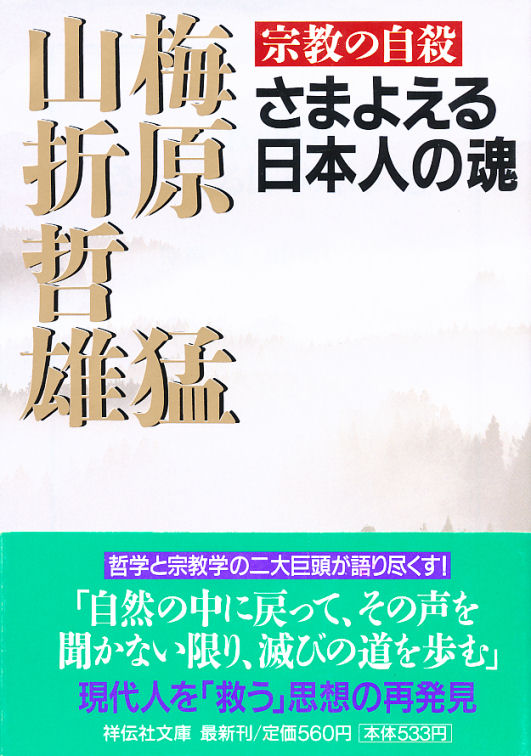
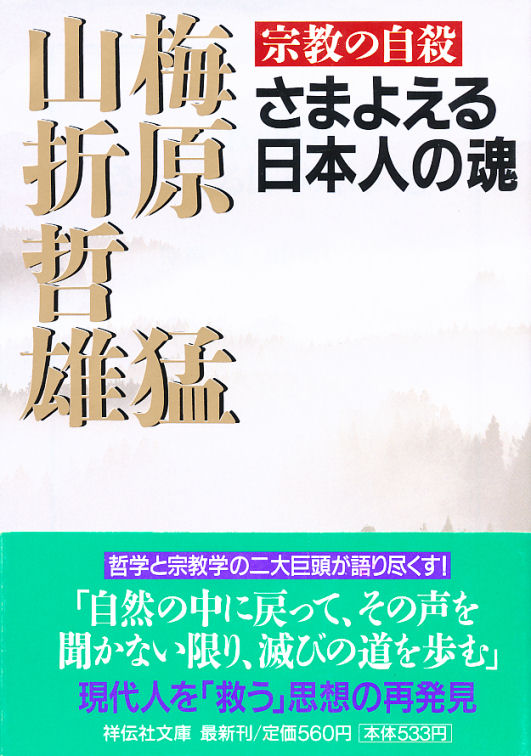
![]() 「宗教の自殺 さまよえる日本人の魂」
「宗教の自殺 さまよえる日本人の魂」
梅原猛 山折哲雄 著 祥伝社 より
|
明治以降の国家主義により古神道は改変させられ、その原点を見失った時代に私たち は立っている。わずかにアイヌや沖縄に生き残った古神道のあるべき姿から遠く離れて しまった多くの日本人の魂、この古神道という源流は仏教や西洋の個人主義の流れを 穏やかに包み込みながら日本独自の世界観を作ってきた。しかし、その源流の存在さえ 忘れてしまった現代において、オーム真理教などのようなカルトの狂気を呼び寄せる背景 を作り出している。このような危機的状況の日本人、このさまよえる日本人の魂を救うに はどのような宗教や哲学が必要なのかを、哲学と宗教の二大巨頭が語り尽くしている。 アイヌや沖縄に残った古神道の世界観(インディアンに代表される世界各地の先住民族 の世界観と共通するもの)を再生することなしに未来への希望はないかもしれない。 (K.K)
|
![]()
|
によってある程度知られているが、それだけでは靴の上から足をかくようなもので、その 文化に深く宿っている魂を研究しない限り、この日本文化の原点というべき縄文文化は 理解できないのではないかと考えた。アイヌ文化及び沖縄文化に日本の基層文化が残っ ているのではないかと思って、しばしば北海道や沖縄を訪れた。北海道では藤村久和君 と知り合い、アイヌにおいて神を表わす言葉はほとんど古代日本語と同一であることを 聞いた。おどろいたことに、アイヌの言葉に七、八世紀の日本においてもはるか昔に死 んだと思われる日本語、ラマトという言葉が残っていたのである。アイヌも古代日本人も あつく神をうやまう民族であり、両者とも自己の宗教は外から来たのではなく固有なもの であることを信じている。そのような状況の中で二つの民族が神を表わすことばを共通と いうよりは、全く同一しているのはどういうわけであろう。私は日本の古代神道とアイヌの 宗教との同一性を認めざるを得なかった。すでにこのような見解は、江戸末期にアイヌの ところにおもむき、アイヌ文化を知った国学者などにとられている見解であるが、私は改 めてアイヌの文化の中に日本の基層文化である縄文文化の名残があると認識せざるを 得なかった。アイヌの宗教こそ、沖縄の宗教と共に古神道の名残をとどめるものであると いうことになる。 (中略) 私は日本の神道は、国家主義の呪縛から脱却するのが何よ りもまず必要なことであると思う。明治以来百年間を支配した神道は、却って神道の魂を 殺してしまったのである。神道には二十一世紀において最も必要な、自然崇拝がある。 もう一度人類は自然の中に戻って、その声を素直に聞かない限り、滅びの道を歩まざる を得ないと思う。神道には自然を神とし、自然と仲良く生きる知恵が含まれているのであ る。
言葉でいっているけれども、それは、古代の人々が魂は死なないと考えていたのと、同じこ とかもしれない。どうもそんな気がしますね。私も孫ができてから痛切にそれを感じます。 どうしてこんなにおじいちゃんに、それも悪いところばかり似ているのかと思う。整理整頓 はできないし、忘れ物はするし、靴のかかとは踏みつけるし、電信柱にぶつかるところまで 似ている。学校でも、五年生にもなるのに、授業を聞いていないとよく先生に注意される。 それでも結構成績はいいらしいのだけれども。悪いところを教えたわけでもないのに、孫 のしていることを見ていると、そんなふうになっている。やはり遺伝子なんでしょう。そうい うふうに人間はできているんです。昔なら、おじいちゃんはとっくに亡くなっていただろうか ら、そういう孫が生まれてきたら、「この子はおじいちゃんの生まれ変わり」といったに違 いない。この「生まれ変わり」というのは、遺伝子の秘密を直感したいい方だったと思い ます。そのように考えると、個人を絶対化する考え方が、いかに人間の生命の法則に 矛盾しているかが見えてくる。デカルトのように、「我思う、故に我あり」の「我」だけが確実 で、そこから一切の哲学が出発するというのでは、やはりまずい。自分の中には、生命と いうものが誕生して以来の生命があり、そしてこれは未来永劫の生命につながっている のだという自覚が必要なんです。それを倫理の根底に置くべきだと思います。デカルトは 彼の小さな部屋で、近代哲学の始まりを告げる「我思う、故に我あり」という言葉をつくり 出したけれども、私は孫と故郷の田舎へ行って、そこの自然の中で新しい哲学の原理を 考えた。孫は、山へ行って蝉をとり、海へ行ってイソギンチャクと遊んだ。その蝉は六十 年前に私がとった蝉の何十代めかの子孫であろうし、そのイソギンチャクも私が遊んだ イソギンチャクの何十代めかの子孫であろう。かつて子供の私が蝉やイソギンチャクと の出会いを喜んだように、また孫がその子孫のイソギンチャクとの出会いを喜ぶ。人間 と自然の出会いが永遠に循環する。人間は自然に出会い、また次の人間も同じように 自然に出会い、そういうことが永遠に繰り返されていくのです。それが生命の本質という ことになるのではないでしょうか。昔の人々には、そのことが直感的にわかっていたのだ と思います。われわれはそこに、もう一度この人間と自然の出会いの原点にかえって、 新しい哲学の体系を生み出さなければいけないのです。
|
|
それに対して儒教からは修養、西洋からは個人主義をそれぞれ積極的に受容して、それらを うまく重層化させながら、自らの人格形成に役立ててきたのである。ただ問題なのは、それら がお互いにどのように重なり合い、どのような形でふれ合っているのかが、もう一つはっきりし ないということだ。だがともかくこれらの思想的特質がわれわれの人生観や世界観のうえに、 陰に陽に作用しているらしいことだけは確かである。これらの三つの思想的要因を、われわれ の意識の底の方で支えているのが神道的な感覚ではないかと私は思う。神道は宗教ともいえ ないような、思想ともいえないような、極度に柔らかな自然感覚にみたされたものであるのだ が、しかしこの柔軟この上ない自然との神道的な共鳴感覚が、日本人の世界観を大きく押し 包んでいることに注意しなければならない。神道は、日本古来のものであり、私自身はそう いういい方を好まないが、アニミズムといってもいいだろうし、シャーマニズムとあいかかわる 領域を共有している。天地万物に神が宿るという考え方である。そこには、教祖もいなけれ ば教義もない、積極的な宣教活動存在しない。そういう古来からの神信仰がベースにあって、 その上に仏教や儒教の考え方、西洋の個人主義が重層的に乗っかっているのではないか。 見ようによっては、多神教といってもいいし、汎神教といってもいい。キリスト教やイスラム教、 ユダヤ教のような一神教からするならば、その「一神」がいないのだから無神論的世界だと いうことになるかもしれない。そのような宗教のあり方を、一体何と名づけたらいいのか。 かつての山本七平氏のいい方にならっていえば、このいわくいいがたい多元的価値を認め る世界のありようを、「日本教」と表現することができるかもしれない。さまざまの神、仏が、 それぞれに自立性を保ちながら共存する世界である。
最近、われわれの周辺に「共生」という言葉が、氾濫するようになった。地球環境の問題や エコロジーの思想に絡んで急速に意識されるようになった用語であるが、これは宗教世界 における多元主義が日本の土壌に伝統としてあったからこそ、自然にいわれ出すようになっ たのかもしれない。その意味で、「共生」という言葉はまさに日本産の日本語という性格を はじめから荷っていたのである。しかし、「共生」だけでは、私は人生観としても宗教観とし てもきわめて不完全なものだと思う。なぜならそこには生きることに執着するある種のエゴ イズムの匂いを感ずるからだ。それに対して、「共生」という思想は「共死」の思想に裏付け られてこそ、はじめて本物になるのではないだろうか。この場合、「共死」は無常観とも深く 関わっているはずである。それだけではない。空や無の感覚ともつながっているだろう。 そしてそこにおいてはじめて、日本人の本来の宗教観は完結した像を結ぶのではないか。 日本的な「修養」や「個人主義」という観点から見ても、共に生き、共に死ぬということがあっ てはじめて人間の成熟した人格形成が可能になるという人間観が抱かれるようになったの である。その意味において「共死」という観念抜きの「共生」論はきわめて一面的なものでは ないかと思う。地球上では、今、さまざまなところで、宗教や民族の違いそれ自体が原因 となって紛争や戦争が起こっている。皮肉なことに宗教がそれ自体の力で、そういう紛争 を解決できないでいるのだ。とすれば、もはや特定の宗教が、快刀乱麻を断つがごとくに 問題を解決すると考えることの方がおかしい。伝統的な宗教は、確実に本質的な改変を 迫られているのではないだろうか。二十一世紀の宗教は、したがって教祖や教義をそな える体系化されたものではなくなっていくのかもしれない。攻撃的な自己主張をする宗教 は、すでに二十一世紀を導く宗教たりえなくなっているのではないかと私は思う。その 意味でキリスト教も仏教もイスラム教も、そろそろその歴史的な役割は終わりつつあるの かもしれない。それならばそれらに代わるべき、人類のための普遍宗教のようなものが 今後はたして生みだされるのだろうか。そのような見通しが現実のものになるのかどうか はまったくわからない。ただこの時代の大きな転換期において、多元的価値を共存させる 日本の伝統的な宗教感覚が、あるいは一つの意味ある役割を果たすことになるのでは ないだろうか。そのような可能性に私はいちるの望みを託したいと思っているのである。 とするならば日本人は、このような宗教感覚をこれから世界に向けて新鮮な言語にのせ て発信していく必要があるだろう。時代の足音に耳をすましながら、伝統的なタームによっ てではなく、より普遍的で刺激的なタームによって、それを表現していく努力を注いでいか なければならないだろう。
|
|
プロローグ 日本人が創る新しい宗教観 山折哲雄 神に嘉せられた民と呪われた民 カルトを生んだキリスト教社会 「無垢なる人間」という幻想 日本では読みかえられた善悪論 同居する因果応報と宿命論 サバイバルの思想と全滅の思想 短歌へ溶かし込む死への思い 吸収装置を失なったルサンチマン 汎神論的な日本人の宗教論 既存宗教から「日本教」の時代へ
第一章 人間は善悪を超越できるか 1 オウム真理教事件は「悪霊」の世界 類似するロシア革命とオウム事件 得体の知れない暗い情熱 革命を目指す人間は浅薄なもの 人間とは善悪を超えられない存在? 2 ルサンチマン(怨念感情)をもつ人間の幸と不幸 宗教的感性と権力志向性をもつ麻原 日本初・ルサンチマンの社会化 偉大な仕事をする源 日蓮に自己をなぞらえた麻原 誤った知性が生んだ犯罪 3 「悪人」は救われるか 真剣に探求すべき悪人救済の問題 あの世を語らない宗教は無意味 悪人が往生するための二つの条件 「歎異抄」愛好者の人生の甘さ 宗教における悪とは何か
第二章 日本の宗教 1 日本仏教の二重構造 本来葬式は重要な儀礼 統合された霊魂信仰と仏教 古来からの土着の霊魂観 2 必要な神道の見直し 宗教学の定義から外れる神道 「稲荷」から神道は始まる 全てに対応できる現世的益神 3 怨霊から守護神へ 機能を拡張する北野天満宮 道真の怨念を利用した時平 恨みの神は守護神になる 4 織田信長の宗教革命 十三世紀宗教革命の誤解 禅の五山文化が近代思想を生んだ 禅と権力の親和関係 中世武士の宗教
第三章 宗教と倫理 1 武士道と儒教倫理 嘘をいわない倫理 武士道は道徳ではない 思想家に潜む儒教 善悪を超越した心境とは 2 仏教が日本にもたらした倫理 あの世志向と菩薩行 無常観が生む現実感 儒教、仏教などが混在する日本人の思想 人間信仰こそが日本の文化 道徳は宗教なしでなりたつか 3 “共生と共死”の思想 共死と成熟の観念 宇宙大に広がる共生共死の観念
第四章 神なき時代からの脱出 1 戦後教育の反省 宮沢賢治の童話で教育 「頭も体も偏差値づけ」の問題 「知」が危うくなっている 文学さえも空洞化する時代 2 自然を取り込んだ新しい倫理の確立 「永劫回帰」が未来へのヒント 魂は山海へ行き神になる 先祖崇拝こそ日本人の根本 霊魂は遺伝子的なもの 遺伝子=魂は死なない
エピローグ 現代人を救う「思想」の再発見 梅原猛 哲学との出会い ニヒリズムからの脱却 空海の発見と衝撃 自然と人間を一体化する仏教 法然に流れる親鸞より熱い血 二度イデオロギー化された神道 古神道に見える日本土着の思想 全人類の思想は、二つの源流から始まる 宗教と距離をおく哲学者としての姿勢 既存宗教は、教義と知恵の再発見を 新興宗教は金集めを止め、現代人の心を救え
あとがき 山折哲雄
|
|
2012年4月1日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |
|
2012年4月20日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |
2015年8月16日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  縄文のヴィーナス(2012年、国宝に指定された土偶の3分の1のレプリカ) (大きな画像) 実物の「縄文のヴィーナス」はこちら 土偶が何故創られたのか様々な説がある。生命の再生、災厄などをはらう、安産のための身代わり、大地の豊穣を願うなどなど。 今後も新たな説が生まれてくると思うが、時代の背景を踏まえながら全ての先入観を捨て(完璧には不可能だとしても)、純度の 高い目で土偶に向き合う姿が求められているのかも知れない。 今から30年前、この土偶に関しての衝撃的な見解が「人間の美術 縄文の神秘」梅原猛・監修に示された(私自身、最近になって 知ったことだが)。 殆どの土偶(全てではない)に共通する客観的な事実、「土偶が女性しかも妊婦であること」、「女性の下腹部から胸にかけて線が 刻まれている(縄文草創期は不明瞭)」、「完成された後に故意に割られている」など。 アイヌ民族や東北に見られた過去の風習、妊婦が亡くなり埋葬した後に、シャーマンの老婆が墓に入り母親の腹を裂き、子供を 取り出し母親に抱かせた。 それは胎内の子供の霊をあの世に送るため、そして子供の霊の再生のための儀式だった。 また現在でもそうかも知れないが、あの世とこの世は真逆で、壊れたものはあの世では完全な姿になると信じられており、葬式の 時に死者に贈るものを故意に傷つけていた。 このような事実や背景などから、梅原猛は「土偶は死者(妊婦)を表現した像」ではないかと推察しており、そこには縄文人の深い 悲しみと再生の祈りが込められていると記している。 「縄文のヴィーナス」、現在でも創った動機は推察の域を出ないが、そこに秘められた想いを私自身も感じていかなければと思う。 縄文人に限らず、他の人類(ネアンデルタール人、デニソワ人など)や、私たち現生人類の変遷。 過去をさかのぼること、彼らのその姿はいろいろな意味で、未来を想うことと全く同じ次元に立っていると感じている。 |
![]()

Forgetful? Distracted? Foggy? How to keep your brain young | The Independent
