|
本書より引用
 アニミズムの根本は何か。それは木にも、石にも、虫にも、鳥にも、もともと、カミが宿っている アニミズムの根本は何か。それは木にも、石にも、虫にも、鳥にも、もともと、カミが宿っている
ことを認め、そういうカミでいっぱいの自然を尊重しながら生きることだ。そうすると、木は木と
して宇宙の主人公になり、山は山として主人公、ひとは誰もかれも一人ひとりが主人公になる。
自分も、また、その仲間になって、風景が生き生きしてくる。これがアニミズムの本質なのだ。
一般に、アニミズムは未開人の宗教だと言われている。しかし、ホントはそうじゃない。未開人
だって・・・・そういう人がいたとしても・・・・何千年、何万年も地球とともに生きて、悩んで、考え
考えしてきたのだから、かれらの宗教、かれらの世界観を未熟だなどと言うわけにはいかない。
かれらのなかにだって、たくさんの哲学者がいたし、宗教家もいたに違いない。そういうかれら
が信じているカミなのだから、そのカミと出会い、そのカミの声を聞くのは、われわれの側に委
ねられた仕事なのだ。
それなのに、アニミズムのカミなんてダメだ。高木から下りてきて住民に供物を要求したり、お
どろおどろしい衣装をまとって人びとを恐怖におとしいれるのが関の山だ。それは現世利益を
旨とする民俗信仰より、もっともっと低級なものだ。そういう声がやかましいくらいだ。
しかし、宗教と文化をとり違えては困る。アニミズムは始めから終わりまで、祈りのなかの出来
事であって、欲望の渦巻く文化のなかの出来事ではないのだ。現代人は霊的な力、あるいは
直感の力が衰えてしまったから、その結果によってしか宗教の真偽を判定できない。その証拠
を求めようとする。しかし、カミの証拠なんて、どこにもないのだ。

 宗教はわれわれに何をしてくれるのだろうか。こころのやすらぎを与えてくれる。もろもろの悩み 宗教はわれわれに何をしてくれるのだろうか。こころのやすらぎを与えてくれる。もろもろの悩み
から救ってくれる。
いったいどういう方法で救ってくれるのだろう。もつれた糸をほどくように、宗教という薬が熱と痛
みを取り去ってくれるのだろうか。それとも、悩みのない、やすらぎの場所に連れていってくれる
のだろうか。その場所が、天国とか、極楽とか、浄土とか呼ばれるところなのだろうかそこへ行く
地図はどうなっているのだろうか。どうしたらそこへ行けるのだろう。乗り物、交通手段は何だろ
うか。
「経典を読めばくわしく書いてありますよ」、といわれるとその通りかもしれない。しかし、経典の
文章は今日から見て時代がたちすぎている。もっと生き生きとした童話や物語につくり直すこと
はできないだろうか。銀河鉄道に乗っていく。くるみ林をとおり、奇妙な鳥を捕らえ、雨雪のしずく
を飲みながら、星々のなかを走る。何となく、自分はイーハトーヴォ(宮沢賢治が描いた一種の
ユートピア)のなかにいるように思うけれども、銀河鉄道はそこを出発してどこかにたどり着こうと
しているのかもしれない。たどり着くべきところも、イーハトーヴォの内部にあるのだろうか。
禅宗の場合は、座禅として何事かを悟るのかもしれない。悟りの世界というのは一様で、外部か
らの批判を許さないのだろうか。それとも、悟りのなかにも、ヒマラヤの崇高な風景があり、熱帯
雨林の永遠の静けさがある。海の深さがあり、草原のざわめきがある。そういう多様な悟りの風
景のなかに、自分の風景を重ねあわせるのだろうか。
浄土宗の仏教なら、修行などに気を散らされることもなく、一直線に信の世界に入りこんでしまう。
それに違いないだろうが、浄土、あの世の表現ということになると、今後の問題じゃないだろうか。
蓮の花はわが家にも咲くし、時どき鳥が来て囀る。だからここも極楽だ、とはいえない。そこの住
人、つまり自分自身が悩んで、右往左往して、およそ信とは遠い生活をしているからである。
密教の場合は、寺も人も教義も、自然のなかにスッポリ入りこんでしまってたいへん結構である。
しかし、あのマンダラ図はもっと単純化できないものだろうか。私にとっては迷路と同じだ。悪口を
いっているのではない。私自身がもともと迷路なのだから。
どうも、日本の宗教は、発達しすぎた。くどい。山・川・草・木がいつも言っていることを、一つ一つ
人間語に翻訳しなくたっていいのだ。風景そのものが、そのなかに住む人間にとって宗教なのだ。
デジャ・ビュ(既視)と呼ばれる心理学の現象がある。初めて見た風景なのに昔どこかで見た風景
とそっくりだ。不思議というのだけれど、既視として見えているものは、私風にいえば、原風景なの
だ。自分が自分であることの証拠としての忘れえぬ風景なのだ。
無数のタネが同時に発芽して、一面の花園になってしまう。そこはどこだろう。私は宗教の世界に
おいては「そこ」が「ここ」で、「ここ」が「そこ」、「この時」が「あの時」だと思っている。素直にそう信じ
ている。信じているわけじゃない。その通りにみえるのだ。

 人生というとらえどころのないものをとらえる。いや、とらえようとして悪戦苦闘していまった。人生 人生というとらえどころのないものをとらえる。いや、とらえようとして悪戦苦闘していまった。人生
は眼に見えないものである。風のようなものといってもよい。空間に刻印をのこすこともなく、時間
に目盛りをきざむこともない。形もなく、色もなく、音もない。重さもない。だからこそ、無理を承知
でその人生をとらえてみたかった。その結果、ここで見いだしたことは次のようなことであった。
第一に、人生は文化という名のカプセルに包まれていること。別のいい方をすればカプセルとそ
の中味は別だということである。
第二に、文化をシンボルの体系とすれば、人生はその中にあって特に点滅する動的な象徴のカ
プセルに入っているということ。ここで象徴というのは文化を超えた世界に衝突したときの現象と
考えることができる。そしてもちろん、その前提として文化の向う側に文化を超えた世界があると
いうことになる。文化は海のなかの島のようなものである。
第三に、人生というものは眼に見えないものである。しかし、それは眼に見えないながらも常に
形をもとうとしている。そこで、その形を望ましい姿に造形する方法がある。われわれは人生と
いうものを造形する方法について考え、「つみあげる」「けずる」という二法を用いることにした。
そしてその結果を、絵について、人物について、庭について検討してみた。
第四に、こういう作業を通じて、わずかながら、わかってきたことがある。それは人生を二つの
場所の統一として、あるいは対応・変換の体系としてとらえるということである。ものの置かれて
いる場所とそれを映す場所、あるいは物と鏡、あるいは現世と他界。これらの二つの場所が構
成する空間に人生というものが出没し、去来しているということである。
第五に、鏡というと、すぐさま、ガラスの鏡を思いうかべるけれども、ほんとうは生死の場が鏡な
のである。その場が、その場だけが現世と他界、二つの世界を同時に映すことができる。鏡と
いうのは、眼に見えるものと同時に、眼に見えないものを映すから鏡なのである。人生はそこに
映っている。
第六に、その場、その場を言葉で解説することはできない。しかし、その場の風景として示すこ
とはできる。紙芝居のように、一枚一枚の風景を示し、それを重ね、それを取り換えていく。そう
いう方法によって人生を示唆することができる。
第七に、この小論を書いてきて、あるいは読んでくださって、何がわかっただろうか。私のいい
たいことは左の通りである。
人類が文化という名前の籠のなかにとじこめられていると、間もなく死ぬだろうということ。しか
し、文化の中にいて同時に文化を超えた世界に触れ、そこに出入りすることができるようになる
と、よりよく生きることができるだろうということ。もちろん、人間は無限に生きるわけではない。
しかし、文化を超えたものに触れると、それ以前とくらべて生死のかたちが違ってくる。簡単に
いうと、それまでは一人旅、それからは二人旅となる。一人はいうまでもなく自分自身、もう一人
は伝統的な用法にしたがって仏といってもよい。他者といってもよい。大地といってもよい。もっ
と簡単に地(じ)といってもよい。地(じ)が他者で柄が自分自身。
生死の単位が違ってくるのである。林のなかで巨木の梢がゆさゆさとゆれている。そういう処で、
その木の下で死んだら、死がすこしも怖ろしくないような気がする。しかし、われわれは現代人
だから、そんなことは考えもしない。不必要であるというかもしれない。それはそれでよい。しか
し、それでは巨木は悲しむだろう。
|
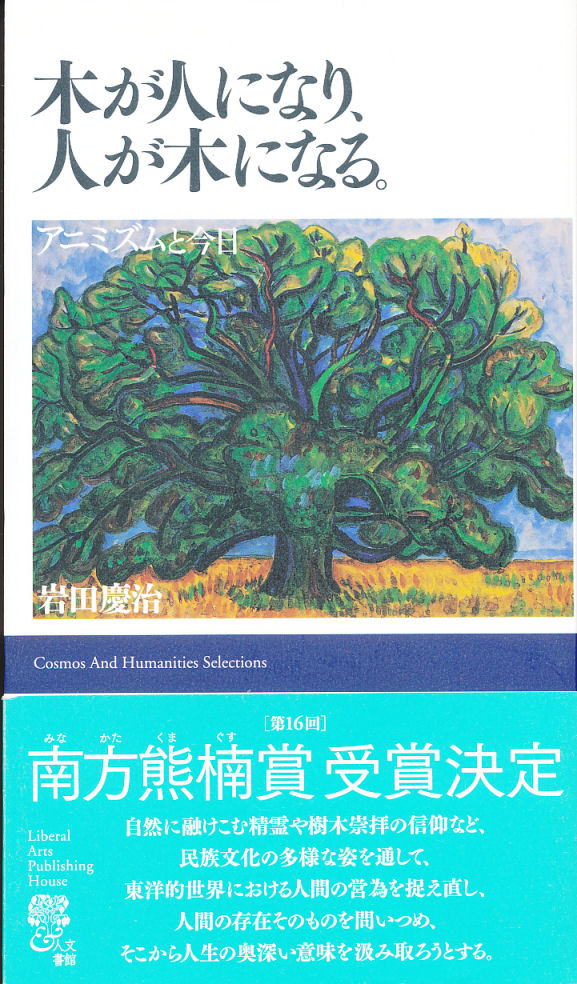
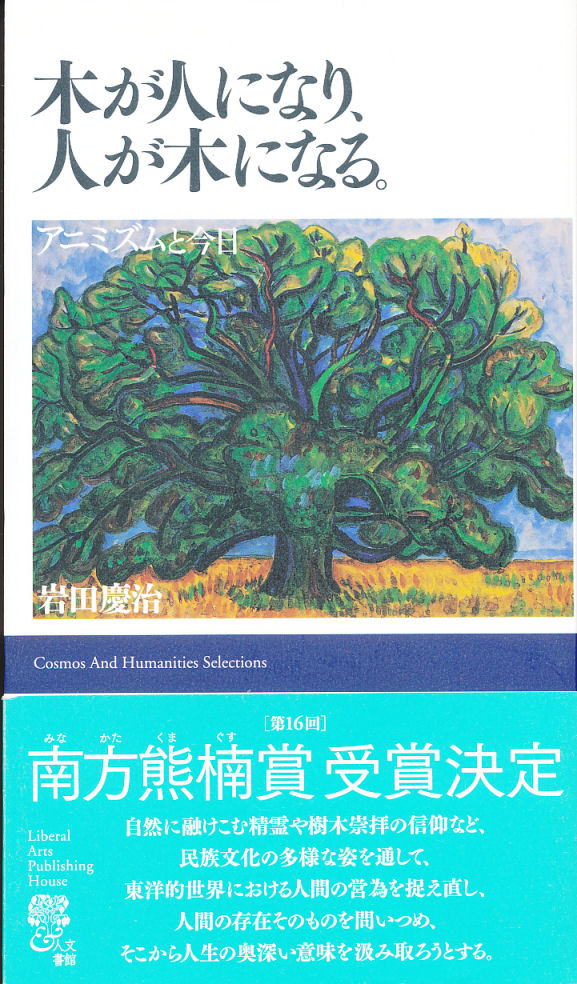
![]() 「木が人になり、人が木になる。 アニミズムと今日」
「木が人になり、人が木になる。 アニミズムと今日」
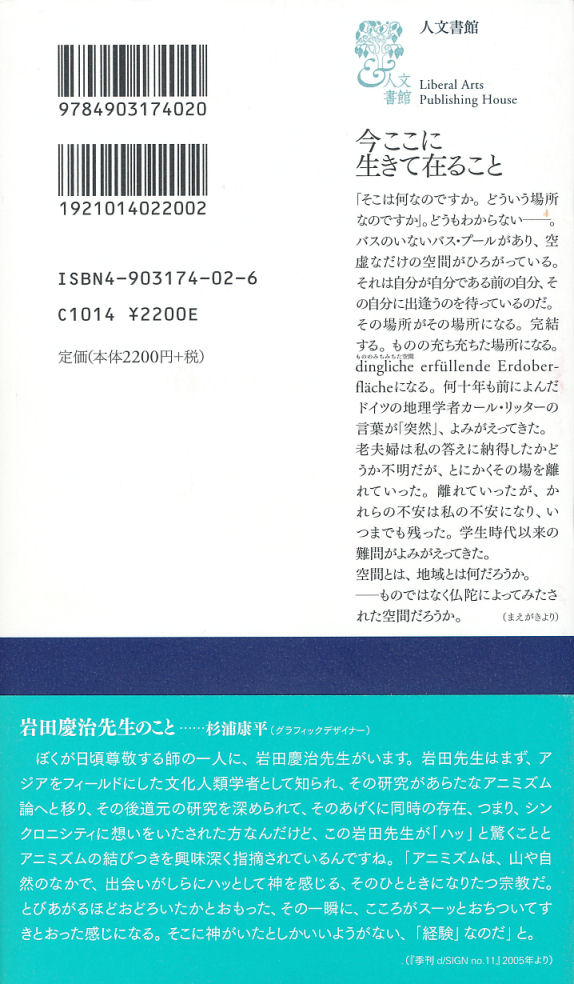
![]()
![]()
![]()

